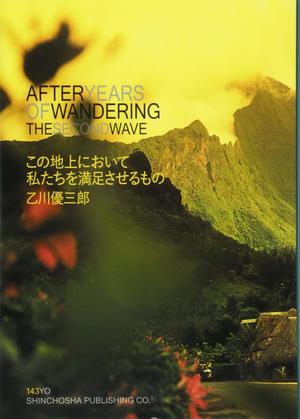前作『二十五年後の読書』と対を成す
“完璧に美しい小説”、堂々完成!
「いつもより早い朝明け。/いつもより姦(かしま)しい鳥たち。/いつもより濃いコーヒーを飲みたくて起きてしまう。少しずれた太陽の仕業か、嵌め殺しの窓が明るい」――本書は、ほとばしることばの奔流によって幕をあける。
この1巻は、過日、この書評で扱った乙川優三郎の『二十五年後の読書』と対を成す力作である。前作は作家と書評家という1組の男女を軸とした至高の小説をめぐる物語だったが、本書は、小説家、高橋光洋の人生の軌跡を追った十篇の作品から成立している。
巻頭の1作「学ぶソニア」は、光洋が終の棲家と決めた房総の住居で、住み込みの家政婦、フィリピン人のソニアとのささやかな日常からはじまる。その中で既に71歳になり、いつ心臓の発作が起きてもおかしくない自分の越し方を回想しはじめる。
およそ豊かさとは無縁であった終戦直後の暮らしから、一家離散の如く解体されてゆく家族。そして製鉄所に勤め、組合運動のリーダー、木辺と知り合いになった光洋が、文学と音楽になぐさめを求めつつ、その一方で、野党の政治家をも取り込み、自らも政界に打って出る木辺の組合運動の正体を知る。が、そのとき、光洋も木辺からいままで手にしたこともないような分け前をもらう。
そこから、パリ、スペイン、フィリピンと、光洋の魂の彷徨がはじまる。光洋が、理想に向かって一生飢えつづけ、一生燃えつづけるであろう女性画家、武藤泰子と出会い、ショッキングな結末ながら妙に座りの良い「丘の上の下町」、ヘミングウェイの息子を自称するダンディな乞食と聖女を思わせるメイドと陽気なサンダル売りの一家との邂逅を描く「乞食と女中とサンダル売り」、そしてボクサーを志す少年の「ひとりの娘を貧困から救って自足する男の目」に民族の良心を見る「反逆者製作所」を経て光洋は日本に帰ってくる。
実際、この旅の行程はヘミングウェイの“ニック・アダムスもの”を読んでいるようでとても興味深い。
これらと「ムジカノッサの夜」が前半5篇で、日本に帰った光洋は、ある女性編集者と内縁関係となるが、彼女を癌で喪ってしまう。そして驚くなかれ、前半5篇は、後半5篇の伏線であり、この伏線は見事なまでに回収されてゆき、かつ最終的には1つのピースとなって『二十五年後の読書』で語られていた“完璧に美しい小説”を現出させるではないか。至福の時間を約束してくれる1巻といえよう。
記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。