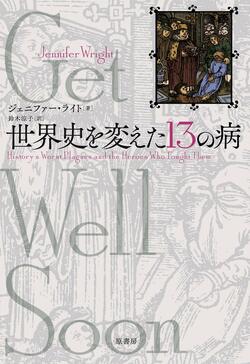ここ1年半の将棋界はほとんど機能停止の状態であった。プロの公式戦こそ行われたが、それだけだった。細々とオンラインでファンサービスが行われるのみであった。なにせ不要不急の最たるものである。ファンに夢を売るという大義はあるものの、所詮世の中にあってもなくてもいいものなのだ。飲食、観光、運輸の次にしんどかったのは娯楽産業であろう。
コロナは凄かった。人は皆病気が恐い。だから流行り病は時として世界を変える力を持った。
ジェニファー・ライト(鈴木涼子訳)『世界史を変えた13の病』(原書房、2018)は天然痘、ペストなどの強力な病気が、いかに世界の歴史に影響を与えたかを細かく書いた本である。ちなみにこの本はコロナ禍の2年前に出版されているにもかかわらずさほど話題にならなかった。おそらくタイトルが「病」だったからだろう(「感染症」としていれば!)。
この本の特徴は、医学的な見地をほぼ無視して、歴史の視点から書かれていることだ。ハッとさせられるのは、危機の時こそ時の政治家の力量が問われ、ときには国を亡ぼしたり、人心を乱すということである。古代ローマをおそった疫病においては「街に溢れる死体の山を片づけるための政策が決定的に重要」だった。死体を見ると人間は無条件で不安になるそうである。また、疫病が流行ると「国境に派遣する戦士が減るので、他国の侵略に気をつけねばならなかった」という今の世にも通ずることが古代ローマにおいて語られている。コロナが終息したとしても、歴史の教訓として読み継がれていい本である。
同じ世界史における本だが、ブノワ・フランクバルム(神田順子、村上尚子、田辺希久子訳)『酔っぱらいが変えた世界史』(原書房、2021年)は異色の本である。タイトルがすべてだ。世界史を変えた出来事、その中心人物が、いかに酒に溺れていたかがこれでもかというように書かれている。ピラミッドを造らせるのに欠かせなかったのはビールだ、ぐらいなら、うんうん知ってるよとなるが、フランス革命の裏側にはワイン税に対する不平不満の爆発があったとか、マルクスもレーニンもとんでもない酔っぱらいだった、などは、やはりニヤリとさせられる。ソ連がらみでやはりおもしろかったのが、日露戦争の旅順攻防戦の最前線のロシア兵士に、なにがともあれと1万ケースのウォッカを届け、それで兵士達の士気が、突然ぐんと上がった、というエピソードだ。
特に中世の王室の酒への耽溺ぶりが凄い。よく考えてみれば、歴史の表舞台にいたのは、貴族であり、思想家なのだが、そんな高級な暮らしをしていた人間はヒマだらけで身のまわりのことをしなくてよかったわけだから酒ばかり飲んでいたに違いないのだ。
権力者から庶民まで、ヒトは酔っぱらってばかり。その物語には、正史ではない裏面史として、強いリアリティがある(ちなみに将棋界の歴史も酔っぱらいの歴史だ。決して表に出ないが)。
*
私がはじめて週刊誌というものを手に取ったのは中学生の時だった。手にしたのは「週刊新潮」であった。世間を知らない中学生にとって、そこには、圧倒的な「大人の世界」があった。そしてなにより、性的だけではない、「いやらしさ」に満ち溢れていた。
柳澤健『2016年の週刊文春』(光文社、2020年)は、そんな週刊誌と、版元である出版社の歴史を、設立から現在まで描いた本である。
この本に描かれているのは、表現、そして報道をする者たちの、狂ったような熱量である。ひとつの会社における見事なまでの活気だ。1冊の本、1冊の週刊誌を売るために、1冊でも多く売るために、現場の記者は体を張り、それを上層部が支えてゆく。人事のことまで書かれているこの本は、ひとつのユニークな最前線の物語である。
私は、子供を殺された親の家のインターホンがどうしても押せずにその夜に酩酊した記者を知っている。「こんなことをなんでしなければいけないんだ――」と号泣した彼女に上司はぽつりといった。「仕事だからだよ」
私は週刊誌に殺人事件が取り上げられるのを読むと、必ずあの夜のことを思い出す。
この本には現場の苦悩、汗、熱、そして現場に伸び伸びとした仕事をさせるための上の苦心が書かれている。
もっとも酒のはなしは、初期の作家のこと以外ほとんど書かれていない。裏側を知り尽くしたであろう著者にはぜひ『酔っぱらいたちの週刊文春』という続編を期待したいところである。
記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。