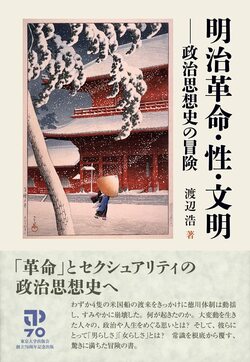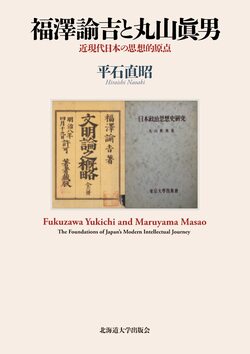「中国は、永く続き、今も続いているデモクラシーの実例なのである」(41頁)。渡辺浩『明治革命・性・文明――政治思想史の冒険』(東京大学出版会、2021)は真顔でそのように言う。無論、中国政府のプロパガンダを真に受けたからではない。学問的に真面目な主張である。
だが、どうすればそのような一見荒唐無稽な結論にたどり着くのか。鍵はA・トクヴィルという思想家にある。1805年に生まれ1859年に死んだ。19世紀のフランスの人である。主著としてはアメリカ滞在中の見聞を記した『アメリカのデモクラシー』が知られている。
このトクヴィルはアメリカに「デモクラシー」を発見した。何を当たり前のことを、と言われるかもしれない。だが、ここでトクヴィルのいう「デモクラシー」の理解が実に独特なものであることに注意しよう。デモクラシーといえば通常は王様がいない政治体制のことだ。しかしトクヴィルの言う「デモクラシー」はそうではない。それは社会の状態で、人々の間の「条件」が平等になっていくことなのである。人々の間の身分や生活様式の違いがなくなり互いに似通った存在になっていくこと、それをトクヴィルは「デモクラシー」と呼んだ。
わかりにくいだろうか。そういう方は今の世界を思い浮かべてほしい。もちろん貧富の格差は依然として大きい。だがそれは身分や生活様式の違いでは実のところない。金持ちも貧乏人も携帯電話を持ち目の前の小さい液晶画面を見つめている。この生活の根本的似たり寄ったり感。これをトクヴィルは「デモクラシー」と呼び、アメリカの中に発見した。そしてトクヴィルが予見した通り、それは今や世界を覆いつくしている。
重要なことは、この意味での「デモクラシー」は政治的権力の集中と矛盾しないということである。そのためトクヴィルの定義では、「王様がいるデモクラシー」は決して語義矛盾などではない。また「デモクラティックな専制」さえもあり得る。
ここで冒頭の謎が解ける。そうなのだ。日本政治思想史を専門とし中国思想への深い造詣でも知られる渡辺は、トクヴィルがアメリカの中に発見したものを中国大陸に見出す。もちろん中国大陸の方がはるかに早い。皇帝権力が貴族層を破壊し、科挙によるエリート選抜制度が確立した宋代(実に10世紀)に中国大陸はすでに「デモクラシー」に到達したのである。
アメリカがたどり着いた場所など「我々が2000年前(というとこの場合やや大げさだが:評者注)に通過した場所だッッッ」(『グラップラー刃牙』)とも言わんばかりの中国中心史観が(西洋中心史観を解毒するために)おそらく意図的に採用される。本書で上演される、明治日本を舞台としためくるめく「政治思想史の冒険」 については、直接読んで堪能していただきたい。
話をトクヴィルに戻そう。トクヴィルは、彼が「新大陸」に発見したと信じた「デモクラシー」を無条件に肯定し、礼賛したのではもちろんなかった。それどころか、こうした「諸条件の平等」としてのデモクラシーはそのまま歯止めがかけられなければ「柔らかな専制」に至る。トクヴィルはそう危惧した。
その歯止めは、意外なことに、「旧大陸」の古い智慧から汲みだされた。貴族政の機能的代替物としての法律エリートと、その影響力を浸透させる装置としての陪審制。社会的紐帯の維持培養装置としての既存の宗教。貴族の徳や宗教的信仰、一見古臭く時代遅れに見えるものが実は果たしている機能の大きさへの着目が、トクヴィル『アメリカのデモクラシー』の精髄である。物事をそれ自体の価値というよりは、それが結果として果たす機能の観点から評価する、冷徹でペシミスティックな〈悪い〉思考をそこに見てとることもできよう。
明治の日本人は実によくトクヴィルを読んだ。だが、明治日本人のトクヴィル受容を丹念に追跡した柳愛林『トクヴィルと明治思想史 〈デモクラシー〉の発見と忘却』(白水社、2021)が教えてくれるのは、上記のいわば〈黒トクヴィル〉の側面に気づいた論者は意外に少なかったということだ。トクヴィルの言う「平等」がはらむ深い屈折には思い至らず、字面そのままになんとなく良いものとみなしたままで、トクヴィルを素朴な「平等」論者として持ち上げる人。トクヴィルがキリスト教に対してとった微妙な態度が持つ複雑なニュアンスにもやはり同様に気づくことなく、単なるキリスト教擁護論者としてトクヴィルを持ち上げる人。あるいは単に〈地方自治は大切です〉といいたいがためだけに彼の名前を護符のように使う人。もっとも現代日本人の標準的読解レベルとてこれら明治の人々とどれほど違っているのかはやや心もとないのであるが。
例外は、伊藤博文と福澤諭吉である。多数の英書に親しんでいた伊藤は、日本初の女子留学生として渡米した津田梅子に『アメリカのデモクラシー』を薦めたという。伊藤がトクヴィルに学んだ最大のことはまさにアメリカにおける宗教の機能であり、その機能的代替物を我が国に探し求めることであった、と柳は見る。周知のように伊藤の解答は「機軸」としての皇室である(「我国ニ在テ機軸トスベキハ独リ皇室アルノミ」)。
福澤も深くトクヴィルに学んだ。滅び去るべきかに見える旧時代の遺物が実は、新たな時代のデモクラシーを健全に制御する装置に転生し得るということ。そうした発想を福澤はトクヴィルの書物から得た。西南戦争と西郷隆盛の死の後、死地を求めるようにして右往左往する不平士族の持つエネルギーを、地方自治を担う健全なエトスへと変換せしめることはできないか。『分権論』(明治10年)という書物を書き上げたとき、江戸の旧弊をうち捨て新文明の進歩発展の趨勢に観照的にのみ向き合う「文明の理論家」福澤は姿を消した。そして同時に「封建」の遺産を積極的に活用してでも現実政治の改善を志向する「政治思想家」としての福澤が誕生する。緻密なテクスト解釈を通して福澤の「戦略構想」を読み解く平石直昭『福澤諭吉と丸山眞男 近現代日本の思想的原点』(北海道大学出版会、2021)が到達した一つの結論である。
この三冊を座右に置き、トクヴィルを導きの糸として、近代日本における「政治思想の冒険」の旅に出るのも悪くない。
記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。