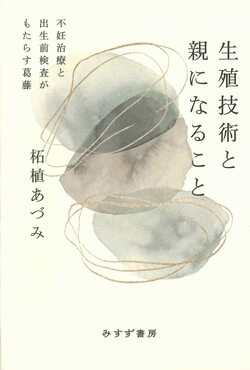ある日突然、母親に「あなたはお父さんの子どもではない」と告げられた子どもの衝撃が想像できるだろうか。両親に騙されていた。自分が何者か分からない。精子の提供者を知りたい。けれど情報がない――。喪失感や怒りに苛まれている子どもが、日本にも少なからず存在する。
日本では70年以上も精子提供による非配偶者間人工授精(AID)が行われ、近年は卵子提供で生まれる子どもも増えているが、精子/卵子提供で生まれた子どもが提供者の情報を求める「出自を知る権利」に関しては、未だに法整備が進んでいない。2020年12月に成立した生殖補助医療法では、民法の特例として生まれた子どもの父と母を明確にした以外は具体的な議論が先送りされ、附則に「2年を目途に検討する」と記された。その2年が経過した今年の通常国会では、生殖補助医療法改正(あるいは新法の制定)が1つの焦点となりそうだ。
そこで、長年にわたって生殖補助医療の当事者にインタビューを行ってきた明治学院大学社会学部の柘植あづみ教授とジャーナリストの大野和基氏に生殖補助医療法の問題やオーストラリア・ビクトリア州の先進的な取り組み、具体的な当事者の事例などについて語ってもらった。
柘植教授も大野氏も2022年に著書を上梓しており、柘植教授の『生殖技術と親になること 不妊治療と出生前検査がもたらす葛藤』(みすず書房)は生殖補助医療全般に関して、大野氏の『私の半分はどこから来たのか AIDで生まれた子の苦悩』(朝日新聞出版)は主にAIDに関して、当事者のさまざまな思いを描いている。
柘植 日本では1948年から慶應義塾大学病院で夫に不妊の原因がある夫婦に対して精子提供が行われ、70年余りの間に1万~2万人とも言われる子どもが生まれましたが、親子関係について定めた法律がなかったためさまざまな法的トラブルが起きてきた。離婚時の親権争いにおいて、子どもが精子提供で生まれたことを母親が明かし、「夫は親権を得られない」と訴えるケースや、夫が亡くなった後に凍結していた精子を使って子どもを生んだ場合に夫が父親として認められるかが争われたケースなどです。

そこで厚生労働省や法務省が法整備の検討を進め、2003年に厚労省は報告書を、法務省は中間試案を発表し、それから20年弱経った2020年12月にようやく生殖補助医療法が成立しました。精子/卵子提供で生まれた子の父親/母親は誰かが明記され、精子提供では子どもを出産した女性の夫を父親、卵子提供では子どもを出産した女性を母親とし、実質的に精子/卵子提供を認めた。
しかし、これ以外、重要な事柄について具体的なことが何も書かれませんでした。たとえば「出自を知る権利」です。「出自を知る権利」とは、精子提供や卵子提供で生まれた子どもがその事実を知り、さらに精子/卵子提供者について情報開示を求める権利のこと。2003年の試案では、子どもが望んだ場合に出自を教えられるような情報管理システムをつくることが書かれていましたが、法案からは削られていた。
こうした状況に、精子/卵子提供で生まれた当事者たちは怒りに震えていました。法案が国会で審議された当時、私は何度も議員会館に足を運び、この法案では不十分であることを議員の方々に訴えましたが、結局法案は成立し、「出自を知る権利」や精子/卵子提供の規制、代理出産などの課題は先送りされ、附則に「2年を目途に検討する」と書かれた。昨年12月に2年が経ちましたが、議論はあまり進んでいません。
アイデンティティの喪失

大野 「出自を知る権利」は、自分がかかる可能性のある遺伝性の病気について聞くことができない、結婚しようとしている相手ともしかしたら血がつながっているかもしれないといった問題だけでなく、アイデンティティの問題にも関わります。
私が取材をした加藤英明さんは、医学生の時に授業の一環で血液検査をしたところ、白血球の型から父親と血がつながっていないことが分かった。母親に理由を尋ね、自分がAIDで生まれたことを聞かされたのです。彼はショックを受け、「自分のアイデンティティの半分が宙に浮いているような感じになった」と言います。
彼の母親は慶應義塾大学病院から紹介を受けたクリニックで精子提供を受けました。当時は医学生がアルバイト感覚で精子を提供することが多く、匿名で提供すること、子どもにも秘密にすることが前提でした。提供した側は軽い気持ちでも、何らかの形で事実を知った子どもは大きな喪失感を覚える。
日本で「出自を知る権利」というと、全く情報を教えないか、身体的特徴から趣味や特技、さらに名前、住所まで全て教えるか、ゼロか100かで捉えられがちです。けれど、情報にもいろいろなものがあり、実際に会えなくても、身元が分からなくても、身長や子ども時代の写真、数学が得意であるとかマラソン選手であったとかいうことを知るだけでも、子どもにとっては救いになると思います。
柘植 日本で「出自を知る権利」が議論されるようになったきっかけの1つが、2002年に2人の当事者がメディアで名乗り出て、提供者について知りたいと発信を始めたことでした。
その1人である石塚幸子さんは、父親が患っていた遺伝性の病気について悩んでいた大学院生の時に、母親から父親と血がつながっていないと告げられました。彼女は提供者を父親だと思っているわけではないけれども、提供者に会いたいと言う。普通の子どもは両親の人間的な関係性の中から生まれてくるけれど、自分は母親と提供者の精子で生まれた。人工的につくられたようで嫌だから、精子の向こうに人間がいたんだということを確認したいと話していました。
告知を受ける年齢が重要
大野 私は海外でAIDによって生まれた当事者にも話を聞いてきましたが、告知を受ける年齢も重要だと感じました。
ロンドンに住むトム・エリスさんは、父親とうまくいっていなかった母親のカウンセリングに同席した21歳の時、事実を知りました。母親は子どもにとってそれがどれほど大きなことなのかを全く分かっておらず、セラピストに話すついでに子どもにも告知をした。エリスさんはそれ以来、軽率な母親に対する激しい怒りを抱え、精子の提供者を探し始めた。
また、オーストラリアに住むキム・バックさんが母親との喧嘩中に「あなたは精子提供で生まれた子なのよ!」と言われたのは、16歳の時でした。深く傷つき、提供者を探そうとしましたが、AIDを行ったクリニックには記録が残っていなかった。
その一方で、オーストラリアに住むコーリー・ロークスとアーロン・ロークス兄弟はいずれも小さい頃に告知を受け、今も良好な家族関係が続いています。提供者に会いたいとも思わないそうです。
大人になってから知るよりも、小さい頃に知った方が事実を受け入れ易い。
柘植 私が2003年にオーストラリアのビクトリア州でインタビューした女性も、5歳の誕生日に両親からAIDで生まれたことを聞き、その後も両親と良好な関係が続いていました。
彼女は精子を提供した人に会いたいと望み、両親も同意したうえでメディアに出て提供者に呼び掛けましたが、見つかっていません。彼女も石塚さんと同じように、「精子提供者がモノではなく、人だということを知りたい」と話していました。
オーストラリア・ビクトリア州の取り組み

大野 「出自を知る権利」について先進的な取り組みを行っているのが、オーストラリアのビクトリア州です。1984年から約30年かけて段階的に法整備を行い、直近の2016年改正法では、精子/卵子提供で生まれた子どもは誰でも、たとえ匿名で提供されていた時代に生まれた子どもでも、情報を請求することができるようになりました。さらに、以前は提供者の同意がなければ情報は開示されませんでしたが、同意がなくても開示されることになった。
この改正法は、長年オーストラリアで「出自を知る権利」を訴えてきたナレル・グリッチさんの名前を取ってナレル法と呼ばれています。彼女は15歳の時に自分がAIDで生まれたことを知り、生物学上の父親を探し続け、ついに会うことができた。それは彼女が30歳の若さでガンにより亡くなる直前のことでした。
柘植 ビクトリア州の取り組みは凄いですよね。精子/卵子提供で生まれた全ての子どもが提供者を知ることができるというベースがあり、それを実現するために、州が親、提供者、子どものカウンセリングに加え、情報の登録・管理・提供を行う決まりになっています。
州の情報管理機関は、提供者の情報を登録していなかった時代(1998年以前)に行われた提供精子によって生まれた子どもの要望にもできるだけ対応しようと、子どもから請求があれば提供者の同意を得ずに情報を開示することを決めました。提供者は自発的に自分の情報を登録し、生まれた子どもが成長してからなら、その子に連絡を取る希望を出せます。
また、ビクトリア州では子どもへ精子/卵子提供で生まれてきたことを知らせるよう推奨しており、かりに親が子どもに事実を知らせなかったとしても、出生証明書に配偶子の提供者がかかわっていることが分かる情報が書いてあり、情報管理機関に連絡をすれば事実が分かるようになっている。
そして、子どもが精神的に「成熟している」と確認できれば、年齢に関係なく提供者の情報を求めることができ、望めば面会もできる。
大野 コーディネーターが双方の間に立って面会が大丈夫か確認してから会わせるんですよね。こうしたカウンセリングが入ると、お互いに安心できる。日本はカウンセリングの態勢も不十分だと思います。
柘植 私もそう思います。
生殖補助医療法で「2年を目途に検討する」とされた「出自を知る権利」などの法制化について、2022年3月に超党派の議員連盟が骨子案を発表しました。その中に、子どもが情報管理機関に問い合わせることができると書いてあるのですが、管理機関が提供者に子どもへの情報提供の可否を問い合わせ、「いい」と言われれば伝えるけれど、「ダメ」と言われればそこで終わり。あまりに事務的な内容だと感じました。
子どもと提供者の間に入って双方の相談に乗り、場合によっては心理カウンセラーを紹介するコーディネーターが必要です。コーディネーターが提供者に、子どもがどのような気持ちで要請を出しているのか、どのようなことを知りたがっているのかを伝えたり、子どもに伝える情報について、名前や住所がだめなら趣味や特技だけでも——といった交渉をしたりしても良い。提供者の気持ちが時間の経過とともに変わる可能性もあるので、問い合わせは1回きりではなく、5年や10年に1回ずつ行っても良いと思います。
大野 慶應義塾大学病院は、提供の際に「将来、生まれた子どもからの求めに応じて情報を提供する場合もある」と言うようになってから提供者が減ったそうですが、そこにもカウンセリングの問題があると思います。
柘植 ある日突然、子どもが会いに来るわけではなく、安全な場で面会が行われるということを説明しないと、提供者も応じにくいですよね。
精子提供を行っている都内のクリニックでは、以前は匿名での提供でしたが、現在は「将来、子どもが情報を知りたいと言ったら教えても良いか」と聞き、「良い」と答えた非匿名(子どもが希望したら名前等を知らせて良いとした人)の人の精子も提供しています。
だんだんと提供者のタイプや動機も変わってきているようですね。先ほどお話ししたように、以前は医学生がアルバイトで提供することが多かったですが、今は子どもがいて幸せに暮らしている人が、もう自分はこれ以上子どもをつくらないし、他の人のためになるなら――というボランティアに近い感覚で、妻に相談したうえで提供するケースが増えている。
世界最大の精子バンク
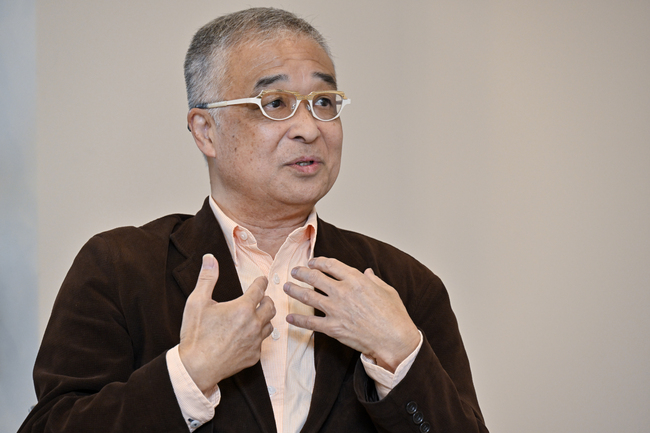
大野 私はデンマークの世界最大の精子バンク「クリオス・インターナショナル」にも取材をしましたが、クリオスでも提供者が匿名か非匿名かを選べるようになっています。
ビジネスとして精子を提供することに最初は抵抗感を覚えましたが、精子はマイナス140℃以下で凍結保存しなければならず、遺伝子検査、輸送、提供者の情報管理にも費用がかかるので、無償ではできない。
柘植 ビクトリア州ではカウンセリングや情報管理に関わる費用は税金で賄われます(一部は自費)が、クリオスでは受益者負担で料金に転嫁される。ビジネスが全て悪いとは思いませんが、中にはいい加減な企業や潰れてしまう企業もあるので、私は公的な情報管理機関があった方が良いと思います。
大野 創業者のオーレ・スコウ氏は、不妊カップルやレズビアンのカップル、シングルの人が子どもを持つ可能性を開くことがミッションだと話していました。クリオスから精子提供を受けて出産したシングルマザーやレズビアンのカップルにも会いましたが、みな心から子どもを欲し、愛情を注いでいた。いろいろな新しい家族の形がある。
一昨年は、SNSで高学歴の日本人男性に精子提供を呼びかけて子どもを生んだ女性が、相手の学歴と国籍が嘘だったことを知って子どもの引き取りを拒否したケースがありましたね。何の検査も保証もないまま行われるSNSでの取引に対し、クリオスは遺伝病や感染病の厳格な検査をクリアした精子しか扱わないため、より安全だとスコウ氏は言います。
柘植 このSNSの事件はちょっと信じられませんでした。
大野 過去に代理出産でも、生まれてきた子どもにダウン症やエイズが見つかったため、引き取りを拒否したケースがありましたね。
二重の遺伝子スクリーニング
柘植 代理出産は高額な料金を支払っている分、何かあった時に拒否感情が出てしまうと考えられますよね。
私は現在、日本でも増えつつある卵子提供について当事者のインタビューを行っているのですが、卵子は精子よりも高額で取引されるので、精子よりも多くの遺伝子検査を行ってもペイできるということで、かなり提供者の遺伝子スクリーニングがされているようです。そのうえ受精卵の着床前検査、さらに妊娠後に出生前検査も受ければ、二重、三重の遺伝子スクリーニングになる。でも、もしそれで生まれてきた子どもに病気や障害があったら、より強い拒絶感情が出るのではないかと心配になりました。
出生前検査がなかったとき、半世紀以上前は、子どもを産みました、その子どもに病気がありました、でも育てていくしかないという時代でした。育ててみたら、子どもがかわいい、子育てが楽しいという方も少なくないと思います。それに対して現在は、育てていくしかないでしょうとは思えないから、何とかしようと出生前検査を受ける。けれど、検査で異常がなかったのに生まれてから病気や障害が見つかり、悶々としてしまうケースがある。
こうした技術が進んだことで、検査を受けるのか受けないのか、検査結果をどう捉えるのか、生むのか生まないのか、生んだことをどう思うのか、以前よりもたくさんの難しい選択をしなければならなくなった。私たちはそういう社会を望んでいるのでしょうか。
生殖補助医療で幸せになったのか
大野 生殖補助医療を受ける時には、どんな子どもが生まれてきても育てるのだという覚悟が必要です。
柘植 私は30年程、当事者へのインタビューを通して生殖補助医療について考えてきました。生殖補助医療は「健康な子どもが欲しい」という希望を叶え、人を幸せにするという前提で技術が進み、最近では出生前診断や精子/卵子提供、代理出産に加え、子宮移植の研究も行われています。
けれど、私がこれまでに出会った当事者の方々は、子どもを持てた喜びだけでなく、不妊や不妊治療の苦悩、出生前診断や精子/卵子提供をめぐる躊躇や葛藤など、本当にさまざまな思いを抱えています。
生殖補助医療が良い悪いではなく、こうした技術で私たちは本当に幸せになったのか、そもそも幸せになるとはどういうことで、親になるとはいかなることなのか、改めて考えないといけないと思っています。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。