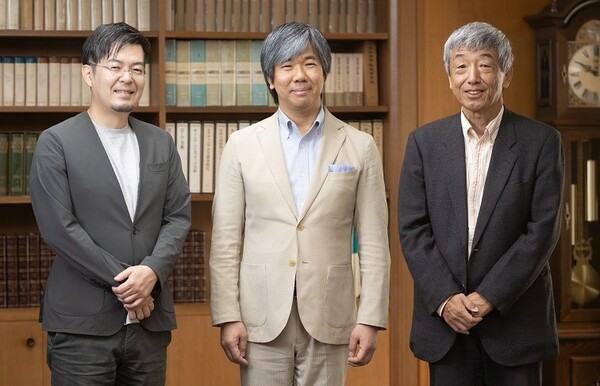
1989年11月に「ベルリンの壁」が崩壊し、世界中の人々が「これで世界は平和になる」と寿いだ。しかし、国際政治学者の高坂正堯(1934~1996年)は、その直後に「歴史としての二十世紀」と題する連続講演を行い、戦争の再来について警鐘を鳴らした。
高坂はなぜ戦争の再来を「予言」できたのか――その連続講演を書籍化した『歴史としての二十世紀』(新潮選書)刊行を機に、国際政治と安全保障を研究している田所昌幸(国際大学特任教授)、細谷雄一(慶應義塾大学教授)、小泉悠(東京大学専任講師)の3氏が鼎談した。
* * *
「少数派」だった高坂先生
細谷 『歴史としての二十世紀』が刊行されるにあたり、私は「はじめに」と「解題」を執筆させていただきました。もっとも、私自身は高坂先生と交流があったわけではありません。生(なま)でお見かけしたのも、高坂先生が1996年に亡くなる前年、慶應義塾大学の秋の三田祭に講演でいらしたときの一度だけ。もちろん、言葉を交わしたりはしていません。
そこで今日、高坂先生について話し合うにあたり、京都大学の高坂ゼミのご出身である田所昌幸先生にいらしていただきました。田所先生は、本書の元となる講演が行われた1990年前後も高坂先生と直接接しておられたと思いますので、ぜひ当時のお話をお伺いできればと思っています。
一方で、高坂先生が亡くなってから27年が経ち、高坂正堯という名前を聞いてもピンと来ないという若い方も多いかと思います。そこで私よりも若い世代の視点から高坂先生を語っていただこうと考え、小泉悠先生にお声がけさせていただきました。本書には小泉さんのご専門の軍事の話も結構入っているので、そのあたりについても後ほどお話を伺えればと思っています。
田所 高坂門下で言えば、中西輝政さん(1947年生まれ)の世代が一番上、その後に私や坂元一哉さんの世代(いずれも1956年生まれ)がいて、さらに中西寛さん(1962年生まれ)や岩間陽子さん(1964年生まれ)の世代が続くという形です。
今からすれば意外に思われるかもしれませんが、当時の知的状況の中では高坂先生は必ずしも主流派ではなく、と言うよりむしろ圧倒的な少数派でした。学生の間でもそんなに人気があるわけではなく、高坂ゼミに入る時も特に苦労することなくすんなりと入れました。
今回の鼎談にあたり、『歴史としての二十世紀』の本だけではなく、元となったカセットテープの音声も聞いてみたのですが、やはりあの京都弁の独特な語り口を聴くと、当時の個人的な想い出がばあっと蘇ってきます。そんな具合ですから、私は高坂先生を客観的に語るには不向きな人間なので、むしろそこは小泉先生に期待したいと思います。
小泉 私は1982年生まれなので、『歴史としての二十世紀』の講演が行われた時には8歳、高坂先生が亡くなられた時もまだ中学生なので、細谷先生のように「生(なま)高坂」を見たこともなければ、そもそもその存在すら認識していませんでした。
私が高坂先生の本を初めて読んだのは、大学院に進学してからです。まず『国際政治』を読んだのですが、第一印象は不遜ながら「古くさいな」というものでした。要するに、一時代前のリアリストだと思ったんですね。というのも、当時、自らがミリタリーオタクだと深く自覚していたがゆえに、かえってそんな自分を相対化しなければと思って、「もう20世紀的な戦争なんて起こらないことは知っていますよ。これからはポスト冷戦的ユーフォリアの時代ですよね」という立場に過剰にかぶれていたんですね。
でも結局、それだけでは国際政治は把握しきれないだろうと気づいて、そもそも根がミリオタだというところも重なって、またリアリズム的な世界に戻っていきました。その時に高坂先生の『国際政治』を読み直して、「これは予言の書だ」と目を瞠りましたね。
冷戦終結は「一つの帝国が潰れただけ」
細谷 いま「ポスト冷戦的ユーフォリア」という言葉が出ましたが、本書の元となる連続講演が行われた1990年1月から6月にかけては、ちょうど前年11月にベルリンの壁が崩壊し、これで世界が平和になるだろうと人々が多幸感に包まれていた時期です。日本もまだバブル経済が崩壊する前で、まさに絶頂期でした。
それにもかかわらず、高坂先生の講演にはそんなユーフォリア的な雰囲気がまったくない。何しろ第一回のテーマが「戦争の世紀」で、第二回が「恐慌」ですからね。あたかも、その後の世界が直面する困難を見通していたかのようです。あらためて考えると、これは凄いことです。
田所 それで思い出しました。冷戦が終わった時、高坂先生は「これでしばらく戦争はナシやな。ただ『しばらく』やで。まあせいぜい20~30年やろ」と言っていました。当面はロシアも大人しくなるかもしれないけど、だからと言って人類が戦争をしなくなるほど賢くなったわけではない。人間が人間である限り、国家というものが存在している限り、パワーポリティクスはなくならない――これが先生の考え方でしたね。
また、「命がかかった大戦争を心配しなくて良くなった分、これからは“ちっぽけな正義”をめぐって人々が争うようになるぞ。歴史問題とか嫌煙運動とか反捕鯨とかやな」とも言っていました。当時は何を言っているかよく分からなかったですが、本当にその通りになりましたね。
小泉 高坂先生は意外に冷戦という時代状況に絡めとられていない人だったんだな、というのが『歴史としての二十世紀』を読んだ私の印象です。米ソが軍事的に角を突き合わせ、一歩間違えば核戦争で人類が滅亡するという瀬戸際にあった時代のはずなのに、高坂先生の筆にかかると、冷戦もそれまでの世界史の延長上にある普通の状態に過ぎず、特別な状況ではなかったという気にさせられます。
高坂先生には、安易に「歴史に名前をつけない」という姿勢を感じますね。長いスパンで見れば、人間の営みにはある程度の普遍性が見出せるだろうという文明観がある。そのような人間の普遍性をさまざまなトピックを通じて鮮やかに抽出しているところに、この本の面白さがあるように思います。
細谷 私もお二人の話を伺っていて思い出しましたが、1994年春に日本国際政治学会で高坂先生が「国際政治の力学」というテーマのセッションで、パワーの概念を中心に報告をしたことがあったようです。
私はその場にいなかったのですが、高坂先生は、第一次世界大戦では、ロシア帝国、ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国と帝国が4つも潰れた。冷戦では、ソ連という帝国が一つ潰れただけだから大したことはない、というような発言をしました。他方で、冷戦の終結は、ウェストファリア体制以降のパワーポリティックス構造が根底から転換したことを意味する。これからはヨーロッパ統合が世界のモデルとなり、世界統合こそが国際政治の主流になる、というような反論もあったという話を聞きました。後者のような見方をする代表的な国際政治学者が、東京大学法学部教授で、その年に日本国際政治学会の理事長となった鴨武彦教授でした。
当時の、大学院生になりたての私には、そのどちらが正しい分析なのかということについて、自ら判断する能力はありませんでした、でも、次々と戦争が勃発し、大国間競争が顕著な今になってみれば、高坂先生の見通しがより適切なものであったことは明らかだと思います。結局は、パワー・ポリティクスは冷戦後の世界でも続き、国家間の戦争も続いていった。ウェストファリア体制の終焉は、到来しなかった。
「右」とか「左」とかでは割り切れない
田所 私の知っている限りでは、高坂先生は日本の外交政策への関与は、ほどほどというかかなり選択的だったのですが、冷戦終結で世界が非常に楽観的になっている時代、具体的には、この講演の直後、1990年8月にイラクがクウェートに侵攻して湾岸戦争が始まった時期に、明らかに非常に強い危機感をもって発言し始めています。「このままでは日本が危ない」と、かなり強い焦燥感に駆られていました。
小泉 湾岸戦争で日本に軍事的な脅威が及ぶわけではないですよね。ということは、アメリカから要請された自衛隊による掃海艇や補給艦派遣といった後方支援を、日本が断ったことに対する危機感でしょうか。
田所 国際社会が日本に期待していることと、日本国内の議論が完全にずれていること、もっと言えば戦後日本がごまかしてきたことが露呈してしまった。とりわけ当時は日米貿易摩擦で日米関係も揺らいでいた時期だっただけに、高坂先生はその後の日米関係をどうなっていくのか相当悩んでいました。
もともと高坂先生は、軍事力の役割はゼロではないけど限定的であると考えていました。とりわけ戦後は軍事力の効用は曖昧なものになった。日本の場合はいくらシャカリキになったところで、軍事大国になれるはずもないのだし、9条を書き換えることにこだわるよりも、曖昧な憲法のままの方が、生き延びるために知恵を使うだろうという考え方でした。
小泉 当時は日本の国力の絶頂期だったのに、その見切り方がすごいですね(笑)。
田所 ところが、弱者としてパワーポリティクスの世界をどうやってサバイブしていくかを真剣に考えなければならない日本が、湾岸戦争では「憲法9条」の一声で、何も有効な行動ができなくなってしまった。これはまずいと思ったんでしょうね。この事件をさかいに、高坂先生は改憲派に変わった。そして、日本は旗幟を鮮明にして多国籍軍に可能な限り協力をすべきだと、メディアで盛んに発言しました。
小泉 それもあって、高坂先生のことを「タカ派」「右翼」みたいな誤解をしている人もいるわけですけど、今回の本でも、「軍事にできることは限定的で、軍事力は政治戦略の一つに過ぎない」という考え方が徹底されていて、タカ派でも右翼でもないですよね。
むしろ、そのような軍事力の捉え方、いわゆる高坂的リアリズムは、1976年に採用された基盤的防衛構想にもつながってくるので、逆に陸上自衛隊出身の西村繁樹さんのような軍事戦略屋からは高坂先生はボロクソに批判されました。
細谷 右とか左とかでは簡単に割り切れないのが、高坂先生の魅力です。本書を読むと、過ぎ去った「歴史としての二十世紀」が、実は依然としてわれわれの生きている世界の岩盤として地中に埋まっているという現実を感じます。その意味では、本書の議論の内容が色あせていないどころか、よりリアリティがあるものとして眼前に迫っていると感じます。
※この鼎談は、高坂正堯『歴史としての二十世紀』(新潮選書)刊行を機に行われたものです。
※関連記事
「ロシアに大国をやめろと強制することはできない」――なぜ高坂正堯は「ロシアびいき」とも思える発言をしたのか|田所昌幸×細谷雄一×小泉悠 特別鼎談
「50年以上前の本なのに、まったく古さを感じない」――なぜ高坂正堯の本は、令和の大学生にも読まれ続けるのか|田所昌幸×細谷雄一×小泉悠 特別鼎談
◎高坂正堯(こうさか・まさたか)
1934~1996年。京都市生まれ。京都大学法学部卒業。1963年、「中央公論」に掲載された「現実主義者の平和論」で鮮烈な論壇デビューを飾る。1971年、京都大学教授に就任。『古典外交の成熟と崩壊』で吉野作造賞受賞。佐藤栄作内閣以降は外交ブレーンとしても活躍。新潮選書から刊行した『世界史の中から考える』『現代史の中で考える』『文明が衰亡するとき』『世界地図の中で考える』がいずれもベストセラーとなる。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。