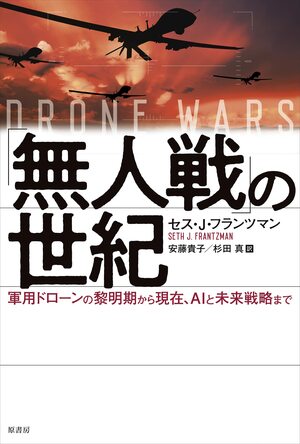現代戦におけるドローンの目覚ましい活躍
2020年9月にナゴルノ・カラバフの領有権をめぐりアゼルバイジャンとアルメニアが軍事衝突し、前者が軍事的勝利を収めた。その勝因の一つに、ドローン(無人機)の活躍があったと言われる。アゼルバイジャンはトルコ製武装ドローンのバイラクタルTB2やイスラエル製滞空型自爆ドローンのハーピーを効果的に使い、アルメニアのロシア製防空システムS300や戦車等を多数撃破した。また、現在進行形のウクライナ戦争でも、ウクライナ軍はバイラクタルTB2によってロシア軍の戦車や兵員輸送車両の破壊など顕著な戦果を挙げ、果敢に応戦している。米国もウクライナへの有効な軍事支援として滞空型自爆ドローンのスイッチブレード300・600を供与した。このように、ドローンが戦況に多大な効果や影響を及ぼすことから、ドローンが「ゲーム・チェンジャー」である、または、「ドローン戦争時代」が到来した、と言われている。
一口にドローンといっても、現在、13t以上の大型機から25g未満の超小型機まで多種多様である。それらはまず、民生用と軍用に大別され、軍用でも、目的により偵察・監視用と攻撃用に、規模により戦略用(大型で高高度・長距離・長時間航続)、戦域用、戦術用、近距離用(小型で低空・短距離・短時間航続)に細分される。ドローンは有人機と比較して、軽量・小型化により敵による探知可能性が低く、操縦士の生理的限界に関係なく長時間にわたり「退屈で(dull)危険で(dangerous)汚い(dirty)」任務(英語の頭文字から3Dと呼ばれる)を遂行できる利点がある。特に、兵士を戦場に送らずに、それゆえ、兵士の犠牲者を出さずに戦闘活動を可能にする兵器としての特性は高く評価される。
ドローンは、誕生から現代まで軍事戦略、兵器体系および現実の戦争の中でどのように位置付けられてきたのか。そして今後、未来戦を想定してどのような発展過程を歩むのか。誰もが知りたいところである。ここに紹介する本書は、まさにドローン技術の未来形を探るために纏められた。フランツマンは、大学で教鞭をとったこともあるジャーナリスト(エルサレム・ポスト紙の上級中東特派員・中東事情アナリスト)である。彼は、多数の戦争事例を引用し、ジャーナリスト特有の現場重視の視点から、軍・政府関係者、ドローン技術開発者および中東・安全保障研究者へのインタビューや紛争地域での現地取材に基づきながら、戦場でのドローンの実態を詳細に活写している。
ドローン発展史――ベトナム戦争からホルムズ海峡まで
米国人であるフランツマンの問題意識は、現在のドローン活用が偵察と標的空爆に限定されており、今が軍事史の分岐点であるにもかかわらず、米軍がその潜在能力を生かし切れていないもどかしさにある。そして、ドローンの古いプラットフォームを変更しようとしない保守性や、ドローンに対する先見の明のある軍関係者の不在を批判し、あるべきドローンの未来形という解を求めてその発展史を振り返る。ベトナム戦争での米国やレバノン戦争でのイスラエルは、ドローンをデコイ(おとり)として飛ばし、敵の地対空ミサイルのレーダーを起動させ、別のドローンでそのミサイルの位置を特定する手段として利用していた。1991年の湾岸戦争では、戦争が大量破壊時代から精密攻撃時代へ移行しつつある時代を背景に、ドローンによる情報収集・監視・偵察機能が重視された。その延長線上に、長時間の偵察活動を可能とする戦略用ドローン(グローバルホーク)が誕生する(第1~2章)。
しかし、偵察ドローンは、標的を発見しても別の戦闘機による攻撃までの時間差によりそれを取り逃がすので、探知と攻撃を同時に行う武装ドローン(プレデターやリーパー)のニーズが高まってくる。その契機となったのが、2001年の9.11同時多発テロであった(第3章)。オバマ政権は、対テロ戦争の一環として武装ドローンによる標的殺害を多用した。半面、米国は、ドローン攻撃に伴う文民被害が頻発したために批判され、武装ドローン輸出規制を厳格化せざるを得なかった。それが、他国(中国、トルコ、UAE、イラン等)によるドローンの国産化や輸出を促し、逆説的に、武装ドローンの保有国や使用国の拡散へと繋がっていった(第4章)。
加えて、非国家主体(イエメンのフーシ派やレバノンのヒズボラなど)も、独自開発や他国の軍事支援により武装ドローンを保有し使用する側に立った。2019年8月には、ついにフーシ派がサウジアラムコ石油施設にドローン攻撃を仕掛ける事件が発生。従来のハイテク防空システムは低空飛行のドローンには通用せず、国家は非国家主体からのドローン脅威を警戒せざるを得なくなった。その結果、国家は、ドローンの研究開発と同時に、対ドローン防空システムの研究開発にも取り組むことになる(第5章)。また、2011年に米国製ドローンのセンチネルが撃墜された事件以降、米国は、ドローンの模倣製造国イランとのドローン戦争に直面することになる(ホルムズ海峡付近での2019年6月の米国製グローバルホーク撃墜や同年7月のイラン製ドローン撃墜)。これらの事例から、米国は今までドローン保有国への対抗手段や対処方法を十分に検討してこなかった事実が判明した(第6章)。
攻撃手法も進化し、2019年9月のイランによるサウジ石油施設へのドローン攻撃事案では、18機によるスウォーム(群れ)攻撃が採用された。現在、スウォーム攻撃対策として、電波妨害装置によるドローン誘導遮断方式かレーザー砲による物理的破壊方式が検討されている。このスウォーム攻撃が戦争を変えるとの予測について、フランツマンは、刺激的ではあるが、実現していないとして否定的な見方を示している(第7章)。
ドローンの拡散と「貧者の空軍」
では、今後、ドローンはどのようなコンセプトの下で研究開発されるのか。ドローン超大国の米国は、中東地域でのドローン戦争の成功体験により、根本的見直しというよりも、追加的な高性能ドローンを追求する傾向にあるが、フランツマンはそれを油断の原因とみている。具体的な新構想として、有人戦闘機と連携するロイヤル・ウイングマン(忠実なる僚機)としての無人戦闘機を開発する「スカイボーグ」計画と、その候補機としてのステルス無人戦闘機XQ-58Aヴァルキリーの実証実験が行われている(第8章)。
未来のドローン戦争の在り方を知る手掛かりはどこにあるのか。フランツマンは、最初の本格的なドローン対ドローンの戦争として2020年のリビア内戦(トルコ支援の暫定政府軍vsロシア支援の反政府軍)に注目した。ここで証明されたのは、ドローンは対空兵器システムを備えた敵に対しても有効であり、組織的・資金的に弱体な内戦当事国であっても「インスタント空軍」または「貧者の空軍」が持てることである。米国が対テロ戦争に専念して他の軍事大国の動向に関心を払っていない隙に、中国はドローン開発を強力に推進し、2018年には無人戦闘機の最大輸出国となった。ロシアも、2008年の南オセチア戦争後にドローンの有用性に着目し、2014年以降のウクライナ東部地域での紛争でドローンの実戦使用国となった。以上のドローン発展史からフランツマンは、ドローンはゲーム・チェンジャーにも偽りの希望にもなれるし、使用国に様々な選択肢を与えるものの、必ずしもドローンだけで戦争に勝てるわけではない、との教訓を導く(第9章)。
ドローンの未来形に関する包括的問題として、有人機から無人機への移行は確かであるとしても、それが意味するのは有人空軍の終焉なのか、それとも、有人機と無人機の協働なのか。その問いに対して、フランツマンはパイロットを排除する前提として一層のインテリジェントなマシン、すなわち人工知能(AI)が必要であると指摘する。スウォーム攻撃もロイヤル・ウイングマン構想も、AI搭載ドローンでなければ実現できない。AIによる兵器の自律化は時代の要請であるが、その問いの答えは、人間の判断をどこまでAIに委ねるかによる。最後にフランツマンは、ドローン使用の可能性として、①有人機との組合せ、②ドローン軍の組織化、③多様な任務に合わせた多層的ドローンの形成、そして、④使い捨て可能な武器としての大規模スウォームの使用を挙げている(第10章、エピローグ)。
「ぬえ」的存在としてのドローン
軍用ドローンは、未来戦においても多用されるだろう。また、フランツマンも指摘するように、スウォーム化、ステルス化、AIによる自律化、そして、有人機と無人機の連携化の研究開発も、間違いなく促進されるだろう。このように、軍事大国は、少量であっても高速・多機能・高性能(その結果、高価格)というハイエンド(高品質)なドローンを求めている。他方で、弱小国や非国家主体は、財政的・技術的限界から、「インスタント空軍」の建設を目指して、低価格で使いやすく使い捨て可能な、ローエンドなドローンを大量に調達しようと試みる。
この「質か量か」の問題は、有人戦闘機に取って代わる使い方か、それとも、小型爆弾や巡航ミサイルに近い使い方かにも関連する。使用主体、使用目的、使用方法、使用場面による多様なニーズを満たすために、多種多様な機種が開発されてきたドローンは、他の通常兵器と比較して、振れ幅が大きく柔軟な「ぬえ」的存在なのかもしれない。フランツマンも暗示しているように、ドローンは、‟戦術的な”ゲーム・チェンジャーであるかもしれないが、‟戦略的な”ゲーム・チェンジャーではない。とはいえ、現時点ではまだまだ気付かないドローンの活用形態がありそうだ。ドローン戦争の未来がどうなるのか、本書をもう一度読み直して、見過ごしているヒントを探してみたい。
記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。