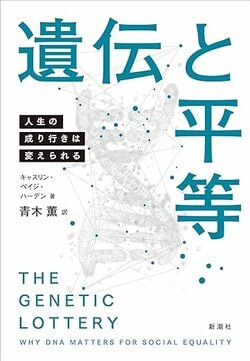テキサス大学心理学教授のキャスリン・ペイジ・ハーデン氏は、これまで科学者が「優生学の擁護」の誹りを免れようとタブー視してきた「遺伝と平等」の問題に真正面から切り込んだ。同氏の新著『遺伝と平等―人生の成り行きは変えられる―』(新潮社刊)は、遺伝的差異を根拠に社会的不平等を正当化する優生学とも、遺伝学的差異に目をつぶることで結果として社会的不平等の是正を妨げてしまうゲノムブラインドネスとも異なる、新しいアプローチを提唱する。以下は本書の一部抜粋と著者へのインタビューだ。
人生の成り行きを決める社会的偶然と遺伝的偶然
もちろん人生はアンフェアだ――人生の長さである寿命まで含めてそうだ。齧歯類やウサギの仲間から霊長類までさまざまな種において、社会的ヒエラルキーの序列が高い者ほど、より長く、より健康な一生を送る。アメリカでは、最富裕層の男性は、最貧困層の男性に比べて、平均で十五年ほど寿命が長く、最貧困層の男性の四十歳における平均余命は、スーダンやパキスタンの男性とほぼ同じだ。(中略)こうした所得格差は、教育格差と複雑に絡みあっている。コロナウイルスのパンデミックが起こる前でさえ、大卒でないアメリカ白人の寿命は、実際に短くなりつつあった。
人々は、教育、富、健康、幸福、そして人生そのものについても、大きくレベルの異なる経験をする。これらの不平等はフェアなのだろうか? (中略)「機会均等」のレンズを通して見れば、不平等の大きさや程度がどうであれ、それだけでアンフェアな社会ということにはならない。むしろ重要なのは、その不平等が、親の属する社会階級やその他、子ども自身にはどうしようもない誕生時の状況に結びついているかどうかだ。金持ちの両親のもとに生まれるか、貧しい両親のもとに生まれるか、教育のある両親かそうではないか、両親は婚姻関係にあるかないか、病院から家に帰ったとき、周囲の環境は清潔で整然としているか、不潔で散らかっているか――こうしたことは、人の誕生にまつわる偶然の要素だ。
しかし、成長後の成り行きの不平等に関連する誕生時の偶然が、もうひとつある――あなたが生まれた家庭や地域環境という社会的偶然ではなく、あなたが持って生まれた遺伝子の偶然だ。(中略)裕福な家庭に生まれるか、貧しい家庭に生まれるかという偶然と同じく、遺伝的バリアントの特定の組み合わせを持って生まれるかどうかもまた、誕生時に引かされるくじの結果なのだ。
優生学とアンチ優生学
教育格差や社会格差の理解に遺伝的性質が関係していると主張することは、それがどんな関係であるかによらず、そう主張する者を破壊に導く行為だ。その考えは、危険思想だと見なされる。その考えは――率直に言おう――優生学的だと見なされるのだ。
私は本書の中で、人は遺伝的に異なると述べるのは優生学的なことではないと論じるつもりだ。遺伝的差異のために、特定のスキルを身につけたり、役割を果たしたりすることが容易にできる人たちがいると述べるのは優生学的なことではない。遺伝的な影響を受けた資質や能力を、歴史的・文化的にたまたま重要になった特定の組み合わせで持つことになった人たちが、教育システムと労働市場と金融市場において、金銭的にもその他の面でも有利になる様子を、社会科学者が明らかにするのは優生学的なことではない。優生学的なのは、人間ひとりひとりの違いと、それらの違いを生み出す遺伝的バリアントを受け継いだことを、人には生まれながらの優劣があるという考えや、ヒエラルキー内のランクや自然な階層といった考えと結びつけることなのだ。優生学的なのは、道徳的には何の意味もない遺伝的バリアントの分布という基礎の上に、資源、自由、福祉の不平等を作り出し、その不平等を固定するための政策を立てたり、それを実施したりすることなのである。
そうだとすれば、アンチ優生学のプロジェクトは、(1)遺伝的な運が、われわれの身体や脳が作られる際に果たす役割を理解すること、(2)われわれの現在の教育システムと労働市場と金融市場が、ある種の身体と脳を持つ人たちに報いる(それとは異なる種類の身体と脳を持つ人々には報いない)仕組みを記述し、(3)これらの社会システムを、遺伝くじの結果によらず、すべての人に報いるものに変えるための方法を思い描くことだ。
アメリカの優生学の負の遺産を思えば、遺伝学研究が理解され、新しいやり方で利用されることが可能だと考えるのは、あまりにも楽観的、いやむしろおめでたいとさえ感じられるかもしれない。しかし、このリスク――便益の考察からは、人々の遺伝的差異が社会的不平等を形成する仕組みを理解しようとする試みが、学者と一般の人たちの両方から広くタブー視されている現状を放置することのリスクが抜け落ちている。この事態はもはや擁護できない。人々のあいだの遺伝的差異に目をつぶるという、広く見られる傾向は、心理学と教育学をはじめ、さまざまな社会科学分野の発展を妨げてきた。その結果として、人間開発を理解することと、人々の生活を改善するための介入について、さもなければできていたはずの多くのことがいまだにできていない。もしも社会科学者たちが集団として、人々の生活を改善するために立ち上がろうというなら、人々はまったく同じに生まれるわけではないという、人間本性の基本事実に目をつぶっていてよいはずがない。
*
このように著者は、遺伝的差異を根拠に社会的不平等を正当化する優生学とも、遺伝学的差異に目をつぶることで結果として社会的不平等の是正を妨げてしまうゲノムブラインドネスとも異なる新しいアプローチとして、アンチ優生学を提唱する。
ゲノムの違いに目をつぶってはいけない
著者が本書を記したきっかけや本書に込めた思いはどのようなものか。国際ジャーナリストの大野和基氏が聞いた。
――私は、社会的平等を考えるにあたって遺伝子は重要であるというあなたの主張に賛同しますが、たとえ私が遺伝学を専門とする科学者であっても、平等という角度からそれを探求する勇気はありません。なぜなら最も物議を醸す研究分野だからです。
これまで科学者たちは差別主義者であると非難されるのを恐れて、人種、知能、教育の遺伝的側面をタブー視してきました。であるにもかかわらず、あなたが教育や知能や社会的平等との関連で遺伝を深く研究したいと思った契機は何でしょうか?
科学分野での私の最初の仕事は、動物を使って遺伝学の研究を行うラボのリサーチ・アシスタントでした。薬物中毒の研究において、中毒のリスクが人によって異なることは比較的穏当なテーマだったので、マウスの遺伝的バリアント(複数ある遺伝子のバージョン)がアヘン中毒にどのような違いを生むかについて、ウイルス・ベクター(遺伝子治療などで遺伝子を体内の細胞に安全に運ぶものとして使われる組み換えウイルス)を使ってマウスの遺伝子を操作し、研究していました。
その後、博士課程に進み、臨床心理学で博士号を取ったのですが、青春期の発達の相違が中毒リスクを含む後の人生に大きな相違を生じさせることから、どのような人が大学に行くのか、刑務所に入るのか、10代で母親になるのか、高校をドロップアウトするのか、ということに関心が広がりました。これらが小さいときの経験に関係していることは明らかですが、遺伝子の差異にも関係しているという考えが、私の思考の基礎になっています。このような経緯で、最終的に私の研究は遺伝子が個々の違いをいかに生じさせるかという、より広いものになりました。
この本を危険であると言う人は、私が優生学的なナラティブを醸成していると勘違いしているのだと思いますが、遺伝学を優生学に結び付けて危険なテーマだからと避けることは、学校で性教育をしないことと同じで、重要なことに目をつぶっています。
英語には“The apple doesn’t fall far from the tree.”(リンゴは木からさほど遠いところには落ちない。つまり子は親に似るという意味)という表現があるように、我々は親と似ている部分や似ていない部分を観察しながら生きています。そのことを説明するのにfolk theory(通俗理論)を使うことも多いですが、正確な情報は科学者からしか得られません。このことがずっと気になっていました。科学者が遺伝について正確な情報を提供しなければ、我々はゲノムの違いが社会的不平に影響を与えていたとしても、遺伝は自分でどうすることもできないのでゲノムの違いは重要ではない、というふりをし続けることができてしまうからです。私はゲノムの違いに目をつぶってはいけないという意味で、ゲノムブラインドネスの問題について本書で書きました。科学者には、遺伝についてpublic conversation(公の場での会話・対話)に貢献する重要な役割があると私は信じています。
確かにいろいろな人から、このようなセンシティブなテーマについて本を執筆したことについて、「勇気があるね」と言われます。最初は学術論文を書く予定でした。民間のジョン・テンプルトン財団から助成金をもらい、科学と宗教と哲学の交差点に位置するビッグ・クエスチョンをテーマに哲学者と科学者とでチームを組んで論文を書き始めたところ、プリンストン大学出版局の編集者から本として刊行することを打診されたのです。同僚が大学の授業のテキストとして使ってくれたらいいなという気持ちだったので、まさかジャーナリストが東京からテキサスまでやって来て、インタビューをされるとは夢にも思いませんでした。ですから、私自身はこの本を書く勇気ではなく、特権を与えられたと考えています。
教育の道徳化という優生学的ナラティブ

――あなたは能力主義(メリトクラシー)とDNAの関係をどのように見ますか?
私はどんな仕事でも、その仕事に関する能力が最も高い人が行うべきだと思っています。その考え自体は物議を醸すようなことではないと思います。例えば病院が外科医を雇うときに、ベストな外科医を雇いたいと思うのは当然でしょう。
能力主義が物議を醸し始めるのは、社会における権力やお金や名声の違いに付属する役割や責任のことを考えるとき、つまり能力主義がとんでもない格差の正当化として使われるときです。そういうときは、能力主義を疑問視しなければなりません。アメリカは高所得国の中でも、最も裕福な人と最も貧しい人の格差が激しい国ですが、この格差について「それは悪くない」「是正するべき問題ではない」「政府が介入するべきことではない」と主張する人の多さでもアメリカは突出しています。アメリカで格差に対して寛容な人に、どうして裕福な人は裕福かと聞くと、特定の能力を持って生まれたからと言う人よりも、一生懸命頑張ったから、と言う人が圧倒的に多いでしょう。それはプロテスタントの労働倫理が刷り込まれているからですが、私は特定のスキルを他の人よりも容易に発達させることができる脳や肉体を持っているという遺伝的差異にも、注意を促すべきだと思います。
もう1つ、我々が闘わなければならない優生学的なナラティブは、moralization of education(教育の道徳化)です。つまり、特定のスキルなどの生物的な性質を美徳、有徳、道徳的功績と結びつけて、それを人間の価値と捉えることです。こうしたナラティブと闘う1つの方法は、我々には生まれながらにして親から受け継いだ生物学的恣意性があることを強調することです。例えば、あなたはたまたま容易に記憶することができる能力がある人であるとか、たまたま机にじっと座っていられるというような、正規の教育で称賛されるスキルを持っている人であるとか、そういった差異があることを強調することです。
経済学者のロバート・フランクは著書の“Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy”(邦訳『成功する人は偶然を味方にする: 運と成功の経済学 』)の最後に、内部の幸運ではなく外部の幸運について次のようなことを書いています。
〈自身の人生における将来に目を向けるときは、自分がコントロールできることに集中しなければならない。そうやって主体性を養うからだ。しかし、自分の人生を振り返るときは、自分がコントロールできるもの以外で自分に与えられたものに重点を置いて振り返らなければならない。それが感謝や思いやりの気持ちを育む方法である〉
この哲学は、私が能力主義について考えるときに、とても影響を受けました。
「平等」とは何か
――ゲノムを構成する個々の要素と測定可能な人々の特徴との相関を調べる「GWAS」(ゲノムワイド関連解析)に見られるように、テクノロジーは飛躍的な発展を遂げていますが、最終的にどの遺伝的バリアントがどの形質に関連しているかが分かれば、社会を「平等化」するために人間の遺伝子を編集してもいいという考え方もあります。しかし、そうしたテクノロジーが悪用されれば、かえって不平等が広がる可能性もある。社会というコンテキストの中で、「平等」をどのように定義しますか?
それは非常に素晴らしい質問です!
その問いが意味するのは、CRISPR-Cas9(DNAを切断してゲノムの任意の場所を改変できる技術)やポリジェニック胚スクリーニング(PES:遺伝子変異と特定の疾患のリスクの関連性を測定すること)といった新しいテクノロジーが水面下でくすぶっていた葛藤や価値観を表面化させたときに、なぜ我々を不快にさせるかを考えざるを得ないということです。「平等」が何を意味するのか、「平等」の定義の中にあるテンションは何かということをより深く考えさせられます。
平等との関係で遺伝学という言葉を耳にするとき、人は「sameness」(同じであること)の角度から平等であると考えがちです。遺伝子に介入するテクノロジーがあるのなら、平等を達成する唯一の方法は、人を生物学的により同じにすることであると考えたくなりますね。
ここで我々は、「disability justice」(障害者の正義:障害と人種、階級、性別といった他の抑圧構造やアイデンティティとの関連に注意喚起を行う社会正義運動)から多くの教訓を得ることができます。繰り返し指摘されてきたように、障害者にとっての正義とは、肉体を他の人と同じようにすることではなく、社会に参加して社会を楽しみ、社会の中で機能する能力を他の人と同じようにすることなのです。私はこの教訓を深く心に刻み、平等について考えてきました。
我々の関心は、いかにして生物学的均一性を持つかということにあるのではないのです。考えてみると、生物学的均一性を求める世界には誰も住みたいとは思いません。生物学的に多様性のある世界を我々は求めています。我々はクローンだらけの世界に住みたいとは思わないのです。ユニークな生物的多様性のある世界で開花する平等な機会を、我々は求めているのです。私は「平等」を、ゲノムの潜在的な平等ではなく、社会への参加の平等及び抑圧からの自由・解放と考えます。
余談ですが、私は単一遺伝子病の場合にCRISPR-Cas9などの遺伝子編集を行うことには賛成です。私の友人の娘は単一遺伝子病を持って生まれてきましたが、あまりにも痛みが強く、かなり激しい医学的介入をしなければなりませんでした。受精卵の段階での遺伝子検査で遺伝子変異があると分かった場合、生まれてからの苦痛を取り除くために遺伝子編集をするのであれば、それが安全なものであると分かっている限りは遺伝子編集に賛成です。生まれてくる子どもが苦痛を経験しなくてもいいようにできるのであれば、遺伝子編集を行うべきだと思います。
しかし、それは、「違い」とは何か。「障害」とは何か、「病気」とは何か、という哲学的に際どいイシューを提起します。しかもその手のカテゴリーは絶えずシフトしており、社会的に物議を醸します。例えば、多くの人は自閉症を病気だと考えていますが、中にはそれを「違い」と考えている人もいます。
遺伝学は万能薬ではない
――あなたは遺伝子の理解に基づいて、社会的平等のために介入する道義的責任を感じますか?
私は、我々にはどんな子どもも開花できる状況を作り出す社会的義務があると思います。私には3人の子どもがいますが、その子たちには自分たちが高く評価され、歓迎されるニッチ(隙間)を見つけて欲しいと思っていますし、苦手な分野では少し押されても、好きな分野や得意な分野ではそれを追究できるように、多くの機会を与えて欲しいと思っています。それが、私が思う良い社会のモデルです。そして、こうした目標に対して最も適切な介入や構造が何であるかを見極めようとするときに実験的、経験的に応用できるツールを与えることができるのが、遺伝学だと思います。
とはいえ、政策に介入することは本当に難しいです。最終的にどのような結果をもたらしたいか、それをバックアップする社会科学はどうあるべきかによって答えは変わるからです。それは非常に複雑です。公平な社会をもたらすのに実際にどのような手段が有効なのか。それに関する実社会でのリアルな人間の研究から我々は何を知っているのか。遺伝学はそのパズルの1つのピースです。
あなたが先程尋ねた、「私が達成しようとしている平等とは何か」という問いですが、この問いに際して遺伝的差異を考えた場合と考えなかった場合を比べると、遺伝的差異を考えた場合の方がはるかに平等について深く考えさせられました。私が考える平等は、必ずしも人を生物学的あるいは精神的に同じにすることではなく、社会への参加や抑圧からの解放・自由という点で平等という意味です。さらに、生活環境が人間の尊厳を守っていること、そして我々が親から受け継いだ生物学的恣意性を認識することです。
私は誰かが何かを提案したとき、その人がもたらしたいと思っている世界はどんな世界なのか、どのような善をもたらしたいのか、その善は平等な社会への参加を意味するのか、抑圧からの解放・自由を意味するのか、ということを常に考えています。9年生(日本の中学3年生に当たる)で代数に落第する人が少なくなるように、貧しい子どもと裕福な子どものギャップが縮まるように、微分積分をきちんと学習して高校を卒業する人が増加するようにしたいと思っています。その目標をいかに達成するかということについては何十年も前から議論が続いています。たとえば、アメリカのReading Warsです。これは子どもにいかに読書を教えるか、その方法論に関する論争です。
我々の政策目標には、よりすぐれたリサーチができるようになるいかなるツールも役立ちます。私はそこにポリジェニックスコア解析や遺伝学の役割を見るのです。ただし、それは本当に難しいコンテキストの中で子どもの発育の複雑性を理解しようとする問題に応用できる1つのツールに過ぎません。決してsilver bullet(問題を解決するための確実な方法)やpanacea(万能薬、あらゆる問題の解決策)ではありません。
――本書を執筆した狙いの1つは、Nature vs. Nurture(生まれつきか、育ち方か)論争にきっぱりと決着をつけることだったのでしょうか。
その論争には終わりはありません。私は、この論争が起きている要因の多くは、このテーマに関する情報や教育の欠如にあると思っていました。時間をかけてうまく十分に説明すれば、これに関する多くのイシューを解決することができるだろうと考えていました。しかし、私はその点で間違っていました。同じ情報を持っている人同士の間でも論争が起きるのです。
これはいかなるテクノロジーに関するテーマよりもはるかに古くからある論争で、人間であるとはどのようなことかについての、我々の問いの中核にあります。この論争を活発化させ、永続化させているのは、人間の経験の中核にある葛藤(テンション)、つまり自意識のある動物、文化的動物、倫理的動物であるとはどういうことか、というテンションだと思います。そういうテンションは永久に消えることはないでしょう。どんなに新しいテクノロジーが出現しても、それと絡み合いながら永久に続いていくのだと思います。
ただ、私は本書で自分の視座をできるだけ明確に伝えようとしました。教授としてテーマを選ぶとき、壮大なテーマを選ぶのは必然であると感じています。
◎Kathryn Paige Harden(キャスリン・ペイジ・ハーデン)
テキサス大学心理学教授、同大学のDevelopmental Behavior Genetics Lab(発達的行動遺伝学研究室)を運営。テキサス双子プロジェクトを共同主宰。初の著作となった『遺伝と平等―人生の成り行きは変えられる―』は、「The New Yorker」「The Guardian」など各媒体で絶賛され、2021年の「The Economist」ベストブックに選ばれるなど高い評価を得た。
◎大野和基(おおの・かずもと)
1955年兵庫県西宮市生まれ。大阪府立北野高校卒。東京外語大英米学科卒業後、1979年渡米。コーネル大学で化学、ニューヨーク医科大学で基礎医学を学んだ後、ジャーナリストの道に進む。ポール・クルーグマン、ジャック・アタリ、ジョセフ・ナイ、リンダ・グラットン、ジャレド・ダイアモンド、ユヴァル・ノア・ハラリ、マルクス・ガブリエルら世界的な識者への取材を精力的に行っている他、生殖補助医療に関する取材・著書も豊富。主な著書に『私の半分はどこから来たのか AID[非配偶者間人工授精]で生まれた子の苦悩 』(朝日新聞出版/2022年)、『代理出産 生殖ビジネスと命の尊厳』(集英社/2009年)がある。