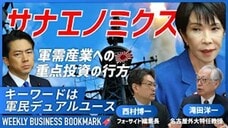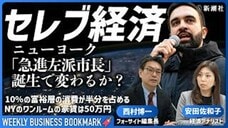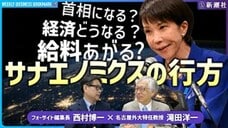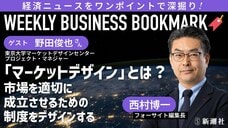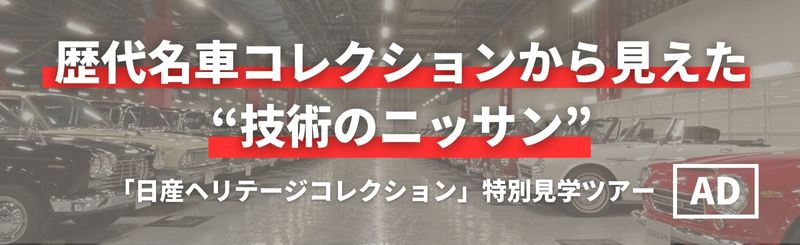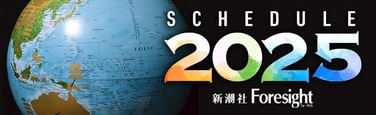昨年12月に行なわれた衆議院選挙では自民党・公明党があわせて325議席を獲得して圧勝し、3年3カ月ぶりの政権交代が実現した。その一方で民主党は170議席以上を減らして60議席を下回り、躍進した日本維新の会(維新)とほぼ同じ議席数となった。政党の議席数の動きで見る限り、日本政治には大きな変動が生じたといってもよい。
しかし、今回の選挙結果や政権交代に対して、有権者の評価はあまり芳しくないようだ。その大きな理由は、比例代表での得票率や獲得議席比率(議席占有率)から見れば30%程度しかない自民党が、小選挙区をあわせれば単独で294議席、議席占有率61.3%、公明党の31議席とあわせれば衆院の3分の2を超える勢力となったことへの違和感であろう。また、選挙前には10以上の政党が乱立した選挙になったこと、民主党も維新も第2党として自民党に対抗するにはあまりに小さな勢力になったことも、政党間の実効的な競争関係を弱めるという見方もあるだろう。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン