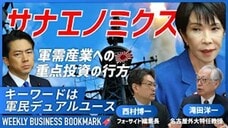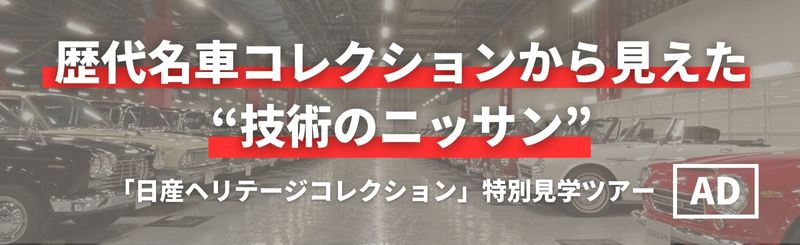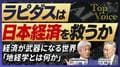「油を買うには土産がいるだろうな」――日本における海水淡水化の技術研究は、こんな一言から本格化した。命を受けたのは当時、工業技術院の研究員だった後藤藤太郎(現・造水促進センターエグゼクティブアドバイザー)。一九六九年、第一次オイルショック(七三年)が起きる前のことである。後藤は海水の分析と脱塩技術の研究に着手する。後に後藤は、サウジアラビアでの蒸発法や濾過膜を利用した海水淡水化の技術指導にもあたった。 中東の人々にとって水はどのようなものなのか。後藤は、「砂漠のオアシスとは井戸であり、その権利は実に厳格。他人の井戸の水を勝手に飲むと殺されてもおかしくないとさえ言われる。海水淡水化は、『アラーからの贈り物』と喜ばれた」と語る。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン