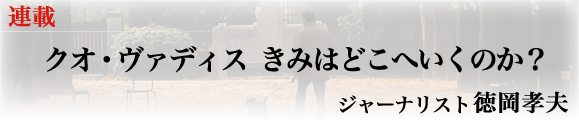アジアの英字紙を読んでいて、ふと1個の英単語に目が止まった。尖閣諸島の領有権を争う日本と中国の対立、また中国各地で起きた反日暴動。それは詳しく書いてある。東南アジアにも南沙諸島の帰属問題で中国と争っている国があるから、尖閣はヨソ事ではない。
記事に、中国が日本の尖閣諸島国有化をintrusionと呼んでいる、と書いてある。ふーんintrusionか。
中国外務省の報道官がそう言ったか、北京の英字紙がそう報じたのだろうと思いながら先を読もうとして、私はintrusionの意味を「不法侵入」としてしか知らないのに気付いた。
そこで大きい英和辞典を引いてみると、こうあった。
intrusion ①(意見などの)押付け、侵入②(場所、私事などへの)侵入、邪魔③〔法律〕(無権利者の土地、寺禄に対する)侵入、不法占有、横領
なるほど。私は①の「押付け」を知らなかったが、③を見て中国がこの単語を使った理由が分った。
彼らに言わせれば、日本が尖閣諸島に上陸した行為は、単なる上陸ではない。それは、そもそも無権利の日本による侵入である。そう言いたいので、法律的な意味のあるintrusionを使ったのだろう。
日本の新聞によると、中国では日本人が中国の領土を「盗んだ」と言っていると書いた。しかしintrusionという言葉を使えば、日本は尖閣に対して無権利者であり、日本の行為は最初から犯罪だった、ということになる。欧米の新聞は、この単語ひとつで日本イコール領土窃盗犯というイメージを持ってしまう。
ところで尖閣諸島に関する話は、諸メディアに書かれているので、ここで終わる。私はintrusionに「私事に対する無権利者の侵入」という語義があるのに注目した。
実は、尖閣問題が起きたのと同じ9月中旬の新聞に、やや別種のintrusionが(日本では)小さく載ったからである。
それは島でも寺禄でもない。英国ウィリアム王子(30)の新婚後まもない妻キャサリン妃(30)の胸が、無権利者であるフランス誌「クローザー」に掲載されたという話である。
キャサリン妃(向こうではケイトと略している)は、さる縁ある富豪の持つシャトーのバルコニーで日光浴中にトップレスになり、ビキニのボトムだけの姿で夫にお尻にサン・タン・オイルを塗ってもらっていた。その場面の画像が出た(相当な枚数を一挙掲載したらしい)。ただし長距離レンズによる撮影だから、写真の画質は悪いという。
誰もが思ったのは、ウィリアム王子の母ダイアナ妃の悲劇の一生だった。
パパラッチ(主にスキャンダルを狙う冒険的カメラマン)が執拗にダイアナ妃の私生活を盗み撮りし続け、ロンドンの大衆紙がそれを買って載せ、最後はダイアナさんの死に至って終わった「近い昔」の物語だった。マスコミは、またあれをやるのか?
英国の大衆紙は、ダイアナ妃の例に懲りたのか、今回は「クローザー」が売りに出した写真を買わなかった。
ところが全裸同然のケイトの写真を買ったメディアが2つある。アイルランドの「アイリッシュ・デイリー・スター」紙とイタリアの「Chi」誌である。後者は「クローザー」と同じ前イタリア首相で億万長者ベルルスコーニの所有するマスコミ帝国の傘下にある。
メージャー元英首相は、BBC放送に出て、ケイトの隠し撮り写真を載せたメディアを「ピーピング・トムだ」と批判した。女性の裸を窃視して喜ぶ下劣なヤツというニュアンスの言葉である。日本人の尖閣上陸を猛烈批判した中国と同様、無権利者のintrusionは許せない、と言ったのである。
ウィリアム王子とケイトは、かなり開放的な気分だったらしい。「クローザー」によると、ケイトはマルセイユ空港で飛行機から車に乗り換えるとき、禁煙地区を出るや否や煙草に火をつけたという。
「Chi」の編集長は、なぜ英王室女性のトップレスを載せたのかと問われて答えている。
「あの写真は一つのスクープだった。スクープして、それを載せないジャーナリストはいない。あの写真は、英王室の知られざる一面を見事に見せた」
もっともである。だが同じような記事または写真を獲得したジャーナリストは、みな同じ弁解をするだろう。
「クローザー」が売店に出て数日後、フランス当局は同誌の出版・販売を差し止めた。また同誌編集部が問題の写真を入手するに至った経緯について刑事捜査を始めた。
一方で仏民事法廷は、写真原板を含むすべての写真コピーの提出を命じ、他社への転売を禁じた。
ダイアナ事件の再演を恐れる英国の強い世論に配慮したらしい措置だが、いくら差し止めても雑誌はすでに売れている。撮影した者の住所氏名を報告せよとも命令されているが、雑誌側はきっと「分らない」と答えるだろう。
だいいちダイアナ妃のプライバシーを徹底的にintrusionしたのは、誰よりも英国のタブロイド紙であった。英国セレブの側も、トップレスを写されたくなければ、戸外でトップを取らなければよい。
いずれにせよ日中間の尖閣をめぐる争いも、英王室女性の胸を争うintrusion騒動のように、敏感であり続けるだろう。女性に胸がある限り、日中の間に尖閣諸島がある限り、当事者全員が納得する解決は無理である。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。