
国際政治学者・北岡伸一氏の新著『覇権なき時代の世界地図』(新潮選書)が刊行された。
北岡氏は著名な研究者でありながら国連次席大使(2004〜06年)、JICA(国際協力機構)理事長(2015〜22年)を歴任し、国連での活動や途上国への開発協力を通じて激動する国際社会の現場を見つめてきた。
JICA理事長時代の経験を中心にした『世界地図を読み直す――協力と均衡の地政学』(新潮選書)に続き、JICA特別顧問としての取り組みを含めた直近の活動を通して見えてくる世界の実像とは。そして今後の日本にできること、すべきことは何か。盟友でありJICA現理事長でもある田中明彦氏と語った。
***
緒方貞子さんから引き継いだJICA理事長
田中 私はいまJICA(国際協力機構)の理事長で、北岡さんは特別顧問ですが前理事長であり、その前は私が理事長でした。私は2回目ということになります。なぜ私たちのような研究者がJICAの理事長を歴任してきたかというと、2003年に現在の独立行政法人になって最初の理事長を務めたのが国際政治学者の緒方貞子さんだったということが大きいと思います。
緒方さんから引き継いだ当時の任命権者の意図はよくわからないのですが、国際協力は非常に幅が広くて、農業のような専門的な技術協力もあれば円借款という金融業務もあり、開発経済学という学問的な見地も必要になる。JICAという組織の特性から、国際社会全体にある程度の目配りができる人間が指導するのが望ましいということかもしれません。
北岡 さらに前史を話すと、私と田中さんは1992年以来の付き合いなんです。読売新聞社が憲法問題調査会を設置した際に、我々は委員として第1次提言の原案を書いた。その時の結論は、憲法をすぐに変える必要はなく、解釈をきちんとやって行けばよろしいという立場で、これは政治学者としては中道なんですね。田中さんは理論で私は歴史と、バックグラウンドは違いながら、なぜか物事の判断が似ているところが多くて、他の場所でも私が座長で田中さんが座長代理というようにコンビを組んできました。
緒方さんがJICAの理事長を辞められた後、いちおう私にも打診がありましたが、他の都合で受けられず、田中さんに決まって良かったと思っていた。田中さんの後にまた私に声がかかって、私が日本の外交を教える中でODA(政府開発援助)も対象の一つだったので、ある程度の知識はありましたが、現場でどのように行なわれているかも知りたかったし、もっと推進すべきという考えだったので、やりたいと思った。それが引き受けた理由です。
2022年に6年半の任期を終える頃、JICAを所管する外務省が、次の理事長は公募したいと言ってきた。公募だと年齢制限があるため、私にはほぼ可能性がない。外務省の判断というのは、しばしば短期的な国際情勢に振り回されます。JICAは独立行政法人ですが、もう少し長いスパンで仕事をする必要があるので、外務省の言う通りではなく、良好な関係を保ちつつも独自の判断ができる人が望ましい。それで田中さんにもう一度やっていただくのがいいと思ってお願いに行って、手を挙げていただいたんです。
国際社会の激しい変動を写し取った『覇権なき時代の世界地図』
田中 2022年に特別顧問に就かれて以降も、北岡さんにはJICAの事業を精力的に指導していただいています。特に日本の近代化の経験や戦後復興、ODA政策について途上国に学んでもらうJICA開発大学院連携やJICAチェア(JICA日本研究講座設立支援事業)といった事業では、重要な国へ赴いて、日本についての講義などを行なっていただいている。
北岡さんは理事長時代の経験を中心に『世界地図を読み直す――協力と均衡の地政学』(2019年)を書かれ、今回はその続篇と言うべき『覇権なき時代の世界地図』を刊行されました。概して言うと、日本の国際政治についての視野が日米関係や日中関係にばかり集中していて、それ以外の国々については専門家でさえ充分な理解が進んでいないという傾向があります。この2冊は、一般の読者が今の世界情勢のどういう点を見るべきかという時に、訪れた途上国の現状だけでなく歴史的な背景も含めて視野を広げてくれるという意味で大変重要な貢献をされている本だと思います。

北岡 今回の『覇権なき時代の世界地図』の特徴的な背景は、直近の国際社会の変動がとりわけ激しいということです。20年に新型コロナによるパンデミックが始まって、豊かで技術力があるはずの先進国が打撃を受け、途上国に対する充分な支援ができなかった。21年には我々が積極的に支援してきたミャンマーにクーデターが起き、アフガニスタンでは9・11以降にアメリカが関与し国際社会が支援してきた政権が潰れた。22年には、それまでにも前兆のあったウクライナでついに戦争が起こってしまった。これはつまり、グローバリゼーションやアメリカの一極支配に対する反動が起こってG7の力が充分ではなくなってきたということで、これら縦軸で起きた変動の筋を通すのに苦労しました。
「援助・支援」ではなく「協力」
田中 21世紀に入ってグローバリゼーションが進んで、国際社会の中でも格差や分断の問題が出てきた。ロシアの例でも、2008年にジョージアへの侵攻があり14年にはクリミア併合がありと、国際社会は具合の悪いことが起こりつつあると思いながらも、充分な対応ができないままウクライナ侵攻に至った。
その中で日本の立ち位置を考えると、世界第2の経済大国ではなくなって国際的な影響力も低下していると見られることが多いと思いますが、世界情勢が大変難しいことを前提とした上であえて言えば、私は日本の影響力はかつてより大きくなっていると思うんです。
日米摩擦の激しい頃やバブルの頃には日本の国際的な影響力が大きかったように思われているけれど、実際には2010年代以降、自民党の長期政権で安倍晋三首相が世界を飛び回り、かなり長い間にJICAのような組織が活動を積み重ねてきたことが日本の影響力の源泉になっているのではないか。
日本が行なってきた開発協力は、「援助(aid)」「支援(assistance)」よりも「協力(cooperation)」という姿勢を重視しています。これは一方的な施しではなく、パートナーの国と一緒になって解決していきましょうということですね。ODAは70年の歴史がありますからうまくいかなかったこともあるけれど、日本は受け入れ国にとって役に立つことを押し付けではなく、パートナーの国のオーナーシップ、つまり自主性を尊重しながら行なってきたというところが、世界の多くの国の信頼感に繋がっている。私はこの頃、グローバルサウスから最も信頼されている国は日本なんじゃないかと思っているくらいです。
北岡 ODAは欧米が先に始めましたが、根っ子にはチャリティ、恵みや施しという思想があると思うんですよ。JICAの姿勢として「人間の安全保障」という考え方がありますが、すべての人間は尊厳をもって生きる権利がある、それを尊重しようということで、施しではないんです。
海外に専門家を派遣する際に相手国から望まれる条件として、専門能力が高いこと、語学能力があることはもちろんですが、もう一つ、人柄が良いというのがあって、これが最も重要だと思うんです。途上国に来て上から目線でモノを言うような人は勘弁してほしい。一緒になって何とかしようという人がいい。結果としてその点が評価されていると思います。
田中 援助・支援ではなく協力だという考え方の背景は、戦後の日本が、国際社会の信頼を勝ち得ないといけない状況で国際協力を始めたからでしょう。日本も戦後すぐは貧しかったし、チャリティではなく日本のためにもなることだから、途上国と一緒にやっていこうという姿勢だったと思います。
北岡 私はもっと古いと思っていて、江戸時代には近江商人の「三方よし」の考え方もあったでしょう。略奪式の資本主義じゃなくてウィン・ウィンでいく。さらに遡ると、稲作農業というのはみんなで一斉に助け合わないとできないわけで、これは日本のルーツに則した考えではないかと。あまりエビデンスはないですけど(笑)。
田中 第二次世界大戦で酷いことをやったという反省が相当にあって、協力に当初関わった人たちには、そんな日本がアジアで上から目線でやる資格があるかという感覚があったと思います。ですから、長い伝統と直前の時代に対する反省の両方ですね。
出すお金の額よりも大事なことがある

田中 以上を踏まえてこれからの日本の役割を考えると、世界は複雑で、一刀両断でこうすればいいということはなかなか言えない。一方で、性急な判断で右往左往せずに、比較的長い視野で付き合える国と一緒にやっていこうという姿勢が成果を出し信頼を勝ち得ていると思うんです。
効果がある活動は日本だけでやるのではなく、世界中の機関に広げていこうという動きもあって、例えば母子手帳というのは、最近行ったアンゴラではJICAが15万冊分の支援をして、残りの数百万冊は他の機関や企業にお金を出してもらう形で普及させている。ODAでは、出すお金の額が大事だと錯覚されますけれど、大事なのはインパクトの大きさなんです。
北岡 教育も重要ですね。お金を集めるだけではなくて、現場でどう使われるかがもっと大事です。いい加減な教師が教科書を棒読みするだけでは子供には伝わらない。学校で言うと、多くの国で給食の支援もしています。アフリカなどには1日3回食べられない子供も大勢いて、給食があれば食べたいから学校に来る、そうすると健康状態も良くなって学力レベルも上がり、社会が安定するという一石三鳥なんです。
おっしゃるように波及する効果というのがあって、かつて東南アジアの支援をした時に、東南アジアはすでに発展を始めているのだからアフリカへの支援をもっと行なうべきという声があった。しかし私たちは東南アジアが発展すれば、彼らが他の国を援助する側に回ることができるだろうと考えたんです。さらに日本が充分な援助をできない事情のある国には、第三国支援という形を採っています。日本とタイが組んで他の国を支援するなどという形で、JICAの規模を超える形の協力が可能になっているケースもあります。
日本の提案で世界が変わっている
田中 国際政治は難しくて、日本が世界中の紛争を解決するなどということはできない。しかし、いろいろな場面で世界の問題に対して提案していくことはできるし、実際この数年間に日本が提案したことによって世界が変わるということが起きています。アメリカがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)から抜けるという時には、日本は残った国で維持しようと粘った結果、現在はイギリスまでがTPP に参加している。今後の世界経済のダイナミズムを考えるとインド・太平洋地域が重要ということでFOIP(自由で開かれたインド太平洋)という外交戦略を提唱すると、EU(欧州連合)までが関わるようになってきた。
先ほどの母子手帳のような事例も含めて、日本の影響力は増大していると思うし、多くの国で日本に対する信頼感が上がっている。この信頼感の向上ほど、日本の国益に直結することはないと私は思っています。
北岡 アメリカの国際政治学者ジョセフ・ナイが、軍事力や経済力のように相手を強制する「ハード・パワー」に対して、良い理念や文化で相手を魅了する「ソフト・パワー」の重要性を言っています。学校のクラスにたとえると、喧嘩の強い子や金持ちの子が影響力を持つだけではなく、いろいろな提案をしてまとめあげる力のある子も影響力を持つということなんですね。
もちろん軍事力や経済力にもテコ入れは必要ですが、それは前提として、それ以外でもアイディアを出していこうと。日本は先進国でありながら途上国の経験があり、かつアジアに位置しているわけで、これは絶好の条件だと思うんです。岸信介は日本が国連に加盟した翌年の1957年に、日本外交の三原則ということを言った。それは国連中心、自由主義諸国との協調、そしてアジアの一員としての外交です。しかし日本はその後、アメリカ中心の一原則になってしまった。アメリカのような超大国と向き合うと、相手の言うことにあまり逆らえないんですよ。
私は日本には複数の原則があるべきだと思います。それは日米に加えて日欧、アジア、アフリカ、そしてユニバーサルな国連です。インドとの関係なども、日本が2000年頃から深めてきた経緯がなかったら、FOIPもQuad(日米豪印戦略対話)も実現しなかったと思います。
国連でも大事なのは発言力なんです。ただ、日本にはお友達がいない。小さな国でもグループを作って発言すると一応聞いてくれるということがありますから、日本とドイツでもいいし、韓国でもASEAN(東南アジア諸国連合)でもいいから組んで提案すれば、世界は耳を傾けてくれますよ。我々は過去に行なってきたことにもう少し自信をもって取り組んでいくべきだと思います。
※この対談は、『覇権なき時代の世界地図』(北岡伸一著、新潮選書)刊行を機に行われたものです。
◎北岡伸一(きたおか・しんいち)
東京大学名誉教授。1948年、奈良県生まれ。東京大学法学部、同大学院法学政治学研究科博士課程修了(法学博士)。立教大学教授、東京大学教授、国連代表部次席代表、国際大学学長等を経て、2015年より国際協力機構(JICA)理事長、2022年4月よりJICA特別顧問。2011年紫綬褒章。著書に『清沢洌―日米関係への洞察』(サントリー学芸賞受賞)、『日米関係のリアリズム』(読売論壇賞受賞)、『自民党―政権党の38年』(吉野作造賞受賞)、『独立自尊―福沢諭吉の挑戦』、『国連の政治力学―日本はどこにいるのか』、『外交的思考』、『世界地図を読み直す』、『明治維新の意味』など。
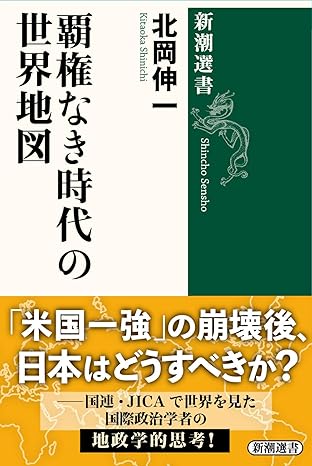
◎田中明彦(たなか・あきひこ)
1954年、埼玉県生まれ。東京大学教養学部卒業。マサチューセッツ工科大学大学院博士課程修了(Ph.D. 政治学)。東京大学東洋文化研究所教授、東京大学副学長、国際協力機構(JICA)理事長、政策研究大学院大学学長、三極委員会アジア太平洋地域議長などを経て、2022年4月より再び国際協力機構(JICA)理事長に就任。著書に『新しい「中世」―21世紀の世界システム』(サントリー学芸賞受賞)、『ワード・ポリティクス―グローバリゼーションの中の日本外交』(読売・吉野作造賞)、『アジアのなかの日本』、『ポスト・クライシスの世界―新多極時代を動かすパワー原理』など。

















































