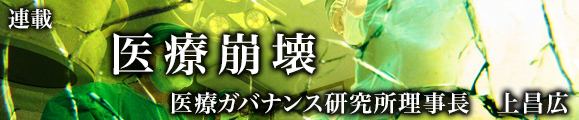東京大学の授業料の値上げが問題となっている。当初は7月中旬の入学者選抜要項発表時に約11万円の値上げを打ち出すとされたが、学内外の反対に鑑み、正式発表は遅れるという。
マスコミは、6月26日の『朝日新聞』の社説「大学授業料 公費支出増へ議論急げ」をはじめ、批判一色だ。
学内では、学生たちの反対活動が盛り上がっている。6月21日には、安田講堂に入ろうとした学生を制止した警備員が怪我をしたとして、東大が最寄りの本富士警察に通報し、警察官が本郷キャンパスに立ち入る事態となった。
1969年の安田講堂事件を受けて、東大と学生は、学内の問題を解決する手段として警察権力を利用しないという「東大確認書」を締結した。今回の対応は、この取り決めに違反している可能性が高く、学生の反発は益々強まるだろう。
私は、一連の議論はピントがずれていると感じる。なんのために学費を値上げするのか。それは東大の経営を安定させるためだ。いま必要なのは、誰がその費用を負担するかだ。客観的なデータに基づき、合理的に議論しなければならない。本稿で論じたい。
流動資産に乏しく脆弱な財務
まずは、東大の現状だ。経営状態は極めて悪いと言わざるを得ない。公開されている最新の決算である2022年度決算では、経常収益は22億円増の2663億円だったが、経常費用が95億円増の2715億円に膨らんだため、差し引き51億円の赤字だった。
この時は期首における資産見返負債のうち、「臨時利益」として930億円を計上し、黒字決算としているが、「次年度も約70億円の赤字で、各部局に一律6%の予算削減の通知がきた」(東大教授)という。今後も円安、物価・人件費上昇、資源高などが続けば、経営は益々悪化する。
東大の総資産は1兆4698億円だが、そのうち1兆2850億円は、処分が難しい固定資産だ。流動資産は1848億円、現金及び預金は1284億円しかなく、この調子で赤字が続けば破綻せざるを得ない。
この状況は、東大と文部科学省も認識している。
救済策の一つと考えられているのが、今年度から文科省が開始した「国際卓越研究大学」という制度だ。文科省は、「諸外国のトップレベルの研究大学が豊富な資金を背景として研究力を高めているのに対し、我が国の大学は研究論文の質・量ともに低調な状況にあります」「国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学を国際卓越研究大学として認定し、当該大学が作成する国際卓越研究大学研究等体制強化計画に対して、大学ファンドによる助成を実施します」と説明する。
文科省が立ち上げたファンドは10兆円規模。初の公募には東大など10大学が応募し、東北大学が選ばれた。初年度に約100億円が措置されるという。
70億円の赤字を出す東大にとっては干天の慈雨だ。ただ、今年度は採択されなかった。前出の東大教授は、「本部は、この制度に期待していたようですが、あてが外れました」という。これが、東大が反発覚悟で、学費値上げを強行しようとしている理由の一つだろう。
世界レベルに大きく劣る基金運用
基金運用は大学運営にとって重要だ。このことは東大も認識している。2021年4月の「総合科学技術・イノベーション会議 世界と伍する研究大学専門調査会」の配布資料には、「研究大学の基金の状況」という項目があり、欧米の一流大学の基金とその運用状況を紹介し、東大と比較している。
2019年度、東大の基金は149億円で2.45億円の運用益を得ている。これは欧米の一流大学と比べると大きく見劣りする。ハーバード大学の基金と運用益は、それぞれ4兆5023億円、2004億円だし、イェール大学は3兆3346億円、1409億円だ。英国のオックスフォード大学やケンブリッジ大学も、8235億円、4591億円の基金を運用している。
今回の対応は、東大など個別の大学では基金が運用できないので、国が代わってやろうということだろう。
このような考え方をしている限り、東大は益々ダメになる。我が国の財政状況や与党・財務省の対応を考慮すれば、運営費交付金であろうが、国際卓越研究大学制度の交付金であろうが、国からの補助金に頼っている限り、尻すぼみだからだ。
学問の自由を担保するには、経済的な独立が欠かせない。欧米の大学が基金運用に力を注ぐのは、自立を尊ぶからだ。米国でも公立大学の状況は異なる。カリフォルニア大学バークレー校、サンディエゴ校(UCSD)の基金は5279億円、1908億円で、ハーバード大学やイェール大学とは比べ物にならない。いざという時に公費が支出されるからだろう。
明治時代の先人たちも、このことを意識した。立花隆氏の『天皇と東大 大日本帝国の生と死』には、当時の関係者が国から独立するため、一回は巨額の資金を受け入れ、その後は基金として活用し、毎年補助金をもらうのはやめようと議論した様子が紹介されている。
この時、東大が政府からの独立を選んでいれば、現在の日本の大学の在り方は変わっていただろう。東大はお上頼みを選択した。この結果、東大は政府の財政難とともに成長できなくなった。
最大の問題は「法人化から20年の低成長」
世界的にみて、東大の最大の問題は、2004年の国立大学法人化以降、成長していないことだ。前出の「総合科学技術・イノベーション会議世界と伍する研究大学専門調査会」向け資料によると、病院収入を除く東大の収入は、2005年の1546億円から2019年には1855億円と約20%増であり、欧米の一流大学と比べて見劣りするという認識が示されている。
同時期にハーバード大学は3081億円から6062億円と約2倍、カリフォルニア州立大学サンディエゴ校は1615億円から3720億円と約2.3倍、オックスフォード大学は716億円から2201億円と約3.1倍、ケンブリッジ大学は1107億円から2959億円と約2.7倍に増えている。
この20年間で、収益規模の点で、米国の一流大学との差は決定的になったし、2005年の段階では、東大よりも経営規模が小さかったオックスフォード大学やケンブリッジ大学にも逆転されてしまった。
なぜ、こんなことになったのか。東大は、寄附金収入や特許収入が少ないことを問題視しているようで、前出の資料の本文23ページのうち、9ページを寄附、4ページを特許収入増加の施策に充てている。
いずれも重要な課題だが、やや的外れだ。それは、米国の一流大学と比較するなら確かに東大の寄附金・特許収入は少ないが、世界的には必ずしもそうではないからだ。2019年度の東大の寄附金、特許収入は、それぞれ104億円、9億円だが、これはケンブリッジ大学の150億円、8億円と遜色ないレベルである。
留学生で授業料収入を伸ばした欧米
東大が著しく見劣りするのは、前出の基金運用益以外には、授業料収入だ。
東大の授業料収入は165億円(授業料140億円、入学金21億円、検定料4億円)程度だ。国立大学法人化以降は、2005年度に年額1万5000円値上げしたが、ほぼ横這いだ。東大の授業料などの収入は、2022年度決算で経常収益(病院収入を除く)の8%を占めるに過ぎない。
これに対してハーバード大学は22%、オックスフォード大学は14%、UCSDは22%、UCバークレーは33%だ。特記すべきは、これらの大学では、2006年度から19年度の間に授業料収入が大きく増加していることだ。増加分は、最も少ないオックスフォード大学でも360億円、最も多いUCバークレー校では743億円に上る。
2006年度、UCバークレー校の収入に占める授業料の割合は17%で、研究費収入(30%)を大きく下回ったが、2019年度には、33%対23%と逆転した。かつて研究大学と考えられていた同校だが、いまや教育が経営の中核だ。
なぜ、授業料収入を増やすことができたのか。それは、留学生の受け入れを増やしたからだ。世界の留学生数は、2000年の160万人から2020年には560万人に増加した。経済発展を遂げた中国で、高等教育を希望する若者が増えたからだ。2018年には約100万人の中国人が留学している。このような中国人留学生が大学に富をもたらした。豊かになった中国人が、海外の名門大学卒業という学歴を得るためには出費を惜しまなかったからだ。
欧米の一流大学は、留学生の授業料は高く設定した。経済協力開発機構(OECD)によれば、米国の州立大学に通う学部学生の授業料は平均して8780ドルだが、留学生は2.8倍の約2万4500ドルだ。豪州は3.8倍、カナダは4.0倍だ。英国も同様だ。全体のデータは公表されていないが、オックスフォード大学では2.9~4.1倍、ケンブリッジ大学は2.4~6.3倍だ。このような国や大学では、留学生が高額な授業料を払うことで、国内の学生の授業料を日本の国公立大学と同レベルに据え置いている。
欧米の一流大学は中国人留学生の確保に走った。中国人が関心を持つのは、ITや金融、理工系、医薬系の実学だ。このような大学は、留学生が支払う学費を用い、世界中から優秀な教員をリクルートした。そして、2000年から2020年の間に米国は約67万人、カナダは約47万人、英国と豪州は約33万人の留学生を増やした。日本の大学生の数は、大学院生まで含めて約300万人だ。如何に留学生の存在が大きいかご理解いただけるだろう。
優秀な教員確保には金がいる
欧米の一流大学の学生構成は、この20年間で一変した。今夏、カナダのトロント大学で学ぶ大学生である森本理瀬さんが、医療ガバナンス研究所でインターンを経験した。森本さんは「在校生の半分が中国人です」という。これが、欧米先進国で進んでいる大学教育のグローバル化の実態だ。中国人の優秀な頭脳を「持参金」つきで集めていると見なすことも可能だ。
東大は、このような変化に対応出来なかった。在籍する留学生は4968人(2023年度)で、学部生の3%、大学院生の約3割を占めるに過ぎない。米英は勿論、カナダ、豪州、仏、独、さらに中国などの多くの大学と比べて見劣りする。
そもそも、東大も文科省も大学経営の視点から留学生への対応を考えたことがないのだろう。学費は、留学生も国内の学生も一律53万5800円だからだ。今回の学費値上げでも、差をつけるという話は出ていない。留学生の学費を上げることで、授業料減免の対象を拡大することができるにもかかわらずだ。
グローバル化が進む大学教育で、いかにして生き残るのか。東大は、その存在価値から考え直さねばならない。東大の第一義的な使命は学生の教育だ。優秀な学生を世界からリクルートしたいなら、優秀な教員を確保しなければならない。それには金がいる。
優秀な学生と教員が集まれば、自然に研究レベルも向上する。そのために、「国際卓越研究大学」制度の補助金に頼るか、海外からの留学生からの学費に頼るか、議論の余地はない。東大が生き残るには、「お上」にすがるのではなく、欧米や中国の一流大学と競争し、魅力的な教育を提供できるよう組織を改革せねばならない。