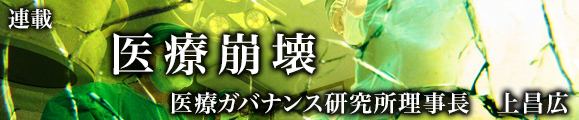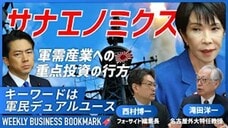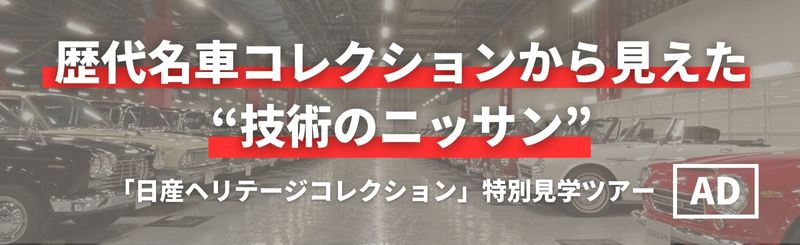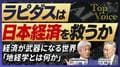花粉症の季節真っ只中だ。2月初旬から4月中旬にかけてスギ花粉、3月中旬から5月上旬にかけてヒノキ花粉が舞う。私の外来にも、大勢の花粉症患者が訪れる。一日に30人以上を診察することもある。
花粉症の増加は日本に限った話ではない。世界アレルギー機構の2016年の報告によれば、13~14歳の小児の花粉症の有病率は、世界全体で22.1%だ。地域別には北米33.3%、欧州33.5%、アジア23.9%、アフリカ29.5%、中南米23.7%などだ。過去15年間を平均すると年平均0.3%のペースで増えているという。
日本の花粉症の有症率は、世界でもトップレベルだ。2025年にウェザーニューズ社が実施した調査では、全国で58%の人が花粉症を発症していると報告されている。都道府県別では、山梨県が72%で最も高く、次いで三重県69%、静岡県68%と続く。
高齢者は避けたい「抗ヒスタミン剤」の連用
最近の花粉症の特徴は、高齢の花粉症患者が増えていることだ。2023年12月にユーグレナ社が実施した調査によれば、60歳以上の花粉症の人のうち、29.3%が60歳以上で新規発症したという。花粉症といえば、若年者の疾患というイメージが強いが、今や年齢を問わない国民病と言っていい。
その社会的損失は大きい。2月6日、パナソニック社が発表した「花粉症による労働力低下の経済損失額2025」によれば、花粉症に起因する労働力低下の経済損失は、一日あたり約2320億円だ。また、2019年3月に第一生命経済研究所が発表した試算によると、同年1月から3月の間に花粉症の悪化を避けるために外出を控えたことによる消費の低下は約5691億円という。
花粉症対策は、我が国の経済成長を考える上でも重要だ。特に、高齢の花粉症患者の対応は重要だ。その臨床像は、若年者と若干異なる。くしゃみや鼻水よりも鼻づまりが強く出ることが多く、皮膚のバリア機能が低下しているため、花粉が付着すると湿疹やかゆみなどの皮膚炎を引き起こしやすい。顔や首など露出部分に出やすく、掻くことで悪化し、美容にも影響する。花粉症は高齢者のQOL(Quality of Life)を大きく損ねる。
花粉症なら、普通に治療すればいいとお考えの方が多いだろうが、高齢者特有の問題がある。
花粉症の治療薬の中核は抗ヒスタミン薬だ。治療効果が異なる10以上の化合物が承認されているが、薬効と副作用の強さは比例する。代表的な副作用が眠気だ。服用者の3%しか眠気を催さないとされるフェキソフェナジンは治療効果が弱いし、治療効果が最も強いオロパタジンは、25%が眠気を訴える。眠気は転倒リスクの増加を招き、高齢者にとって重大な問題だ。
高齢者では、眠気以外にも譫妄や排尿障害を呈することが知られているが、近年注目されているのは認知症だ。2022年に台湾の研究チームが『加齢神経科学フロンティア』誌に発表した研究によれば、65歳以上ではリスクが1.8倍増加し、男性や併存疾患の多い患者でリスクが高かったという。同様の研究結果は、他のグループからも報告されている。高齢者では抗ヒスタミン剤の連用は避けたい。
眠くならない治療薬「ゾレア」
最近、この問題を克服する可能性がある治療薬がいくつか開発された。その一つが、ノバルティス社の抗体治療薬オマリズマブ(商品名ゾレア)だ。
この抗体治療薬はアレルギー反応を司るIgE抗体と結合し、その働きをブロックする。2009年に気管支喘息の治療薬として承認され、2019年に花粉症に対して適応拡大された。花粉症シーズンの前に投与を開始し、期間中は2〜4週ごとに皮下注射する。
ノバルティスが国内で実施した第3相臨床試験(F1301試験)によれば、プラセボ群と比較してゾレア投与群では、「鼻症状スコア」が1.03点減少しており、これは統計的に有意だった。この変化は「非常に困る、生活に支障がある」というレベルから、「困るが、生活に支障はない」レベルに改善することを意味し、臨床的意義は大きい。
免疫反応は年齢によって異なる。果たして、高齢者にも効くだろうか。この点については、現在、市販後臨床試験が進行中だが、おそらく問題はないだろう。それは、市販後臨床試験が終了している気管支喘息患者への投与で、65歳以上の有効率は48.7%と、65歳未満(50.6%)と遜色なかったからだ。副作用の頻度は6.6%と、65歳未満(9.3%)よりも低かった。
治療薬に即効性があり、眠気の副作用がないことは高齢者にとってありがたい。花粉症に悩む高齢者にとって福音だ。ところが、現場では使いにくい。
私の外来にも、ゾレアによって花粉症が改善した70代前半の女性患者がいる。重症気管支喘息のため、ゾレアが投与された。彼女は長年にわたり花粉症を患っていたが、「その年のシーズンは症状が消失した」という。それまで、花粉症の季節は「(抗ヒスタミン剤を連用するため)ボーッとすることが多く、ピーク時には家に閉じこもっていた」らしい。「花粉症から解放されるなんて夢のようだった」と語ってくれた。
その翌年、花粉症のシーズンがやってくると、「今年もゾレアを使ってほしい」と要望された。「昨年の経験が忘れられない」そうだ。ところが、使うことはできなかった。ノバルティス社が推奨する適格基準を満たさなかったからだ。
ゾレアを投与する場合、投与前に血液検査を行い、血清総IgE値とスギ特異的IgE値を確認しなければならない。総IgE値を測定するのは、この値に応じて投与量を決めるからだ。スギ特異的IgE値の測定は、重症度の判断基準なのだろう。患者の場合、総IgE値は基準を満たしたが、スギ特異的IgE値は2+で基準(3+)以下だった。
私はノバルティスの担当者に連絡した。担当者は親切な人物で、色々と情報提供してくれたが、「査定されるリスクがあるので、基準を満たさない患者に使うのは推奨できません」とコメントした。
医師は「混合診療規制」のリスクを無視できない
ゾレアは、1回の費用が3万〜10万円もする高額な薬剤だ。1シーズンの薬剤費は数十万円となる。基準を満たさない患者に投与して審査支払機関に査定された場合、クリニックは大きな損害を被る。高額医薬品だから、査定されるリスクは高い。
ただ、製薬企業が推奨する量より減量して使えば、薬剤費は安くなる。75mgバイアルなら1万1655円だ。少量から始めて、効きそうなら増やすことも可能だ。これなら費用は大幅に安くなる。
この患者は裕福だ。自費診療も可能だったが、私はその選択肢を提示しなかった。それは、混合診療規制に抵触するからだ。多くの医療機関で混合診療は行われている。私がこれまでに勤務してきた医療機関でも、厚生労働省直轄だった国立がん研究センター以外は、全てやっていた。厚労省は、よほどの問題がない限り介入しない。
ただ、市販後調査期間中のゾレアの適応外投与など、目立つことをやった場合に厚労省がどう動くかわからない。処分は役所の腹一つだ。混合診療を咎められれば、過去に遡り、巨額の診療報酬を返還することになる。そこまでのリスクを取ることができる医師が、どれだけいるだろうか。
公的保険財政が逼迫した昨今、厚労省が、不適切な処方を防ぐため、保険診療を厳格に査定することは理解できる。ただ、これでいいのだろうか。このような対応は、患者の利益だけでなく、日本経済にとっても問題だ。
「医療消費」は「命を金で買うこと」ではない
日本の家計の金融資産は約2230兆円だ。その内7割以上を高齢者が保有している。彼らが関心をもつのは健康だ。健康に積極的に投資したいと考え、そのニーズに応える形で、健康産業は様々なサービスを開発し、急成長してきた。
例外が医療だ。高齢者の関心が最も高く、成長するはずの業界だが実態は逆だ。インフレが進む中、診療報酬は抑制され、多くの医療機関が赤字に陥っている。3月10日に日本病院会など6団体が発表した調査結果によると、医療機関の69%が赤字という。
これは、厚労省が医療界を統制してきたからだ。医療は価格統制と量的規制が残っている数少ない領域だ。厚労省は、邪な連中が跋扈するのを防ぐために、自分たちが統制しなければならないと考え、医療費を社会的コストとみなし、抑制することが正しいとも思い込んでいる。
彼らの視点から抜け落ちているのは、医療が「消費」としての側面を持つことだ。今回のケースが、その典型だ。花粉症の治療を、どこまで公的保険でカバーすべきかは難しい問題だ。一方、前出の患者の場合、ゾレアを使えば、QOLは改善する。高齢者に対するゾレアの安全性は検証済みだ。自腹で使いたいと思う患者がいてもおかしくない。このような使用は、いわば「医療消費」である。
「医療消費」は公的保険財政を損なうことなく、医療産業を成長させる可能性がある。ところが、混合診療規制が障壁となり、このような市場は成長できない。
混合診療規制は、厚労省による価格統制の本丸だ。厚労省はもちろん、利権のおこぼれにあずかる業界団体や業界誌が、「命を金で買うのか」と必死で抵抗する。こうやって、日本の医療界はジリ貧を続けてきた。そろそろ、日本の医療の存続を本気で考えるべきである。混合診療規制の緩和がその一歩である。