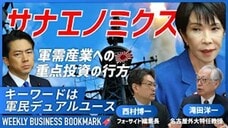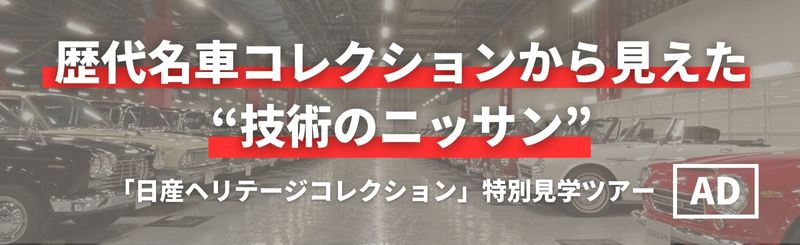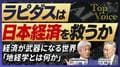現在、上野の東京国立博物館で、「古事記1300年 出雲大社大遷宮 特別展 『出雲―聖地の至宝―』」が開かれている(11月25日まで)。長年の考古学の成果が、一堂に会した形だ。 昭和58年(1983)に荒神谷(こうじんだに)遺跡(島根県出雲市斐川町)で大量の青銅器が発見されて以来、出雲(島根県東部)周辺から新史料の出土が相次いだ。しかも、どれもそれまでの常識を打ち破る発見ばかりだった。 結果、弥生時代後期、出雲が急速に勃興していたことや、ヤマト建国に出雲が貢献していたことが明らかになった。神話のお伽話に過ぎないと無視されてきた出雲は、「確かにそこにあった」のだ。 またヤマト建国の直後、出雲は謎の衰退に向かい、まるで出雲の国譲り神話が事実であったかのような経過を辿っていることもはっきりとした。 しかし、だからといって、これらの新史料が、古代史像を塗り替えたかというと、実に心許ない。「出雲神話は絵空事」という、かつての常識が謎の解明の邪魔をし、ヤマト建国をめぐる謎解きは、邪馬台国論争が中心だから、出雲の入り込む隙間がないのだ。また、「神話」が文学と民俗学の専門分野だったことも、障害になっている。学問の世界にも、学閥と縦割りの弊害が残されている。6世紀以前の歴史を、8世紀の朝廷が知っていたはずがないという史学者の「決めつけ」も、神話を見る目を曇らせている。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン



時事](/mwimgs/c/1/616mw/img_c17251eddddb31407ad3b885091d361a18096.jpg)