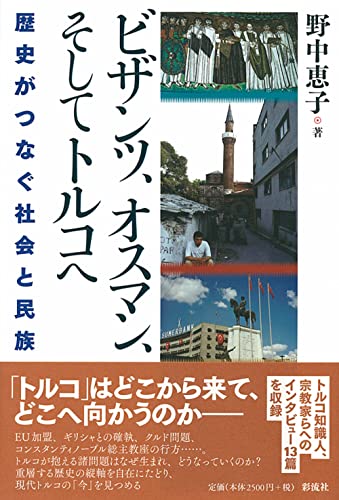3月31日、トルコ共和国で行なわれた統一地方選挙では、現職のレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領率いる親イスラム保守派の公正発展党(AKP)など与党連合が地滑り的な敗北を喫した。選挙戦を制したのは、国父ケマル・アタテュルク(以下「アタテュルク」)の遺産である中道左派の共和人民党(CHP)である。2018年に元祖イスラム派政党の復活として結党された新福祉党(YRP)が予想外の大躍進をしたことも、AKPを震撼させた理由だ。
AKP大敗の直接の要因は、エルドアン氏の独自な理論に基づく金利政策が招いたトルコ・リラ暴落と高インフレに、国民が耐えきれなくなったことだが、国内で現在も公式発表で310万人以上のシリア難民や他の非正規移民を抱える葛藤、昨年2月に発生した大震災の復興の遅れも大きい。エルドアン氏は熱狂的な岩盤支持層から「世界の指導者」と持ち上げられてきた、さしずめ“現代トルコ帝国のスルタン”だが、大半の国民がその政権運営の問題点を直視し始めたのは明らかだ。野党は国政選挙の前倒しを強く求めており、憲法再改正で大統領3期目を狙うとされるエルドアン氏が巻き返しのため解散に打って出るとの観測もある。
AKP単独政権は22年の長期にわたるため、トルコ国内も世界も、もはや殆どエルドアン氏のトルコしか知らない。北のロシア・ウクライナ戦争、南のイスラエル・ハマス紛争という二つの危機に挟まれているトルコの今回の選挙結果は地域全体にとっても重要な転機となり得るものだった。
内政混乱の産物としてのAKP政権
AKPは1960年代に始まったトルコのイスラム思想「国民の視座」を基盤とした国民救済党(MSP)の後継である福祉党(RP)を母体とする。1996年のRPの短期連立政権での首班獲得、その6年後(2002年)のAKP単独政権獲得は、どちらも冷戦終結後の世界的な民族主義の復興を受けたイスラム再台頭の結果と言われてきた。しかし、それはトルコがイスラム教の国であることによる先入観からくる誤解だ。AKPが政権を握った根本的な理由は、20世紀後半のトルコ政界の慢性的な混乱である。
トルコでは1923年の建国から第2次世界大戦終結時まで実質的にCHPの一党独裁体制が続いたが、戦後デモクラシーの中で様々な新党が誕生した。しかし冷戦下で早々から社会・経済構造上の脆弱さが露呈して政情不安に陥り、1960年と1980年に2回の軍部クーデターがあった間に、軍政を含め15回の政権交替と20回の内閣改造を経験した。その間、単独政権だったのはわずか5年5カ月だ。他は過渡的な軍政を除き、政府維持のために水と油の各党が連立組閣を繰り返していたのである。1970年代は政界が機能不全に陥り、高位軍人出身の大統領による組閣要請と各党首の組閣失敗が続いたのは、冷戦という外生的要因だけでは説明がつかない。この間MSPも3度連立入りし、党首はいずれにおいても副首相になった。MSPは宗教派だったが少数派の代弁者として受容され、脅威とは見做されていなかったのである。
1983年の民政移管時に殆どの政党が一新されてからは、中道右派の祖国党(ANAP)単独政権が8年続いた。だが、1994年にRPがイスタンブール・アンカラ両市長選を制する(この時のイスタンブール市長選当選がエルドアン氏の政界デビューとなる)。RPはその勢いで翌年トルコ議会第一党に躍り出ると一気に宗教色を強めた。1998年に世俗主義への違憲判決で閉党処分となったが、後裔政党の一つとして2001年に結党されたAKPが、翌2002年の総選挙でいきなり単独政権を獲得した。それは、ANAP単独政権崩壊からの11年間で7回も連立政権が交替したことへの反動だ。政界は冷戦終焉による新時代到来のチャンスを活かせず、政治の寸断に翻弄され続ける国民は、保守派・革新派を問わず過去から学ばない都市型エリートの各政党に嫌気がさした。そこで第一段階として、他とは異色の超保守性が逆説的に変化の風穴を開けられると見てRPへの付託を試み、第二段階でAKPを確信的に選択したのだ。
既存政党との差別化によって台頭したAKPは、世俗派から警戒の強かった「国民の視座」との関係を解消して宗教色を希釈し、地方と庶民を包摂する幅広い保守派に衣替えしていた。これが大当たりになった。
国民の信仰心を政権の基盤固めに利用
トルコで敬虔なイスラム教徒ではなくとも国民が親イスラム政党を選択するのは非合理的ではない。なぜならトルコ国民の99%はイスラム教徒である。キリスト教徒人口がまだ一定数存在する近隣の中東諸国との大きな違いで、トルコの日常は宗教別ではほぼイスラム教一色だ。
トルコ共和国は第1次世界大戦でのオスマン帝国戦後処理の一環で、連合国側の思惑とアタテュルク率いるトルコ新政府の要望が一致した結果、ギリシャとの宗教別住民交換により人口を純化して建国されている。先進西欧諸国と肩を並べるイスラム教徒の国民国家に変わることが100年前の建国の目的だったため、純粋な信仰心だけでなく、教条的なアタテュルク主義によっても、祖国愛とイスラム教の価値は一体で不可分である。
従ってトルコにおいてどの政党が政権につこうと、イスラム教を否定するという、国是の破綻を招く施策はありえない。あったのは欧米を模範とする現代的な国家体制・国民生活を実現させる世俗化政策と、アタテュルク亡き後のCHPによる残留キリスト教徒への迫害だ。しかし、信仰心と世俗主義の間の違和感を解消できない一定の人口が存在し続けた。これがRPを生んだ背景であり、AKPが利用した点だ。
AKPは政権を取るや、半ば宗教心から、半ば従来政権との差別化目的から、抑圧されてきたイスラム教の解放を喧伝し、呼応する人々を政権の脇を固める新たな権益層にした。世俗派のうち建国エスタブリッシュメントの連綿たる流れを汲む人々以外にとっては、乗り遅れるわけにはいかない時流の転換点であり、AKPへの支持は急速に拡大し強固となった。当時BRICsと言われた諸国がトルコ同様に高い潜在力を有する旧帝国や大国であったことに照らせば、グローバル時代を迎えたトルコ経済の伸張は、安定した単独政権が続くのであれば既定路線であったと考えられる。
特に他国に先んじて旧ソ連圏の各地に進出可能になったことは大きかった。ロシアはオスマン帝国にとり最もよく知る隣国であり、トルコはソ連から独立戦争期・建国期を通じて支援を受け、深い関係性を構築していた。今日のトルコのロシア・ウクライナ双方との特別な関係は、エルドアン氏個人の成果のように強調されていても、実際には過去のこうした文脈にもとづいている。エルドアン時代にトルコで国内キリスト教徒の処遇が改善されたのは、良心の問題と宗教連合国家であったオスマン帝国時代の秩序の象徴的な回復、EU基準への適合問題に加え、正教はギリシャをはじめとする旧オスマン帝国キリスト教属州諸国の他、ロシア・ウクライナ双方との友好関係保持の切り札になるからであり、両国間戦争の勃発はその成果をエルドアン氏にもたらすことになった。
凶と出た「新オスマン主義」外交
軌道に乗ったAKP政権は、中東のオスマン帝国旧属州を率いる旧宗主国としての立ち位置を明確にし始めた。それが「新オスマン主義」と呼ばれる、トルコを中心国としたイスラエルを含む中東アラブ地域との共栄圏構想の実践で、「ゼロ・プロブレム」外交の中核となる。ただし、それはあくまでもトルコから見た21世紀の中東像であり、中東諸国から見たトルコ像は考慮外であることが新オスマン主義の誤算の一つだった。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。