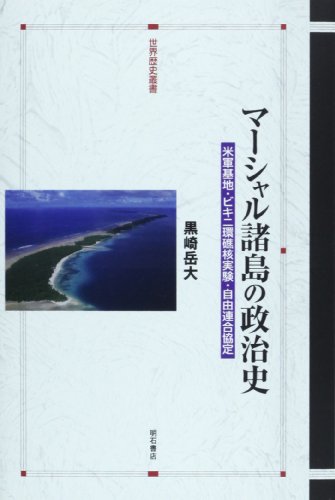「ニューカレドニア独立運動」が浮き彫りにする太平洋諸島地域の地政学――日本は“懸け橋”になれるか

2024年5月、南太平洋でも指折りのリゾート地であり、「天国にいちばん近い島」として知られるフランス領のニューカレドニアから、衝撃的なニュースが届いた。13日夜、ニューカレドニアの先住民カナックの若者たちが南部の中心都市(首都)ヌーメア郊外の幹線道路を占拠、車両に放火したり、商店に侵入して略奪を行うなどの大規模な暴動が発生した。現地からの報道によれば、この暴動で治安部隊の隊員2名を含む7人が死亡、90人以上が負傷する事態となった。また暴動に参加した若者たち約350人が拘束された。暴動時には観光客を含む約300人の日本人がニューカレドニアに滞在しており、空港が閉鎖されたことで海外へ逃れることができず、現地に住む日本人から事態の収拾が見えないことへの不安の声がインターネットを通じて届けられるなど、日本国内でもその深刻さを多くの人々が知ることになった。
今回の暴動は、フランス本国で進められていた憲法改正の動きと深く関係している。従来ニューカレドニアでは先住民カナックの権利を守るという目的から、ニューカレドニアの地方選挙の参政権は「1998年以前にニューカレドニアで選挙人名簿に登録された者およびその子孫」に限定されてきた。しかし、今回の改正ではそれが緩和され、「ニューカレドニアに10年以上暮らす住民にまで拡大する」という案がフランス議会に提出され、賛成多数で可決されたのである。このことで、新たに移住してきた人々にも参政権が付与されることになり、先住民カナックは自分たちの票の重みが失われかねないと反発した。当初は抗議活動によるデモであったものが、徐々に暴動へ発展していき、上述の略奪や放火へとつながったのである。
今回、カナックの若者たちの残虐な行為が映像で繰り返し放送されたこともあり、彼らに対して非難する声が大きかったように思われる。ただし、カナック側の視点から見ると、この暴動が起きたのは、これまでのフランスの植民地並びに海外領土という歴史の中で先住民の権利が十分尊重されてこなかったためであり、その歴史を知ることが必要だ。また、暴動の背景にはフランスとニューカレドニアという二者の関係にとどまらず、周辺諸国の思惑も大きく関与しており、太平洋諸島を取り巻く新たな国際秩序をめぐる動きの中で理解しなくてはならない。
住民がボイコットした3度目の住民投票
ニューカレドニアがフランス領になったのは1853年である。当初フランスはこの地を流刑地としていたが、ニッケル鉱山が発見されるとヨーロッパやアジアから多くの移住者が次々とやってきた。フランスはニューカレドニアを植民地化する過程で、メラネシア系の先住民カナックから武力で土地を奪い、山間部に作られた居住地に強制的に移住させるなど、「土着民法」の下で彼らの権利を奪っていった。第二次世界大戦後、土着民法は廃止され、カナックも市民権を獲得したが、それでも彼らが従来住んでいた南部の地域には多くのヨーロッパ系住民が移り住んでおり、自分たちの土地を回復することはできなかった。
1950年代になると、植民地独立問題に端を発して第四共和政が崩壊したフランス本国の政治状況の影響を受け、フランスに留学していたヨーロッパ系住民と協力して、カナックたちもフランスからの解放を求める反政府運動に参加するようになる。さらに1970年代に入ると、近隣のイギリス植民地であるパプアニューギニアやフィジーなどの独立達成を目にし、カナックも権利回復やフランスからの独立を目指していった。しかしながら、ニューカレドニアでは、フランス系をはじめとしたヨーロッパ系住民ら、独立に反対するグループが人口の多数を占めていた。そこでカナックは、自分たちの活動はフランスによって奪われた権利を回復する脱植民地運動であり、先住民文化を回復するための運動であると訴えた。1980年代以降、独立運動を牽引するカナック社会主義民族解放戦線(FLNKS)を中心に、各地で暴動が起こされ、ニューカレドニア全土に非常事態宣言が出されるほどにまでなった。
フランス政府も国際社会からの注目が高まる中でカナックたちの要求を無視できなくなり、FLNKSとの間で協議が行われた。その結果、1988年にマティニョン協定が締結され、カナックの自治権拡大が約束された。さらに、1998年に結ばれたヌーメア協定では、2014年から18年までの間に独立の是非を問う住民投票を実施すること、否決された場合でも議会の3分の1以上の要請があれば、2020年、2022年と、最大3回まで住民投票を実施できることが決められた。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。