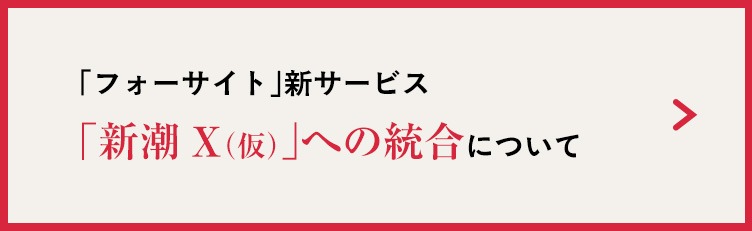一九〇〇年のパリ。「ベルエポック」(良い時代)と歴史家があとから振り返って呼ぶように、この時代のフランスは戦争もなく、町には街灯がつきはじめ、次々と普及する自動車、電話など新しいテクノロジーが、明るい未来を約束するように見えた。このムードの頂点となったのが、パリ万博である。 主催者だったフランスをのぞくと、日本から出展された作品の数は、米国、英国に続いて二十八国中三番目に多い。ジャポニズムといわれる、日本に対する並々ならぬ関心の表れだろう。その中でもセンセーショナルな話題をさらったのは、女優・マダム貞奴こと川上貞奴の演技であった。当時、一世を風靡していた「女優サラ・ベルナールでも及ばない悲しみの表現」と批評家は絶賛し、彼女の演技を見たロダンやピカソは強い霊感を受けた。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン