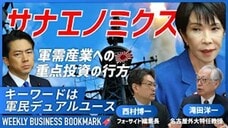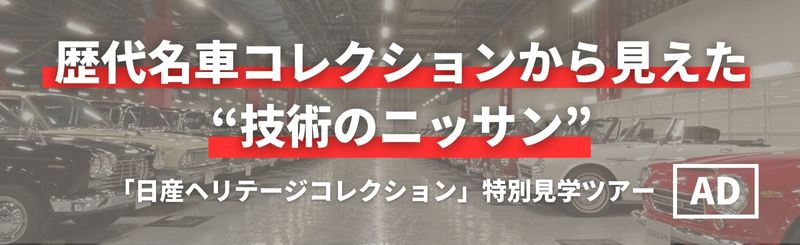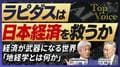本格始動した第2次トランプ政権(トランプ2.0)の内外政策が、世界を揺さぶっている。2月初旬にはメキシコ・カナダへの25%関税賦課と中国への10%追加関税賦課を発表。いずれの相手国からも激しい反応と応酬が見られたが、メキシコ・カナダからは問題視されていた国境管理の厳格化などの対応策が取られたため、関税発動は見送られ1カ月間は停止となった。他方中国への追加関税は実施に移され、中国は直ちに対抗措置として関税引き上げとWTO(世界貿易機関)への提訴を行っている。これらの関税を巡る動きで、世界経済に不安が生じ、ニューヨーク市場を始め各地で株価が乱高下した。同盟国でさえも関税のターゲットとなりうることが改めて明らかになり、今後のトランプ2.0の通商・貿易政策に世界は身構えることになる。
また、就任初日以来、矢継ぎ早に発表されている大統領令などにおけるトランプ2.0の重要政策も米国内外を揺さぶり続けている。筆者は、トランプ2.0の基本スタンスは、①「アメリカを再び偉大にする:MAGA」と「アメリカ第1主義」の重視、②ワシントン政治の「常識」には囚われない独自のイニシアティブ重視、③バイデン前政権の政策からの方向転換、④まず揺さぶりや圧力を掛けて、そこからDeal(取引)を目指す交渉スタイル、などの要素から構成されることになると見ている。ここまでに発表された大統領令などは、発足直後のトランプ2.0の優先課題と見なされるが、いずれも、上記の4つの基本スタンスに適うものとして読み解くことができる。
これらの政策はまさに多岐にわたるが、本稿では筆者の専門あるいは主要関心領域とし、主にエネルギーと気候変動問題に関わる政策に限定して論を進める。
投資・資金支援で高まる中国の存在感
まず、気候変動政策に関しては、事前の予想を裏切ることなく、気候変動対策の国際協定である「パリ協定」からの再離脱を大統領令で発表した。第1期政権の際にも離脱したが、バイデン前政権が協定に復帰し、改めて再離脱となった。パリ協定に縛られることは米国の国益に沿わない、との判断である。この再離脱で、気候変動対策としての資金コミットメントからも離脱したため、昨年のCOP29(国連気候変動枠組条約第29回締約国会議)でまとまった先進国からの途上国支援、年3000億ドルの確保は困難になった。米国が離脱した分を日欧が肩代わりすることもできない。資金支援の拡充を重視してきた途上国の不満・批判はいや増し、気候変動問題を巡る南北対立の激化は避けられない。この問題における先進国の影響力の地盤沈下は必至で、代わってクリーンエネルギー投資拡大などで中国の存在感・影響力が高まることになろう。
エネルギー政策に関しては、「Drill, Baby, Drill(掘って掘って掘りまくれ)」を推進する取り組みが大統領令などで示されている。一つには、アメリカのエネルギー資源・供給ポテンシャルを様々な制約から解き放ち、「エネルギードミナンス」を追求する大統領令が発出された。従来の政策・規制・制度などが、供給拡大の制約になっている点を踏まえ、それらの撤廃や認可の効率化などが図られることになる。バイデン前政権が発した「LNG(液化天然ガス)新規輸出許可の一時停止」を解除し、またインフレ抑制法(IRA)などによるグリーンニューディールの予算使用を停止する、などの内容が含まれている。
対イラン圧力によって原油価格上昇の可能性も
また、もう一つ注目されるのは、大統領令で「国家エネルギー緊急事態宣言」が出され、米国のエネルギー供給が需要に対して十分でない緊急事態にあるとの認識の下、関係省庁などに追加的な権限を与えて迅速な対応を求める内容となっている。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。