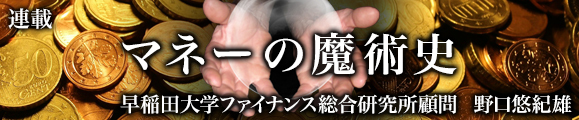田沼意次の貨幣改革
田沼意次の時代、いくつかの新貨幣の導入が行われた。1765年(明和2年)に、明和5匁銀が発行された。これは計数貨幣を意図している。それまでの銀貨は「秤量貨幣」であり、貫匁分をもって量られていた。それに対して「計数貨幣」は、額面で価値が決まるもので、取引の際に秤量する手間を省ける。
ただし、高木久史『通貨の日本史』(中公新書)によれば、むしろ重要なのは、市価に関係なく、法定比価に基づき、明和5匁銀1枚を額面12分の1両相当としたことだ。法定比価を強制すれば、幕府が利益を得ることになる。だから、財政補填が目的であったというのだ。ただし、明和5匁銀は失敗に終わり、普及しなかった。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン