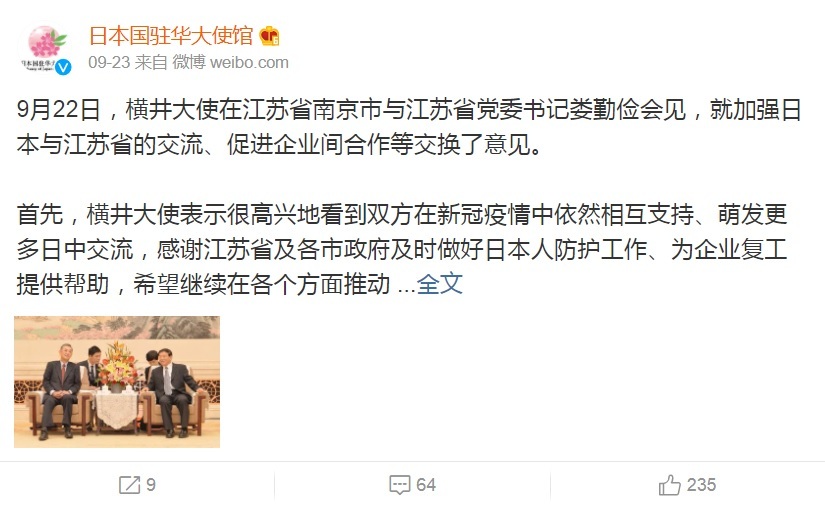
9月22日、江蘇省の婁勤倹・共産党書記と会見した横井裕・駐中国大使。在中国日本国大使館「微博(ウェイボー)」公式アカウントより
8月11日、中国の習近平国家主席が国営メディアを通じて「食べ物の浪費禁止令」を指示し、それを実施しようと、大きな国民運動に発展している。この運動が、すでに以前から節約モードにある外交饗宴に、どう影響するのか注目される。
離任のあいさつで奔走
近々、任期を終えて帰国する横井裕・駐中国大使は、9月末までの約1カ月、離任のあいさつ回りや、それを兼ねたイベント出席で地方を駆け巡った。日本大使館のホームページによると、山東省(8月26~29日)、江蘇省(9月22日)、上海市(同23日)、遼寧省(同24~25日)、海南省(同28日)と、中国沿岸の省を南北に奔走した。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン













































