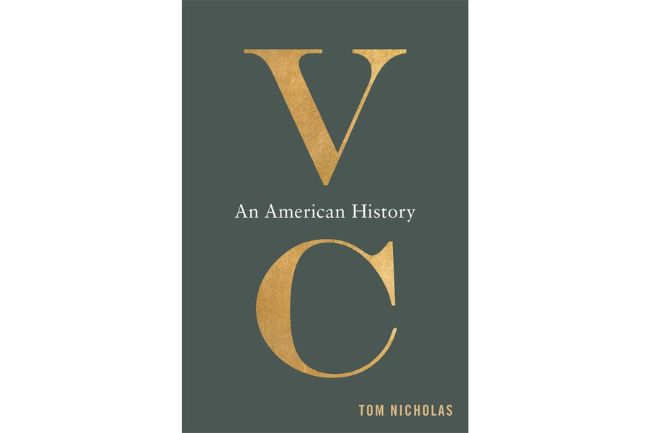GAFAの原点は「捕鯨」である――ベンチャーキャピタルの歴史が物語る「リスクテイク国家」アメリカ
Tom Nicholas『VC: An American History』
俗説ではあるが、スタートアップ企業への投資は「千三つ(せんみつ)」の世界と言われる。1000件の起業や投資案件があったとして、IPO(新規株式公開)にいたるなどして成功を収めるのはそのうち3件程度に過ぎないという意味だ。
現在はハーバード・ビジネス・スクールの教授であり、MITスローン経営大学院やロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの教職も歴任してきたトム・ニコラスによる『VC: An American History』は、アメリカにおけるベンチャーキャピタルの歴史を詳述する。
捕鯨航海に見るベンチャーキャピタルの起源
ベンチャーキャピタルのビジネスモデルの本質とは、利益配分の極端な歪みである。多数のスタートアップ企業で構成される企業群(投資先の「ポートフォリオ」と呼ばれる)に出資し、ほんの一握りの投資先のパフォーマンスから莫大な利益を獲得することを目指す。一方で、他の大多数の企業が低リターンに甘んじたり失敗したりするのはやむを得ないと考える。投資先企業からのリターンは、株式市場のように標準的な「釣り鐘型」(正規分布のような形状)ではなく、「ロングテール型」に分布する。縦軸に近いところ、つまり全く利益が出ないところに大きな山ができ、右側(リターンがプラスの方向)に長い裾野が形成される。プラス方面に突出して伸びた投資案件が、全体のリターンの大半を生み出す。本書冒頭でニコラス教授はそう語るが、それこそが「千三つ」たるゆえんだ。
今日存在しているベンチャーキャピタル企業の元祖は、1946年に設立されたARD(アメリカン・リサーチ&デベロップメント社)であるというのが一般的な理解だ。しかし、ロングテール型のリターンモデル――別の言い方をすれば、アメリカにおける起業家たちの冒険心と抑えられない貪欲さ、金銭的利益の飽くなき追求の起源は、それよりもはるか昔、19世紀の捕鯨航海に原型を見て取れると語るところに、本書のユニークさがある。
石油産業に代替されるまで、鯨油は貴重なエネルギー源であり、捕鯨はアメリカにおける一大産業であった。1850年頃には世界中で運航している捕鯨船の75%近くをアメリカ国籍の船が占め、ニューイングランド、その中でもニューベッドフォード(マサチューセッツ州の南部海岸に位置する都市)が捕鯨業の中心地であった。
捕鯨航海は広大な地理的領域において、捕獲が非常に難しいクジラの群れを何年もかけて追いかけるものであり、多くの資本を必要とするとともに、その航海には危険がつきものだった。作家のハーマン・メルヴィルがのちに乗組員の回想から着想を得て『白鯨』を執筆したことで知られる捕鯨船エセックス号は、1820年の航海中にマッコウクジラと衝突して転覆・沈没し、乗組員たちは救命ボートで命からがら生き延びた。
なるほど、大海で命を落とすリスクまでは無いものの、現代のベンチャーキャピタルと19世紀の捕鯨業には酷似している点がある。つまり、出資者からの資金を受け入れた企業(捕鯨でいえば航海)の圧倒的多数は失敗し、数少ない“ヒット”が、損失を出したり平凡なリターンに終わった投資を補うのである。そして、捕鯨航海もスタートアップへの投資も非常に不確実性が高く、どの投資が “ヒット”するかを事前に見極めることはきわめて難しい。
そこで重要な役割を果たすのが、専門的な知識を持ったエージェントである。資金を提供できる富豪たちと、先行き不透明な捕鯨に従事しようという荒くれ者の船長や乗組員、そしてその両者をつなぐエージェント(捕鯨船の経営代行業者)の関係は、今日のベンチャーキャピタリストが、資本を提供する年金基金などの投資家と、資金を獲得しようとする起業家たちとを仲立ちする関係とほぼ同じと言ってよい。
捕鯨エージェントは、船主や船長を集めるだけではなく、船主たちと保険の範囲や内容を決め、標的とするクジラの種類と漁場の地理的範囲について船長たちに助言をした。つまり彼らは、単なる仲介業者ではなく、捕鯨スタートアップのオーガナイザーであった。今日のベンチャーキャピタルが単に資金の仲介をするだけでなく、起業家たちに経営のアドバイスをするのと同じように、彼らは捕鯨航海に関する専門的な知識を武器とした。調査の情報源として、過去の航海日誌にも目を通していたという。そして、わずかな数の成功者たちが莫大な富を手に入れたのである。現代の著名ベンチャーキャピタリストとかなり近い。
「ベンチャー国家」として発展してきたアメリカ
捕鯨産業はやがて衰退を迎えたが、アメリカはわずか250年弱の歴史の中で、特定の産業に対するリスク資本の集中投資を何度も繰り返している。
そもそもアメリカ合衆国という国家自体が、移民たちによるスタートアップであり、「ベンチャー国家」とも言えるだろう。イギリスからの独立から間もない1790年頃、最大の都市であるニューヨークの人口はわずか3万人強に過ぎず、既に85万人を上回っていたロンドン、50万人のパリには遠く及ばなかった。カリフォルニアに至っては、地の果ての原野であった。
リスク投資の歴史は綿織物業への集中投資から始まり、1830年代には鉄道が大規模に敷設された。19世紀の後半には石油産業が誕生し、1879年にはエジソンが白熱灯を発明、電気の時代に突入した。鉄鋼王のアンドリュー・カーネギーや石油王のジョン・D・ロックフェラーは莫大な富を形成し、今日まで存在している金融機関も誕生する。エジソンの研究所にジョン・ピアポント(JP)モルガンが投資をしたことに端を発して1892年に誕生したのが、ゼネラル・エレクトリック(GE)社である。電気は、個人にとっては照明として、企業にとっては動力源として利用可能であり、非常に幅広い分野への適用が可能である(こうした性質を本書では「一般用途」と呼んでおり、石油や、現代の半導体やマイクロチップも同様の性質を有している)。
こうした技術革新やエネルギー開発の影響は当然ながら他の国にも及んだが、とりわけアメリカがその果実を享受できた重要なポイントして、地理的な集積が挙げられる。主要な産業が移り変わるとともに、その産業の「ホットスポット」も変遷してきたのだ。ニューベッドフォードが捕鯨産業の中心地であったように、1870年代から1910年代にかけては、オハイオ州クリーブランドとペンシルべニア州ピッツバーグが、電灯、化学、石油、鉄鋼といったテクノロジーの中心地になった。やがて自動車産業が隆盛するとデトロイトと五大湖周辺が中心となり、半導体と情報通信技術(ICT)の時代である現代は、西海岸のシリコンバレーに資本の重心が移っている。
産業と資本の集積にあわせてベンチャーキャピタルの原型とも言える仲介業者たちも変化を繰り返したが、ベンチャーへの投資が産業として洗練されたのは第二次世界大戦後である。前述したARDをはじめとして、1940年代から1960年代にかけてベンチャーキャピタル自体の機関化・制度化が進み、今日でも支配的である「リミテッド・パートナーシップ」という組織構造が主流となった。拠出した資金以上には責任を負わないこの組織形態は、外部投資家から資金を呼び込む事に寄与し、税制面も含めて政府とベンチャーキャピタルとの関係も整備が進んだ。1980年代までには、セコイア・キャピタルなど著名なベンチャーキャピタルの多数がシリコンバレーに誕生し、人・技術・市場構造などに着目して投資を行う投資スタイルや方法論も洗練されていった。
シリコンバレーの時代は続くのか?
20世紀末には、ベンチャーキャピタルの支援を受けた企業数がアメリカの上場企業全体の20%を占め、その時価総額のシェアは30%以上にのぼった。ICTセクターがアメリカの経済活動全体に占める存在感はベンチャーキャピタル業界の躍動と歩調を合わせて増大し、当時のICT分野の大手6社(マイクロソフト、インテル、IBM、シスコシステムズ、ルーセント・テクノロジー、デル)の時価総額合計は1999年末で当時のアメリカ全体のGDPの20%近くに達していた。
その後、ドットコムバブルの崩壊という、ある種の「調整」はあったものの、2022年現在ではいわゆるGAFAが我が世の春を謳歌しており、この4社の時価総額だけで日本の上場企業全体の時価総額を上回っている。
それでは、この繁栄はいつまでも続くのだろうか。本書は端的に「シリコンバレーは生き残れるのだろうか」と問いかける。
実は既に、スタートアップ企業がアメリカにもたらす創造的破壊に陰りが見られるのではないかと示唆する兆候がある。GAFAといった“ヒット”を超える“ホームラン”企業は、ベンチャーキャピタルの支援を受けて会社を立ち上げ、市場を征服するまでに成長したが、その間他社に追い抜かれるほどの脅威を受けることはなかった。企業が製品につける価格と、製品を製造するときの限界費用との差を示す「マークアップ率」は、1980年には限界費用に対して約20%だったが、2014年には約70%まで上昇した(National Bureau of Economic Researchの論文“The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications”(Working Paper 23687)より)。
これは(スタートアップではなく)既存企業がイノベーションを強化した結果、既存企業が市場での力を拡大し価格競争にさらされなくなっている事を示唆しているかもしれない。また、2000年頃からビジネスの活力が著しく弱体化しているという見方もある。設立後5年以下の若い企業によって生み出される雇用者数、若い企業の雇用全体に占めるシェアがいずれも低下しているのだ(American Economic Reviewの論文“Declining Business Dynamism: What We Know and the Way Forward”(Vol.106, No.5, May 2016)より)。
それでも、本書でベンチャーキャピタルとその歴史を俯瞰すれば、シリコンバレーおよびアメリカが、他の国では簡単に模倣できないようなレガシーを保持していることもまた分かるだろう。シリコンバレーは、計画的に発展したわけでもないが、全くの偶然で発展したわけでもない。シリコンバレーとは、教育機関での人材育成、軍の需要に基づく政府による科学技術投資、主要なハイテク企業、高度な技能を持った移民など、さまざまな要因が結集した結果なのである。そこには、ロングテール分布の損失の山に沈んだ、無数のリスクテイクの集積が築き上げたレガシーがあるのだ。
※本書は2022年9月22日、新潮社より『ベンチャーキャピタル全史』として刊行される予定。