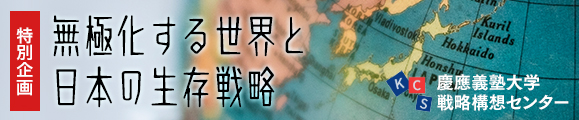2010年代以降の日本と諸外国との安全保障・防衛協力の進展は目覚ましい。自衛隊と各国軍の間の共同訓練・演習は大幅に増加し、日英伊3カ国による次期戦闘機共同開発計画(GCAP)に代表される防衛装備品協力も拡大している。同時にインテリジェンス協力も注目され、米国、英国、豪州、カナダ、ニュージーランドの5カ国によるインテリジェンス協力の枠組みである「ファイブ・アイズ」の名前を聞く機会も増え、日本の参加を求める声も内外に存在する。NATO(北大西洋条約機構)との関係も強化されている。
これらは、安倍晋三政権下で大きく発展したが、その後も引き継がれており、日本の対外関係の方向として定着したようにみえる。
しかし、これらをさらに進めることを妨げる巨大な障壁が存在する。それが「情報セキュリティ(information security)」である。これにはさまざまな要素があるが、安全保障・防衛においては、保有する情報、他国から共有された情報を漏洩しないことがすべての基礎になる。しかし日本は情報セキュリティを確保するための十分な体制を欠いており、同盟国である米国や価値を共有するその他の同志諸国(like-minded countries)の信頼を得られていないことが問題なのである。
以下では、情報セキュリティに関連するいかなる問題が現に発生しているかを検討する。この問題は、セキュリティ・クリアランスなどの個別の制度をめぐる課題として論じられることが多いが、情報セキュリティ分野での日本の取り組みが進まないために他国との安全保障・防衛協力の機会が制限され、国益を損なっていることへの認識自体が、政治やメディア、そして社会全般においても低い現状がある。まずは問題の深刻さを認識することが課題解決の第一歩になる。
問題の解決には法改正をともなう改革が必要であることを考えれば、そこで鍵を握るのは政治、なかでも特に国会だといえる。
同盟国の懸念と苛立ち
日本政府における情報セキュリティの問題は、決して新しいものではない。日本は冷戦時代から「スパイ天国」だと揶揄されてきた。2014年に施行されたいわゆる特定秘密保護法は重要な前進だったが、反スパイ法やセキュリティ・クリアランス制度などは残された課題である。またサイバー関連の能力向上には政府全体としても防衛省としても取り組みが進められているものの、課題解決への道のりはまだ長い。そして、そうした制度の整備とともに、それらを日々運用していく人材の育成も見逃してはならない課題である。
最近の例としては2023年8月7日付の米ワシントン・ポスト紙報道が、文字通り破壊的であった。2020年秋に判明した防衛省の情報システムへの中国による侵入が大々的に報じられたのである。
同記事によれば、中国の侵入を最初に探知したのは米国であり、深刻度が高かったことから当時のトランプ政権は、新型コロナ危機によって渡航制限が厳しかったなかでも、国家安全保障局(NSA)のポール・ナカソネ長官をはじめとする政府高官を日本に派遣した。その後、2021年春になっても日本の対応が不十分で問題の解決にいたらなかったために米国側が懸念を強め、共同での対処を提案したものの、自国の情報システムに米国が入ることへの抵抗から日本側は米国提案を退けたという。同年秋になっても日本側の対応は不十分であり、バイデン政権は再び政府高官を派遣し、さらに踏み込んで対応を求めたという経緯である。
ことの詳細はともあれ、重要な点は、防衛省の情報システムが中国の侵入を許してしまったこと自体ではない。そうした事案を事前に防ぐことができればそれに越したことはないが、その後の日本政府の対応に米国政府が懸念を強めたことこそが問題の核心である。というのも、米国においてもさまざまな情報漏洩事案は発生する。そこで問われるのは問題を解決し、いかなる再発防止策をとるかなのである。日米の間でいえば、「日本であれば適切に対応するだろう」という信頼(trustworthiness)が重要になる。これが欠けていることを浮き彫りにし、その度合いをさらに低下させたのが今回の事例だった。……
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。