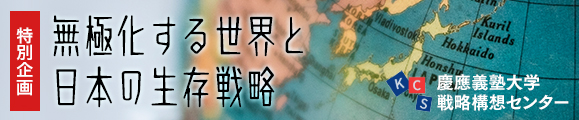ドナルド・トランプ大統領による2度目の政権が始動し、移民対策や政府機関の改革などで、さまざまな政策が猛然と打ち出されている。外交・安全保障は、国内政策に比べると優先順位が低いともいえるが、それでも、歴代政権と比べるとかなり早いペースで物事が動いている。
政権発足翌日にQuad(日米豪印)の外相会合が開催されたほか、その後は、まずイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相、そして日本の石破茂首相がホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領と首脳会談をおこなった。2月13日のNATO(北大西洋条約機構)国防相会合にはピート・ヘグセス国防長官が出席し、その週末のミュンヘン安全保障会議にはJ・D・ヴァンス副大統領が派遣された。ウクライナ停戦をめぐるロシアとの接触も活発化している。トランプ大統領とウラジーミル・プーチン大統領の電話会談に加え、サウジアラビアでは米露外相が対面で会談した。
こうした機会をつうじて、トランプ政権下の同盟の特徴がすでにかなり明確に見えてきた。端的にいって、それは「脱グローバル」と「脱価値」である。バイデン政権の路線からの決別だ。同時に、個別の政権や大統領をこえた米国の新たな方向になる可能性もあり、その意味するところは重大である。以下ではこれらを分析したうえで、日本にとっての課題を考えたい。
「脱グローバル」とは何か
「脱グローバル」が端的なかたちで示されたのは、2月7日におこなわれた日米首脳会談の首脳共同声明である。バイデン政権期は、首脳会談や外相会談などのたびに、ロシアによるウクライナ侵攻への非難やウクライナ支援へのコミットメントが表明されてきた。しかし、トランプ・石破会談の共同声明では、ウクライナはまったく言及されず、ロシアについても、北朝鮮との協力への懸念表明という文脈での1度のみだった。中東もまったく登場しなかった。日米同盟の地理的スコープはインド太平洋に完全に限定されたかのようだった。
「日米同盟が、インド太平洋及びそれを超えた地域の平和、安全及び繁栄の礎であり続けることを強調した」と冒頭で触れられた箇所が、インド太平洋以外への唯一の言及だが、「and beyond」という何とも簡易な表現であり、「超えた地域」についての具体的な話はまったく登場しない。
1970年代頃にはじまり、冷戦後により加速した日米同盟の趨勢は、同盟のグローバル化だった。これは常に米国が求め、日本が躊躇しながら徐々に応じてきたという構図だったといえる。1990年のイラクによるクウェート侵攻、それに続く1991年の湾岸戦争、2001年の9.11同時テロを受けたアフガニスタンやインド洋への関与、2003年のイラク戦争、そして2022年からのロシアによるウクライナ全面侵攻などである。いずれも、米国の求めに応じて、日本が徐々に国際政治、国際安全保障における役割を拡大してきた歴史である。「世界のなかの日米同盟」という標語が繰り返し使われた。
米国にとっては、グローバルな関与の負担が増大するなかで、同盟国にバードン・シェアリング(負担分担)を求める一環だった。アフガニスタンでは、対テロの作戦として米国主導の「不朽の自由作戦」がおこなわれると同時に、NATOが国際治安支援部隊(ISAF)を指揮することになった。これはNATOのグローバル化だった。同様の文脈で、バイデン政権は、欧州諸国によるインド太平洋地域への関与をうながし、日本によるロシア制裁やウクライナ支援の背後にも米国の強い働きかけがあった。
それが、パタっと終わったかのようなのが、トランプ政権の動きである。日本はインド太平洋で役割を果たせばよく、欧州は米国に依存しないでロシアに対処し、ウクライナを支援しろというのである。
欧州に関するこうした立場は、NATO国防相会合に出席したヘグセス国防長官の発言からも明らかだった。ヘグセスは、米国はインド太平洋地域を優先すると宣言し、欧州には欧州安保での主要な役割を求め、それぞれの地域で互いの比較優位に基づいた「役割分担(division of labor)」ができるはずだと述べたのである。これ以上の明確な表明はない。
「脱価値」とは何か
もう一つ、トランプ時代の同盟関係、あるいは、さらに広く国際関係全般において重要なのが「脱価値」である。前述の2月7日の日米首脳共同声明に、価値や人権、民主主義といった単語は一切登場しない。「自由」も、「自由で開かれたインド太平洋」の文脈で使われているのみである。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。