おなかの赤ちゃんを調べる出生前検査は今どうなっている?――検査のビジネス化の一方で厳格な規制、狭間で揺れ動く妊婦さんが悩まないために
毎日新聞取材班『出生前検査を考えたら読む本』(新潮社)

超音波検査、羊水検査、絨毛検査、クアトロテスト……初孫を迎える世代にも知られている各種をベースに、現在は望めば妊娠6週から調べることも可能なNIPT(新型出生前検査)も行われている出生前検査。
取材先の医師の一言からその実態調査を始めた取材班は、NIPTで「陽性」(染色体の重複・欠損の可能性あり)結果を受け、妊娠継続を諦めるまで悩んだものの、専門医の精査で無事に出産に至った母親に出会う。その後も各地の経験者から話を聞き、認証施設と無認証施設、カウンセラーなどへの取材も重ね、検査にまつわる最新情報を『出生前検査を考えたら読む本』(毎日新聞取材班)にまとめた。
ベストセラー『女医が教える本当に気持ちのいいセックス』の著者で、テレビ・コメンテーターとしても活躍する産婦人科医・宋美玄氏は本作を「NIPTについて知りたい人だけでなく、出生前検査や生命倫理に関心のある人にとっても必読」と評価する。それはなぜか。宋氏による書評をお届けする。
***
NIPTの陽性結果だけで中絶選択の衝撃
『出生前検査を考えたら読む本』は、日本におけるNIPT(新型出生前診断)の現状を詳しく取材し、出生前検査を取り巻く課題を多角的に論じた一冊である。本書を読むことで、日本におけるNIPTの導入がどのように進められ、なぜ現在のような状況になったのかがよく理解できる。
NIPTが日本に導入された当初、検査を実施できる医療機関や受検できる妊婦に厳格な制限が設けられた。これにより、検査を受けたいと願う多くの妊婦が制度の枠外に置かれてしまった。その結果、無認証の施設が次々と誕生し、現在ではNIPTをビジネスとして提供する医療機関が多数存在している。本書は、この問題を深く掘り下げ、認証施設と無認証施設の違いや、無認証施設で実際に行われている検査の実態を詳細に報告している。
特に衝撃的なのは、NIPTの結果が陽性だっただけで確定診断を受けずに中絶を選択してしまった例も挙げていることだ。これは、適切なカウンセリングやフォローアップが行われていないことを示しており、出生前検査が生命にかかわる重大な判断を伴うにもかかわらず、浅い知識や流れ作業で進められている現状を浮き彫りにする。対照的に、認証施設で適切な医療を受けた例も詳細に紹介されており、医療機関の対応の違いが妊婦の意思決定に大きく影響することがよく分かる。
本書は無認証施設への取材も行い、妊婦を診療してきた産婦人科医や先天疾患に詳しい臨床遺伝専門医と、無認証施設の関係性の違いを明確に描いている。無認証施設では、出生前検査に関する十分な説明や、結果に基づいた適切なフォローが不十分な場合が多く、妊婦が孤立してしまうリスクが高いことが指摘されている。
また、本書は検査項目の違いについても詳細に分析している。無認証施設では、医学的な意義が薄い項目を高額で検査しているケースがある一方で、認証施設の検査項目を拡大することも今後の課題として挙げられている。100%の精度という検査はなく、偽陽性や見落としのリスクがあること、また疾患の線引きが困難であることが丁寧に説明されている。
現在のNIPTの状況を改善するために
本書を通じて、日本におけるNIPTの特殊な状況が浮かび上がる。NIPTで調べることができる疾患は、無認証施設を含めても先天疾患のごく一部にすぎない。しかし、検査がビジネス化されることで妊婦が適切な情報を得られず、誤った判断を下してしまうリスクが高まる一方で、認証施設による厳格な規制がかえって妊婦の選択肢を狭めるという矛盾も生じている。パターナリズム的な規制も、完全に自由化されることも、それぞれに問題をはらんでいる。
現在のNIPTの状況を改善するためには、妊婦の知る権利を尊重しつつ、医療機関同士が円滑に連携し、どこで検査を受けても適切なフォローが受けられる体制の整備が急務である。超音波検査を含め、出生前診断のあり方を見直し、妊婦が適切な情報と支援を得た上で納得のいく選択ができる環境を整える必要がある。
本書は、NIPTについて知りたい人だけでなく、出生前検査や生命倫理に関心のある人にとっても必読の一冊である。科学技術の進歩に対して、拒絶的な姿勢を取ると歪な体制となってしまう。どのように受け入れていくか、倫理面も含めて考えさせられる内容であり、出生前検査の今後の在り方について議論を深めるきっかけを提供してくれる。
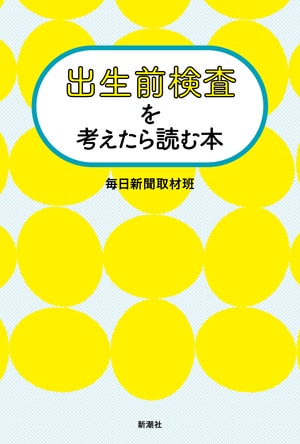
- ◎宋美玄(そん・みひょん)
1976年兵庫県生まれ。大阪大学医学部卒、産婦人科医。一般社団法人ウィメンズヘルスリテラシー協会代表理事、一般社団法人日本ガスケアプローチ協会代表理事、丸の内の森レディースクリニック院長。2児の母として子育てと産婦人科医を両立、メディア等への積極的露出で“カリスマ産婦人科医”として様々な女性の悩み、セックスや女性の性、妊娠などについて女性の立場からの積極的な啓蒙活動を行っている。







































