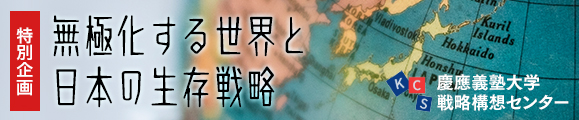「危機の三十年」を超えて――混乱と対立の時代における戦略的思考

2025年1月20日の第二次トランプ政権の成立は、国際社会に大きな衝撃を与えることになった。ドナルド・トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」のイデオロギー、そしてその政策は、それまでのアメリカの対外政策とは大きく異なる様相を示している。同時に、それ以前の政権から持続する長期的な潮流も存在する。たとえば、2009年1月のバラク・オバマ政権の成立以後、民主党と共和党を問わずいずれの政権においても、アメリカの対外軍事関与を縮小する動きが見られる。2013年9月に、オバマ大統領は、「アメリカはもはや世界の警察官ではない」と語り、従来のような対外関与が自明ではないことを宣言した。いわばアメリカの世界への軍事関与の縮小の意向表明は、第二次トランプ政権の新しい動向というよりも、長期的なアメリカ政治に見られる趨勢と言うべきであろう。
このようにして、トランプ大統領による衝動的な言動に振り回されることなく、その背後に見られる巨大な国際政治の構造的な変化にも目を向ける必要がある。すなわち、現在見られる変化を、より大きな時間軸の中に位置づけることで、われわれが直面する危機の性質をより的確に理解できるのではないか。
ここでは、そのような俯瞰的な視座から、冷戦終結後の30年間を「危機の三十年」と位置づけ、そこに現在の多くの国際的な不安定性の根源があることを指摘したい。それでは、「危機の三十年」とはどのような時代であったのだろうか。
「危機の三十年」としてのポスト冷戦時代
ここで用いる「危機の三十年」という表現は、かつてイギリスの歴史家であり国際政治学者であるE.H.カーが用いた「危機の二十年」という表現を参考にしている。カーは、第一次世界大戦後の世界が、パワー・ポリティクスという現実を無視して過度にユートピアニズムに傾斜したことを、その後の不安定性の源泉として批判した。すなわち、それぞれの大国の利益が「レッセフェール」において調和し、人間の理性にもとづいた行動が平和を持続させるという楽観的な時代精神が浸透していた。だが、不幸にして、それによって軍事的な危機への対応を怠ることになった。
カーからすれば、平和を維持するためにはパワーの論理の理解が不可欠であった。イギリスやフランスのようなこの時代における大国が十分な軍事力を背景に、積極的な外交を展開することが必要であった。そのような認識の欠落が、結果として国際的危機をもたらしたのである。
冷戦終結後の国際社会においても同様に、日本やヨーロッパでは国際政治におけるパワーの重要性を軽視して、中国やロシアといった軍事大国の台頭と、それに伴うパワーバランスの変化を看過する傾向が見られた。中国やロシアは自らの勢力圏を確立するためにも、軍事力の増強や軍事技術のイノベーションを進め、そのような動向にドイツのようなヨーロッパ諸国、そして日本は、適切に対応することを怠ってきた。外交による協調関係の構築や、経済的な相互依存にもとづいた平和を、楽観視していたのだ。そして現在、そのような楽観が裏切られたことが、大きな危機を招いている。
それだけではない。「危機の三十年」の時代においては、次のような三つの要素が自明のこととして、国際秩序の根幹に埋め込まれているものと想定していた。それらが大きく後退することで、国際秩序もまた不安定化しているといえるのではないか。
三つのユートピア思想とその衰退
1991年12月のソ連崩壊から、2021年12月のロシア軍による本格的なウクライナ侵攻準備の進行に至るまでの30年間、次のような三つのユートピア主義的な思想が世界全体に広がることと想定されていた。だがそれらは次第に、30年の年月を経過して、大きく衰退するに至っている。
第一には、
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。