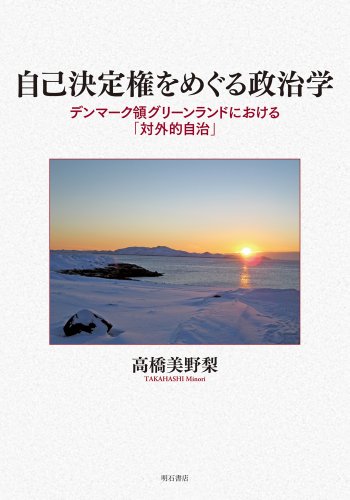19世紀以降の米国は、政治的かつ商業的な観点からグリーンランドの購入を画策し続けており、この点においてトランプの主張は決して異例ではない[グリーンランドを“プライベート”で訪問するドナルド・トランプJr.を乗せた航空機=2025年1月7日、グリーンランド・ヌーク空港](C)EPA=時事
はじめに
2024年12月、大統領就任を目前に控えたドナルド・トランプは、デンマーク領グリーンランドの「所有と管理」の重要性を改めて強調した。2019年に続く2度目の表明だった。デンマークは、自治領グリーンランドが、自国の主権とアメリカの勢力圏との狭間にあるという現実をふたたび突きつけられることとなった。特に、「デンマークは米国の決定に従うだろう(come along)」というトランプの発言は、その真意をめぐる疑念を呼び起こした(DR 2025)。これは単なる挑発的なレトリックではなく、デンマーク政治の中枢ではここ数年で最も深刻な外交危機と受け止められており、その影響は長期化すると予想されている。今、デンマークは自国の足元――すなわちグリーンランドとの関係――をいかに(再)定位するのかという重大な岐路に立たされている。
例外として外国軍駐留を強いられた島
デンマークとグリーンランドの関係は、古くは11世紀半ば頃まで遡れる。12~13世紀に接触の機会は高まるが、15世紀初頭には文字記録が途絶えてしまう。記述史料が急速に積み上げられていくのは、グリーンランドがデンマーク(デンマーク=ノルウェー同君連合)の植民地になった1721年以降である。その後200年以上にわたる統治を経て、1953年にはデンマークの一地方となった。1960年代以降、デンマークのEC(欧州共同体)加盟交渉を契機に、グリーンランドはデンマーク国家の一員としての義務を果たしつつ、自らの存在を示し、カウンターパートと直接対話する必要性――自治――を強く意識するようになった。デンマークとの交渉を経て、1979年には内政自治法が施行され、2009年の改正以降は、公選された31名の議員からなる自治議会と、選出された数名の大臣によって構成される自治政府を中心に、外交・安全保障領域等に対する最終決定権を除く全分野が自治法の下に置かれた。同法には独立交渉を開始することができる「独立条項」も明記された。
こうした自治権獲得過程の実質を理解する上で留意しておきたいのは、その自治が、国内の区画全域にわたって最高権力を行使する中央政府=デンマークとの「中心―周辺」関係の解消を前提としていなかった点である。上述の「独立条項」も、独立への直線的な道筋を示すものではなく、むしろデンマークとの交渉を通じて将来的な関係を構築するためのツールとしての性格が強かった。少なくとも2010年代前半までのグリーンランドは、時代による多少の変動は見られたものの、大勢は分離を志向せず、デンマーク国家の枠組みの中で対外的な発言権を獲得するという論理を貫いてきた。
その一方で戦後グリーンランドは、デンマークの国家安全保障政策の例外的な存在としても機能してきた。米国とデンマークの二者間協定である1951年防衛協定の下、デンマーク本土では回避された平時の外国軍の駐留や核兵器の配置が、グリーンランドでは認められた。2004年の修正補足協定(=イガリク協定という複合協定を構成する協定)以降、グリーンランドも協定締約主体となり、上記二者を含む三者の協議体が恒常化されるなど画期的な動きも見られた。しかし、高度な自治が与えられながらも、例外として国家安全保障の中核的かつ広範な役割を担うという構造自体は連綿と続いており、イガリク協定以降もその本質的な変化は見られなかった。グリーンランドの包摂と排除の歴史は、戦後デンマーク国家の形成とその歩みを強力に支えてきた。
指摘されてきた「不公平に対する自己正当化」
にもかかわらず、グリーンランドがデンマークにおいて(すら)「見える」存在とはなり得ていない現実は、これまでもしばしば指摘されてきた。たとえば、「デンマーク(人)はリベラルな価値観を擁護する国の一員として振る舞う一方で――この点は政府のブランディング戦略とも密接な係わりを持っている(Wivel 2018)――、歴史への視点を欠き、グリーンランド(人)との関係に潜む不平等に対して無頓着である」という態度、あるいは「そうした事実に気付いたとしても、最善の意図、すなわち、自らが良い目的に基づいて行動しているという認識をもってグリーンランドに接してきた」という自己認識――こうした態度や自己認識が、構造の是正を妨げてきた、という声が俎上に載せられてきた。グリーンランド選出の議員アキ・マチルダ・フー=ダムは、この状況を「認知的不協和」と呼んだ(The Guardian 2024)。公平な国の一員であろうとする意識と、実際には対等な関係になろうとすることを軽視している現実とのギャップを、自己正当化によって解消するデンマークに焦点をあてたのである。今回のトランプの発言が、デンマークの文脈で解釈されるとき、照射されたのはまさにこの点だった。
紙幅の都合で深く立ち入れないが、背景の一つには歴史教育がある。私はデンマークで義務教育を受けたが、歴史の授業でグリーンランドとの関係が深く扱われた記憶はほとんどない。グリーンランドについて言及されることはあったものの、それは脚注や囲み記事の形で取り上げられる程度で、歴史の周縁どころか、そのさらに外側に位置づけられてきた。教育に起因する無知や無理解が、グリーンランドに対する認識の深化を阻んできた。両者の関係史がデンマークの義務教育課程で必修化されたのは、2023/2024学年度からである。2025-2028年度には、グリーンランド(人)に対する差別是正を目的とした国策プログラムへの予算措置も講じられている。
「去るものは追わず」と「国家への包摂」
トランプ発言以降、デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は、グリーンランドの人々の意志を尊重する姿勢を一貫して示してきた。ここでいう「意志」とは、2009年自治法第21条「独立条項」をふまえつつ、グリーンランドの人々が自らの進む道を決定することを指している。同条1項には、グリーンランドの独立に関する決定はグリーンランドの人々によってなされるべきであると明記されている。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。