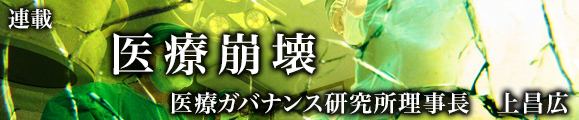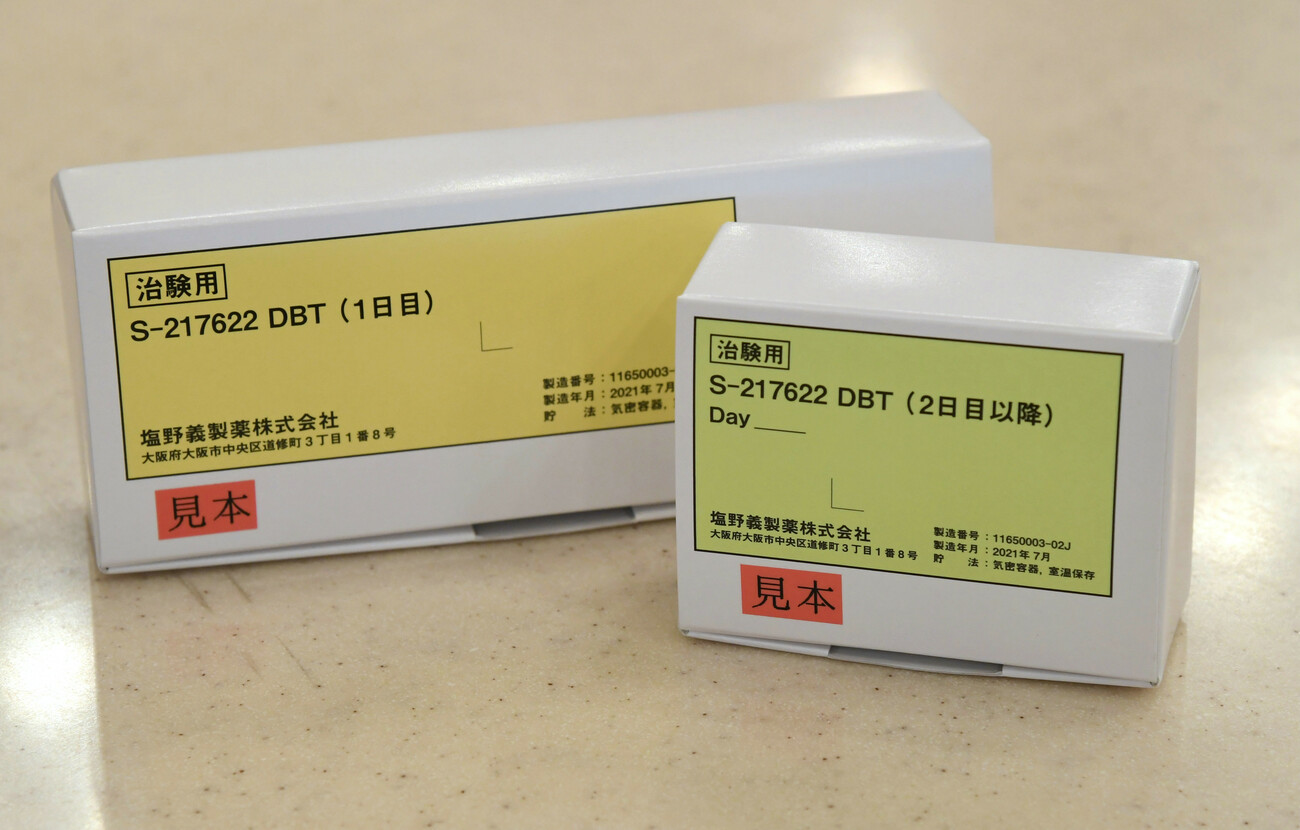
5月12日、日本製薬工業協会(製薬協)が日本経済新聞朝刊に見開き2面を使った全面広告を出した。3月に開催された「第33回製薬協政策セミナー」の紹介だった。「日本発の新薬が花開く未来へ 産学官によるヘルスケアエコシステム加速を」というタイトルで、甘利明・自民党経済安全保障対策本部座長、佐伯耕三・経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課長、岡田安史・製薬協会長ら9人が登壇した。
この広告をみて、私は強い違和感を抱いた。
確かに、我が国の製薬業界が置かれた状況は深刻だ。特記すべきは、日本の製薬市場が縮小を続けていることだ。2020年の国内医療用医薬品の市場規模は、前年比2.7%減の10兆3475億円で、2015年と比べて9.0%の減少だった。こんな先進国はない。英調査会社エバリュエートファーマ社によると、同時期に世界の医療用医薬品市場は33%の成長を遂げている。
だが、医薬品市場が縮小しているのは、薬価を政府が統制しているからだ。
高齢化よる社会保障費が増大する我が国で、医療費の削減は喫緊の課題だ。医療費は薬剤費と医師の診療に対する診療報酬に大別されるが、医療費の総額を抑制すれば、製薬業界と医療界のゼロサムゲームとなる。日本医師会をはじめ、政治力が強い医療界に軍配が上がり、このような顛末となっている。
この傾向は、第二次安倍晋三政権以降、顕著だ。意外かもしれないが、民主党政権の影響が強い2009~15年には医療用医薬品市場は22%成長し、世界平均(16%)を上回っていた。製薬協が岸田文雄政権にすり寄っても、結果は見えている。
モデルナはmRNAワクチンだけで世界的大企業に
これで製薬業界は成長するはずがない。その弊害は、すでに国民にも及んでいる。
米国研究製薬工業協会(PhRMA)によれば、2010年代前半、世界で承認された薬剤の51%が日本でも承認されていたが、後半には43%に低下している。ちなみに米国は84%だ。このことが社会で問題視されることは少ないが、実は日本国民は、米国民の半分の新薬しか使うことができないという深刻なドラッグラグに直面している。
なぜ、こうなるのか。それは日本が製薬企業にとって魅力的な市場ではなくなっているからだ。製薬企業が新薬を販売するには、各国の規制当局の承認を得なければならない。日本も厚労省が日本での治験を求める。一刻も早く治験を終了し、新薬を販売したい製薬企業は、治験のハードルが低い国や、今後、大きな売り上げが期待できる国での治験を優先する。いまや日本はいずれでもない。
製薬業は「薬九層倍」と呼ばれ、新薬開発に成功すれば一攫千金が期待できる。2022年版製薬企業世界売上高ランキングでは、米モデルナが184.7億ドルを売り上げ、19位にランクインした。日本でモデルナより上位に位置するのは武田薬品工業(321.2億ドル、11位)だけだ。モデルナの躍進はmRNAワクチンのお陰だが、これは同社が開発・販売した初めての医薬品だ。たった一つ医薬品開発に成功しただけで、世界的大企業へと成長した。
ただ、創薬は難しい。高度に専門的な領域で、世界的大企業でも失敗する。mRNAワクチンへの対応など、その典型だ。
モデルナ、そして米ファイザーは、mRNAワクチンの開発で巨万の富を得た一方、米メルクは目利きを誤った。同社は、当時ボストンのバイオベンチャーに過ぎなかったモデルナと、2015年1月にウイルス疾患治療、16年6月にがん治療のためのmRNAワクチンの共同開発契約を締結し、さらに資本提携も結んでいたが、コロナワクチン開発には乗り出さず、2020年12月には保有モデルナ株を売却したことを発表している。
同社の関係者は「mRNAワクチンが、こんなに成功するとは思わなかった」という。メルクのようなメガファーマでこうなのだから、メルクと比べれば「素人」に過ぎない我が国の産学官が連携して創薬を推進するなど、机上の空論だ。
「安全保障」が政府頼みの方便にも
そもそも、世界レベルの製薬企業は官に頼らない。
ファイザーのアルバート・ブーラCEO(最高経営責任者)の発言が興味深い。彼は、2021年5ー7月号の『ハーバード・ビジネス・レビュー』のインタビューで、「いつものように最も有望なものを順番にテストするのではなく、いくつかのワクチン候補に並行して取り組むことにしました。これは経済的にリスクがありましたが、より迅速に結果をだすことができます。また、研究者を官僚主義から解放し、不必要な干渉から研究者を保護するために、政府の資金提供を拒否しました」と答えている。
ブーラCEOは、この賭けに勝った。同社は2021年には812.9億ドルを売り上げ、2位のロシュ(687.0億ドル)を大きく引き離して、断トツのトップに返り咲いた。
このあたり、安全保障を錦の御旗に、国産医薬品の開発推進を政府に頼る日本の製薬企業とは対照的だ。5月13日に成立した改正医薬品医療機器法(薬機法)では、医薬品の迅速な実用化を可能とする「緊急承認制度」が盛り込まれた。この制度により、安全性を確認した上で有効性を推定できるデータが集まれば、治験の途中でも前倒しで薬事承認できるが、最初の対象と考えられているのは、塩野義製薬のコロナ治療薬だ。国内で実施した69人の感染者を対象とした臨床試験では、「ウイルス力価の陽性患者割合」は減少したものの、重症化や死亡の減少は確認されていない。欧米では承認されないレベルだ。
塩野義製治療薬は、「緊急承認制度」の初適用事例として承認されるだろう。そして、安全保障の観点から、政府が買い上げ、備蓄に回るだろう。製薬協も、そのような動きを歓迎している。だからこそ、製薬協政策セミナーに甘利氏、佐伯氏を招聘したのだろう。
甘利氏は、慶應義塾大学法学部政治学科卒、父で衆議院議員だった甘利正の秘書を経て、衆院議員となる。佐伯氏は東大法学部から通産省(現経産省)に入省したキャリア官僚で、安倍首相秘書官時代にアベノマスクで失態を演じた。二人とも医薬品開発の素人だ。
日本の製薬業界の問題は、このセミナーの人選に象徴されている。
創薬は薬学・医学・獣医学・生物統計学など多様な専門家の協同作業だ。成功の秘訣は、如何にして多様な人材の協同作業を可能にするかにある。
世界の製薬企業は、多様な人材を確保するために努力を続けてきた。米ファイザーのブーラ社長は、ホロコーストの生き残りであるユダヤ系ギリシャ人を両親に持つ、ギリシャ採用の獣医だし、日本の製薬企業で最もグローバル化が進んでいる武田薬品のクリストフ・ウェバー社長は、フランス生まれで、リヨン第一大学で薬学博士を取得後、英スミスクライン・ビーチャム(現グラクソ・スミスクライン)に入社した人物だ。
このような人材でなければ、国際共同治験は遂行できない。ファイザーがイスラエルでコロナワクチンの臨床開発を進めたのは、ブーラ社長の経歴に負うところが大きいだろう。ファイザーの株主も、このような事態を想定してブーラ氏を抜擢した訳ではないだろうが、多様な人材を揃えたことが、コロナパンデミックのような危機に際し、臨機応変な対応を可能にしたのは間違いない。
在野の専門家の努力こそが重要
これこそ、我々が学ぶべき点だ。ただ残念ながら、それには時間がかかる。
セミナーに登壇した岡田安史製薬協会長は、関西学院大学を卒業後、エーザイに入社した生え抜きだし、7人の副会長は、全員が東京大学など国内の有名大学を卒業後、それぞれの企業に入社したエリート男性社員ばかりだ。極めて同質な集団だ。知人の外資系製薬企業幹部は、「生え抜きのおじさんたちがトップを務めている限り、日本の製薬企業は成長しない」という。
勿論、このことは日本の製薬企業関係者も理解している。だからこそ、決して少なくはない数の企業がグローバル化を推し進め、多様な人材確保に力を注いでいる。おそらく、製薬企業の社内では「第33回製薬協政策セミナー」に象徴される「お上頼み」勢力と、グローバルグループが激しい議論をしているのだろう。このような課程を地道に積み重ねることでしか、日本の復活はない。
改めて確認すべきは、いまの日本に必要なのは、政府による改革ではないということだ。在野の専門家の努力こそが重要だ。コロナパンデミックを収束させた原動力は、ファイザーやモデルナのワクチン、遠隔診療や検査(センシングを含む)を可能にしたIT企業だ。多くの人材と豊富な資金力を備えた民間企業が主導した技術的ブレイクスルーが、新しい時代を切り拓いた。
これは、コロナパンデミックに限った話ではない。そもそも、19世紀に英国ビクトリア朝時代に始まった公衆衛生政策を、実質的に担ったのは、水道整備を推し進めた資本家階級だ。民間主導で課題が解決されているのは、いまも昔も変わらない。
残念ながら、19世紀の日本には資本の蓄積は薄かった。海外から流入するコレラなどの対策を担ったのは、内務省衛生局(「衛生警察」と呼ばれた)で、彼らは感染者や家族、近隣の住民を強制隔離した。日本のコロナ対策が政府主導の隔離で、元厚労官僚である尾身茂氏を専門家のトップとして崇めるあたり、構図は明治時代と変わらない。かつて、マッカーサーは権力・権威への依存心が強い日本人のメンタリティを「日本人は12歳」と評した。我々は、そろそろ「小学校」を卒業すべきである。