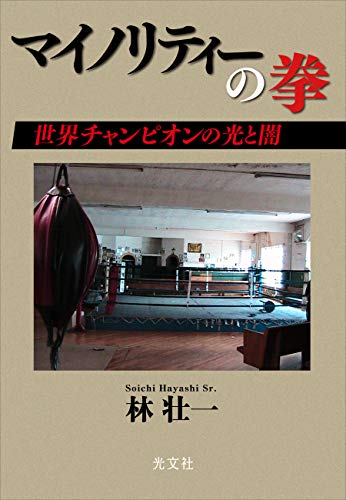ロシアによるウクライナ侵攻が始まった直後、神奈川県横浜市に本社を構えるJBC株式会社の代表取締役、加藤伸彦(71)は、1カ月前に閉鎖したばかりの同社ドネツク事務所の元現地スタッフから送られてきた写真を目にして息を呑んだ。事務所前の道路に、遺体が山積みとなっていたのだ。
加藤は1993年に商社を辞めJBCを立ち上げた。医療機器及び産業機器用(防衛産業向けのミルスペック含む)の半導体を主力商品とする仕入れ販売事業を営み、その他に電子機器、アパレル製品、生活雑貨品の輸出入や、車両の修理販売なども手掛けている。
たまたま縁あってウクライナ人男性を採用
社員数20名の小さな企業が、なぜウクライナのドネツクに事務所を開設するに至ったのか。加藤は自身の足跡を振り返る。
「独立前に勤めていたのも、半導体専門の商社でした。そこを辞めたのは、社長との意見の食い違いでした。正直なところ、喧嘩して辞めたようなものです。家内は『1カ月くらいゆっくりしたら』と言ってくれたし、何の準備もしていなかったのですが、取引先の一つだった旧横河ナビテック(現YDKテクノロジーズ)さんのある方に『これからもこの業界でがんばるように』と、口座を開いて頂きましてね。独立するなら直ぐに社名が必要ということで、Jは『じゃあ』、Bは『僕に』、Cは『(注文を)ちょうだい』でJBCとしました(笑)。まずはレンタルオフィスを借り、一人で営業回りを始めたんです」
柔らかな物腰で社名の由来を話す様に、どこか凄みを感じさせる。
「商社時代のビジネスパートナーだったニューヨークの取引先から半導体を仕入れて旧横河ナビテックさんに売り、あとは飛び込み営業でお客さんを獲得していきました」
やがて、半導体産業の仕入れ先として勢いがあった中国や、ロシアとも取引するようになる。
「仕入れて卸すビジネスですから、技術者はおらず、営業のみでした。この業界は、1998年頃からインターネットで世界各地の在庫状況を調べられるようになったんです。中国企業は半導体のストックをふんだんに持っているので、開拓しようと。特に深圳には小さな商社が無数にありました。私も現地に3度足を運びましたし、JBCの社員を重慶や香港に派遣して、ビジネスを広げていきました」
経営が軌道に乗り、事業の拡大を考えていた2005年、船舶関係の仕事に就いていた4歳年上の幼馴染が転職先を探していると聞き、JBCに社員として迎え入れる。その幼馴染は、たまたま日本とウクライナの友好団体に人脈を持っており、ちょうど同団体が解散するということで、メンバーの一人だったウクライナ人男性も一緒に加藤の社で採用することとした。
「彼は名をスラバと言いました。今64歳かな。ウクライナはヨーロッパや中東、ロシア、中央アジアの中継地点に位置していて、将来的にヨーロッパで事業を展開する足掛かりになるのではないかと思い、事務所を開設できないかと考えたのです。日本から海外に渡ろうとすると時間もお金も掛かりますが、ウクライナからはバスで色々な国に行ける。
ウクライナでのビジネスの可能性を模索するために、採用した幼馴染と一緒にスラバを現地に派遣しました。うちの社員はみんな英語しかできないのですが、ウクライナでは、英語はあんまり通じなかったですね。その点、スラバは英語だけでなくロシア語やウクライナ語も含め6カ国語くらい話せました。最終的にスラバの出身地のドネツクに支店を出したのが、2007年のことです」
日本製なら何でも需要があった
ドネツクでは、着物をはじめとする日本製の衣類や化粧品をウクライナ人に売る商売を展開した。
「ユーラシア大陸での拠点づくりとして進出を決めたものの、現地でどんなニーズがあるのか分からず、扱う商材についてはスラバに任せました。結果的にウクライナで半導体は扱っていません。向こうではMade in Japanに価値があるんです。
特に工芸品や美術品のニーズが高く、着物や浴衣、扇子、根付などを欲しがる方が沢山います。100円ショップの商品も人気がありましたね。理由は安くて質が良いからです。『実際は中国製だよ』と言っても、『アイデアやデザイン案は日本なんだろう』と意に介さず、常に需要がありました。ウクライナから買う物は無く、売るだけでしたね。支払いに関しても個人相手の現金商売ですから、ビジネスをする上では基本的にトラブルはありませんでした」
しかしながら加藤は、同国でショックを受けたこともあった。
「私が初めてウクライナを訪れた2005年、ドネツク空港できちんと手荷物検査をパスして入国したというのに、空港を出た途端にガードマンに止められてバッグを調べられ、難癖をつけて1ドルを要求されました。それは個人的に欲しいからなんです。たった1ドルをせびってくるんですよ。驚きましたね。
スラバいわく、元KGBのスパイだった人が、ソ連が崩壊して職にあぶれて民間のガードマンになったりしている。そういう人は、ロシアから流れてきたタイプが多かったようです」
それでも加藤は、事務所開設以来、毎年ドネツクを訪れていた。が、2017年から叶わなくなる。今回のウラジーミル・プーチンによる全面侵攻も、ある程度予期していたという。
「2014年のロシアによるクリミア侵攻を機にドンバス地方で紛争が始まり、当地の住民であるウクライナ人のスラバでさえ、ドネツクから出るのにビザが必要となりました。2021年末には、スラバの乗ったバスの目の前に爆弾が落ちましたし、弊社のドネツク事務所の壁が砲弾で傷付いたこともあったんです。安全にビジネスができる環境ではなくなっていき、正式に事務所を閉めたのはロシアによる侵攻直前の2022年1月です」
コロナ禍の半導体不足で伸びた売上を寄付に
そして、不穏な予感が現実のものとなった2022年2月、冒頭で記した事務所前に積まれた死体の山の写真を、加藤はスラバからのメールで見ることとなる。
「それを見て、ウクライナを守らなければいけないと思いました。私にできることをやろうと」
以来JBCは、複数のNGOを通じてウクライナへの人道支援を続けている。その一つであるキリスト教系NGO団体のADRA(Adventist Development and Relief Agency)が、ウクライナに開放骨折創、熱傷創、植皮術の被覆、壊死性筋膜炎の応用治療に用いるVAC装置や、衣類、防寒具、毛布、ブルーシート、食料、飲料水等を配布したことを知った加藤は、同団体に500万円を寄付した。
「私自身は無宗教ですが、母親がクリスチャンだったんですよ。母の兄も牧師だったので、子どもの頃から日曜学校に通ったりしていました。そのせいか、寄付には抵抗が無いんです」
とはいえ、社員数20名の同社が数百万円をポンと出せた背景には、昨今の半導体市場の活況がある。コロナ禍において多くの国で不要不急の外出が禁じられ、在宅での仕事が増えたことにより、人々がパソコンやスマホを使う頻度が増した。需要が増えたのに対し、供給は逼迫したため、世界中で半導体の取り合いが起きた。
「この業界で、コロナ禍で売り上げが上がったところは、大手よりもうちのような零細企業が多いと思います。なぜかと言えば、大手は通常の仕入れルートが決まっているんです。メーカーさんから直とかね。逆に弊社のようなところは、小さなルートが沢山あるんですよ。
例年、弊社の年商はだいたい6億円くらいでした。会社の規模と利益率からするとそれくらいで御の字なんです。それが、昨年は驚くほどの売上高を得ることができました。とはいえ弊社もビジネスですから、先のことは分かりません。でも、できるうちは人道支援を続けたいと考えています」
あるウクライナ人女性の半生
戦火が続くウクライナで、スラバとの連絡は途切れ途切れとなり、ここ数週間はほとんど音信不通となっている。できればスラバに取材したいと考えていた筆者だが、それは叶わないことが分かった。そこで加藤が紹介してくれたのが、キーウに住むガイヤネという54歳の女性である。加藤と彼女は、スラバの紹介で2010年末に知り合った。
当時、ガイヤネはスパを運営する会社に勤務しており、加藤はサウナ施設で使えるマイクロバブル風呂をウクライナで売ることを考えていた。
「結局その商談は成立しませんでしたが付き合いは続き、ガイヤネが親戚と一緒に日本に来た時に接待したんです。弊社社員がウクライナのキーウに行った時は、街をガイドしてくれました。現在は友達として、ウクライナ支援の仲介役をしてもらっています」
ガイヤネはどんな人物で、現在のウクライナ情勢についてどう考えているのか。加藤からガイヤネの連絡先を聞いた筆者は、まず彼女の半生について質した。
「私は1969年1月にキーウで生まれました。父はアルメニア人、母はウクライナ人です。父は若い頃、ウクライナ西部の国境で国境警備部隊に所属していました。当時はアルメニアもウクライナもソ連というひとつの国家でした。父は兵役の後、キーウ航空大学に入学し、在学中に母と出会って結婚。やがて私が生まれたのです。
父は航空エンジニアとして働く傍ら、週末はツアーガイドとしてキーウ近郊で小旅行を企画していました。ツアーガイドは歴史好きだった父にとって、知識を深められ、かつ家族のためにプラスアルファのお金を稼ぐチャンスでもありました。私が学生だった頃、父が私のクラスでツアーを行ったことを覚えています。以来、私もキーウの歴史に興味を持つようになりました。
母はウクライナ科学アカデミーの研究所で設計技師として働いていました。今、父は85歳で、母は80歳の年金生活者です。裕福な家庭ではなかった。ソ連では、エンジニアの賃金は一般の労働者よりもずっと低かったんです。でも、両親は私と妹に可能な限り良い教育を与えようとしてくれました。私たちは音楽学校に通い、高価な本も買ってもらいました。両親は私たちのピアノを買うために借金もしました。頻繁に劇場や美術館にも連れて行ってくれました。私たちを教養人に育てたかったんです。
そして両親は、すべての民族は友であるべきだと私たちに説きました。ですから、私たちの家族の周囲には、いつも異なる国籍の友人がいました」
ロシア人の友人たちは真実を知ろうとしなかった
ガイヤネの話は続く。
「父の両親はジョージアのトビリシに住んでいました。毎年、休日は家族でジョージアの祖父母を訪ね、近所に住むアルメニア人、ジョージア人、クルド人の子どもたちと仲良くなって遊びました。祖父母は1916年に、トルコ人によるアルメニア人大虐殺から逃れるため、アルメニアを離れてジョージアに移住したんです。そんな背景がありますから、両親は、戦争とはこの世にあってはならない悪だと言い聞かせて私たちを育てました。私の父と母も1941年から1945年の第二次世界大戦を経験しています。私が物心ついた時から、両親はいつも『戦争さえなければ』と言っていました。
私は子供の頃、外国を旅するのが夢でした。ソ連時代は、親が外交官でない限り、他国を訪れることは不可能だったんです。でも、私は沢山の本を読み、外の世界を覗いてみたかった。ウクライナが独立した折、ついに私は海外旅行の夢をかなえる機会を得ました。その頃の私は自分の天職を探していました。最終的に工科大学、医科大学、美容学コース、建築デザイン学校を卒業しています。そこで学んだ知識は、自分の人生に役立ちました。
加藤さんとの出会いは、ウクライナ全土にスパ施設を設計・建設する会社で働いていた時です。エステサロン用にJBCを通じて日本の化粧品を買ったんです。私は様々な国の癒しや美の文化に関心がありました。銭湯や温泉がどのように配置されているのか知りたかったし、日本の建築物にも興味を持っていました。加藤さんはそんな私を親切にも日本に招待してくれ、あちこちの銭湯や温泉を見せてくれたんですよ。私にとって日本は、独自の伝統と文化を持つ美しい神秘的な国でした。加藤さんは、私の夢を叶えてくれたのです」
もともとウクライナでは、日常生活でロシア語を話す国民が多かった。そして、エリートとされるタイプはモスクワの大学に進学していたそうだ。ガイヤネの家族は今もロシア語でコミュニケーションをとっている。
「私は学生時代からロシア文学が好きでした。16歳の時、ロシア文学オリンピックに出場し、キーウで2位になりました。ただ、学校ではウクライナ語も勉強していましたから、ウクライナ語でもロシア語でも読み書きする上で違いはありません。私はいつも多くの友人に囲まれており、ロシア人の友もいましたね。2014年までは政治にほとんど興味がなく、ロシアの人々を友人だと思っていたんです。親ロシア派と、親欧米派であるウクライナ政府が対立して紛争が始まった時、私は“何が起きているのか”を理解し始めましたが、それを信じたくはなかった。
でも2022年2月24日、私の人生は大きく変わり、目を開くことになりました。モスクワやカザン出身のかつての友人たちは、私がどうしているか、家族はどうしているかを訊ねようともしなかった。彼らは真実を知ろうとしませんでした。それが衝撃的でした。モスクワに住む幼馴染は、『キーウが爆撃されている』という私のメッセージに、『そんなはずはない』と返信してきました。彼女とはそれっきりです。私の心は深く傷付きました。
でも、世界中の国の人たちが応援の言葉をくれました。加藤さんもその一人です」
今、日本に対して望むこと
加藤はNGOに寄付するだけでなく、自らも物資や募金を現地に送っている。先日は、着の身着のままの状態に置かれているウクライナの人々へと、100枚のポロシャツを贈呈した。国旗と同色の黄色とブルーの生地の背に、『ウクライナに栄光あれ』という言葉をウクライナ語で入れたオリジナルシャツだ。「キーウで困っている人に配ってほしい」とのメッセージを添えた。ロシア支配下のドネツクには物資が届かないため、受取人はキーウのガイヤネだった。
彼女は日本からの支援についてどう思っているのか。
「日本政府やNGOはウクライナから日本へ避難した人をサポートし、私の母国に多くの財政的・人道的援助をして下さっていますね。日本が対ロシア制裁を支持していることも知っています。ありがたいです」
最後に、今後日本に対して望むことを訊ねた。
「残念ながら、戦争は続いています。毎日ウクライナ人が命を落とし、誰かの家が破壊されています。ロシアによってヘルソン地方のカホフカ水力発電所も爆破されました。もし、ウクライナ軍が十分な武器や飛行機、ミサイルを持っていたら、戦いはもっと成功しているはずです。何千人もの命を救うことができるとも思います。
どうかウクライナのことを忘れないでください。私たちは、善意の人々の支援を強く望んでいます。テロ国家であるロシアを止めるには、共に戦うしかないのです。ロシア政府は、偽善的で、冷酷で、犯罪的行為を止めません。ロシアの暴挙を止めることができるのは、強い精神と他の国の助けだけなのです」
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の発表によると、ロシアによる武力行使が始まった2022年2月24日から今年4月9日までの約1年間だけで、ウクライナ人の死者は8490名、負傷者は1万4244名に上る。
ウクライナの人々は、加藤が送ったポロシャツにどんな思いで袖を通すのだろうか。JBCでは、日本製が大好きな現地の人々を思い、『ウクライナに栄光あれ』の文字が躍る大漁旗も送った。そして、寒くなるのが早いウクライナの気候を考慮し、すでに防寒着の作成にも着手している。