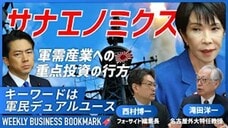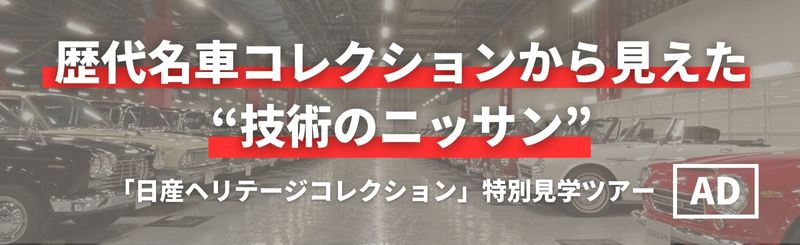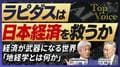先端半導体をめぐる攻防は米中対決の激烈な主戦場だが、バイデン米政権が模索する対中国規制の第2弾がなかなか具体化しない。
昨年10月7日の包括的な規制(昨年12月の杉田のフォーサイト記事参照)は、台湾、日本、オランダ、韓国など半導体先進国・地域を巻き込んで中国に最先端半導体を入手させないという荒っぽい規制だった。中国のダメージは大きい。これに味を占めた米国はその第2弾でさらなる手法で中国を孤立させる策を練る。7月初旬にも発表されると報じられ、世界の半導体産業を身構えさせた。だが、米国内外の抵抗や中国の報復があり、バイデン政権の思惑通りに事態は動いていない。規制強化や補助金のテコ入れといった、アニマルスピリッツを奪う国家政策は、長期的には米国を弱体化させる恐れがある。
米国が狙う3つの新規制
バイデン政権が模索する新たな対中半導体規制はどんな内容だろうか。
米メディア報道では3分野に分かれるようだ。
まずは中国への半導体輸出のハードルをさらに上げる。昨年10月の規制は、最先端半導体だけでなく、その設計、ソフトウエア、部品、製造装置、そして関連する知的財産まで含めて中国への輸出を原則認めず、さらにFDPR(外国直接製品ルール)という制度を発動して、日本など同盟国も米国産の部品、技術、設計を使ったものは中国に輸出できない、と縛った。
FDPRは超大国の米国の覇権の象徴のような域外適用制度である。また中国の半導体産業で米国人や永住権者が就労することも禁止し、多くの米国人が帰国した。
半導体専門家は「米国の技術や設計を使わない先端半導体など世界に存在しない。中国向けのあらゆる輸出が止まる」と言うが、新規制は対象となる半導体をさらに広げる。
生成AI(人工知能)ブームに乗り半導体業界で初の時価総額1兆ドルを記録したエヌビディアの場合、AI半導体であるA100、H100の輸出が禁じられたが、その性能を少し下回るA800、H800という新たなシリーズの半導体をつくることで中国輸出を続けた。米政権はこうした抜け穴を封じるため禁止対象を広げる。
次の新規制は、クラウドサービス企業が先端半導体を使用したサービスを中国に提供するのを禁じることだ。先端半導体そのものを入手しなくとも、こうしたクラウドサービス経由で同様の能力を獲得できてしまう。これを封じるという。アマゾンのAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)やマイクロソフトのAzureが対象となると報じられている。
三番目の規制は、中国の軍事に結び付くAI企業へのベンチャーキャピタルなどの投資を禁じる大統領令となる。中国は独自技術の育成を目指しているが、これには資金が必要だ。米ジョージタウン大学の二人の研究者の報告では、2015年から21年にかけて中国のAI企業に対する米国からの投資は最低でも74億5000万ドルに達したという。
問題は軍事関連のAI企業だけを標的にし、民生用は除外するという切り分けが意味をなさない点にある。AIを使ったゲームがそのまま軍事シミュレーションに使えることからも分かるように、両者の区別は不可能だ。まして中国は「軍民融合」を国是とする国だからなおさら難しい。
財務長官のジャネット・イエレンは7月の訪中の際に「米国の対中規制は安全保障分野に限ったもので、それ以外の分野では中国とデカップルしない」と述べて反発を鎮めようとした。だが、軍事・民生の線引きをどうするのか、答えがない。
エヌビディアCEOの激しい警告
こうした新規制の中身がメディアで報じられるにつれて、米国内の半導体産業が政府にブレーキをかけだした。
エヌビディアCEOのジェンスン・フアンが5月下旬に英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューで語った内容が激しい。
昨年10月の規制で「我々は後ろ手に縛られた状態に置かれ、最大の市場である中国に先端半導体を輸出できない」と不満をぶちまけた。「中国が米国から半導体を購入できないと分かれば、彼らは自力で半導体をつくるだけだ。米国はもっと思慮深くあるべきだ」とバイデン政権に注文をつけた。
米国は、昨年8月に施行した半導体科学法(CHIPS法)が用意した527億ドルの資金で補助金を提供して、最先端半導体工場の誘致に躍起だ。台湾積体電路製造(TSMC)やサムスン、SKハイニックスなどの外国勢やインテルなどがこれに応じている。
だが、フアンはこれにもかみついた。「中国のような巨大市場はほかにない。もし世界の半導体市場の3分の1を占める中国への輸出ができないとなれば、米国の半導体製造工場でできた製品をどこに売るのだ」と語った。鳴り物入りで始まったCHIPS法の意義も消滅し、半導体企業の収入が減れば研究開発もなおざりになり、米技術力が弱体化すると言うのだ。
台湾系米国人のフアンは、30年前にエヌビディアを創設しAIに不可欠な画像処理プロセッサー(GPU)で覇者となった。先見の明は米起業家のアニマルスピリットそのものだ。発言からは、補助金や規制で企業を縛ろうとする政府への敵意も感じられる。自由経済を歪め企業をひ弱にする産業政策への拒否感は、多くの起業家が共有している。
7月17日には米半導体工業会(SIA)が「世界最大市場の中国へのアクセスは、米半導体産業の強化に重要であり、過度に広範囲な規制は、米国半導体業界の競争力を奪い、中国からの報復を招く」との声明を発表した。米半導体企業の中には、収益の6~7割が中国という企業もある。
続けて声明は「規制が限定的で明確に定義され同盟国との十分な調整が行われるまでは慎むよう米政権に求める」と要求している。これ以上の半導体規制はやめろ、と言っているのだ。
半導体業界からの警告は、昨年10月の対中規制が予想外の激しさを持ち、業界にとって不意打ちだったことから、今回は先制攻撃に出ようとの意図がにじむ。米紙が新規制の動きを報じると、エヌビディアの株価は下落しロビイストの政府への働きかけが強まっている。
ガリウムとゲルマニウムで逆襲に出る中国
半導体業界の不満を倍加させたのが、中国の報復措置だ。
中国は7月3日、半導体の材料となる希少金属のガリウムとゲルマニウムの輸出を8月1日から許可制にすると発表した。ガリウムは中国の生産が世界シェア9割超を占め、米国は53%を中国からの輸入に頼る。ゲルマニウム産出量も中国は世界トップだ。かねてから懸念されてきた中国の米国に対する半導体報復措置であり、元中国商務次官の魏建国は中国メディアに「反撃の始まりに過ぎない。対中制裁がエスカレートすれば、報復もエスカレートする」と述べている。
中国は5月には米半導体大手のマイクロン・テクノロジーについて、安全保障上の理由から購入停止の方針を決めた。中国はマイクロンの売上高の11%を占める。マイクロンは日本でも大型投資を発表したばかりだが、中国市場を失うとなれば、アジア戦略は不透明になる。
外交でも動きが表面化した。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。