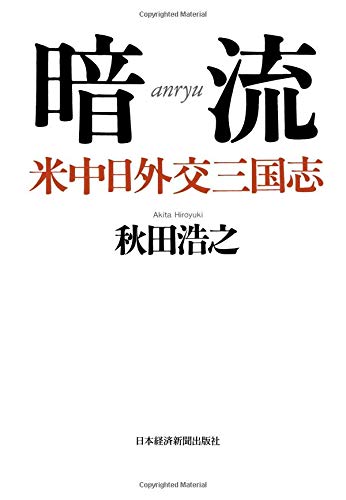世界はきな臭い空気に覆われている。近現代史を3つの期間に区切るとすれば、戦前、戦時(大戦期)、戦後に分かれる。第2次世界大戦後から近年まで、国際社会は「戦後」を生きてきた。国連を始めとする戦後システムのもと、大戦の再発はかろうじて防がれ、世界は繁栄することができた。
しかし、昨年2月24日、ロシアがウクライナに侵略したことによって、戦後は終わってしまった。国連安全保障理事会の機能は壊れ、私たちは「戦前」に突入したといえる。人類は歴史の針が「戦時」(第3次大戦)に進むのを防げるか。本稿では主に米中の視点から、その見通しについて考えてみたい。
「恒久的に準戦時化」という欧州の懸念
5月にロシアに隣接するエストニア、6月には英国を訪れ、政治家や軍幹部、識者らに取材する機会があった。そこで改めて痛感したのが、ウクライナでの戦争が世界にもたらしている脅威の深刻さである。欧州ではロシアへの対応を誤れば、戦火がさらに広がり、第3次大戦への扉が開きかねないという懸念が漂っている。遠く離れた日本ではそうした切迫感は薄いが、残念ながら欧州の認識の方が現実に近いように思う。
例えば、エストニアの首都タリンで取材に応じたクスティ・サルム国防次官は今後の安全保障情勢について、次のように話した。「ロシア軍は装備に再投資し、以前よりも戦力を高めるに違いない。それに何年かかるかはともかく、周辺国の安全保障の環境は良くなるどころか、悪化していく」
ロシア軍が仮にウクライナから撤収を強いられる日が来たとしても、ロシアがウクライナ支配をあきらめることはない。むしろ、軍備を立て直し、再び侵略を試みるだろう。そんなロシアと向き合う欧州は、恒久的に準戦時の状態を強いられる。サルム次官の言葉には、そんな思考がにじんでいる。
5月12〜14日、エストニアで安全保障情勢を討論する「レナルト・メリ会議」が開かれた。そこに参加した米欧の要人や識者らからも、同じような不安が感じられた。ラトビアのクリシュヤーニス・カリンシュ首相に個別にたずねると、極めて悲観的な言葉が返ってきた。
「欧州に恒久的な平和をもたらすにはロシアを徹底的に敗北させ、1945年以降のドイツのような内部変化を起こすしかない。(それが難しければ)長い将来にわたり、ロシアの脅威を封じ込め、抑止する政策が必要になる」
エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国は帝政ロシア、ソ連によって、繰り返し支配下に置かれた歴史がある。およそ半世紀にわたってソ連に組み込まれ、ようやく91年に独立を取り戻した。それだけにバルト三国が極めて厳しいロシア観を抱くのは不思議ではない。
だが、第3次大戦のリスクを感じているのはバルト三国だけではない。6月下旬、ロンドンでインタビューに応じたトニー・ブレア元英首相からも、似たような危機感が伝わってきた。第3次大戦が起きる危険について質問すると、彼はこう答えた。「そんなことになれば、必ず壊滅的な結末になる。だから、私は起きるとは思わない」
ブレア氏は極めて能弁であり、中国やグローバルサウス問題については、精緻な論理で状況を分析した。ところが大戦の危険についてはなぜか口ごもり、あまり掘り下げて語ろうとはしない。「(大戦が)起きるとは思わない」と力説する発言は、感情が先走った言葉に聞こえた。
予断を許さぬ米中「ハイレベル対話加速」の行方
ウクライナでの戦争が欧州、さらにアジアに飛び火すれば、第3次大戦に近づいてしまう。過去の歴史を振り返れば、そのような危険は絵空事ではない。……
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。