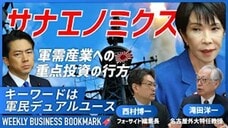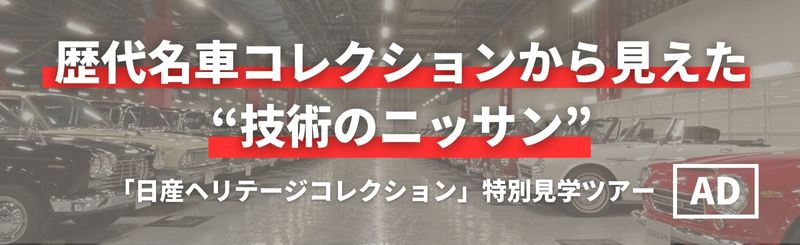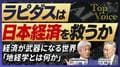「核兵器のない世界」を「究極の目標」とした広島ビジョンへの批判はなぜ生まれるか[平和記念公園で原爆死没者慰霊碑への献花を終えたG7首脳=2023年5月19日](C)時事
核による人類絶滅の恐怖と隣り合わせだった冷戦期は、核戦争に至ることなく終結した。しかし核兵器の脅威はそれで消滅したわけではなかった。核テロリズムが警戒されただけではなく、北朝鮮は核・ミサイル開発を着実に進めてきた。そして、2022年2月に勃発したロシア・ウクライナ戦争では、ロシアがしばしば核恫喝を行っており、世界は核兵器が使用されるリスクと改めて向き合っている。
世界では冷戦終結後わずか30年足らずで大国間の対立が再燃し、「大国間競争」の時代が到来している。その中で、核兵器を巡る安全保障環境も構造的な変化を遂げつつある。中国が大規模な核軍拡を進めつつあることで、冷戦以来の「2つの核超大国」の時代が「3つの核超大国」の時代へと変容しつつあるのである。この変化はどのような形で起こっているのか、世界で最も厳しい安全保障環境に置かれている日本はどう対応すべきなのか、本稿ではいくつかの論点を検討してみる。
1.核を巡る3つの「立ち位置」
今年の5月に開催されたG7広島サミットでは、ロシア・ウクライナ戦争もあって「核の影」が強まりつつある中、開催地が広島だったこともあり、核軍縮が1つのアジェンダとなっていた。そして5月19日には、「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」(以下「広島ビジョン」)に合意した。広島ビジョンには、「我々は、全ての者にとっての安全が損なわれない形で、現実的で、実践的な、責任あるアプローチを通じて達成される、核兵器のない世界という究極の目標に向けた我々のコミットメントを再確認する。」との文言が盛り込まれ、「核兵器のない世界」が「究極の目標」であることをG7の首脳が確認するという成果を上げた。ただ同時に、これを成果と見なさず、広島ビジョンは、核兵器禁止条約に言及していないことや、核抑止力の現実を追認しているとして批判する向きもある。
こうした認識ギャップはどうして生まれるのか。その大きな理由は、核廃絶を優先目標として追求する「立ち位置」は、実は世界の中では前提としては共有されておらず、核兵器を巡る「立ち位置」が実際には3つほどあることに由来していると考えられる。
第1の「立ち位置」は、核兵器を、その破壊力や放射線による後遺症の点から、特に残酷な兵器であるとして「絶対悪」と捉える立場である。この「立ち位置」からは核兵器はまごうことなき「悪」であるから、無条件で核廃絶が目指されることになる。そして「絶対悪」である以上、核抑止の有効性は認められない。
第2の「立ち位置」は、核兵器を「悪」として捉えながらも、「必要悪」と見なすものである。現実の世界には紛争があり、核兵器が抑止力として必要な局面もある。そして何よりも、2つの超大国が厳しく対立していた冷戦期に戦争の勃発を抑止していたのが核兵器であることを踏まえ、現実としての抑止力の有効性を重視することになる。20世紀の2つの世界大戦が核兵器出現前に発生したものであり、核兵器出現後には世界大戦は起こっていないこともまた事実であり、こうした核抑止を重視する考え方は国際社会において一定の影響力を有している。
第3の「立ち位置」は、そもそも核兵器を「悪」とは捉えず、国家の正当な政策手段の1つとして位置づけるものである。特に、現状の国際秩序に挑戦するような国にとっては、核兵器は軍事力の劣勢を一挙に覆すワイルドカードとなり得るため、こうした意味での核兵器の役割が重視されることになる。
このうち、核兵器を「絶対悪」として捉える第1の立場と、「必要悪」と捉える第2の立場は、実際には共通の基盤を見つけ出すことができる。核兵器を「悪」として考える点が共有されているからである。一方で核兵器を「悪」とは見なさない第3の立場とは共通点はない。しかしながら、北朝鮮をはじめとして、第3の立場をとっている国は事実として存在しているのである。ロシアもまた、現在のロシア・ウクライナ戦争における核恫喝を見る限り、第2の立場というより第3の立場であると解釈すべきであろう。
このように、核兵器を「悪」と捉える見方が実際には世界的なコンセンサスではない、ということを考えるならば、広島ビジョンの意味は明確であろう。広島ビジョンでは、「現実的で、実践的な、責任あるアプローチを通じて達成される、核兵器のない世界という究極の目標」をG7諸国が共有していることを明らかにした。つまり、G7諸国は、「現実的で、実践的な、責任あるアプローチ」に導かれるのであれば、「核兵器のある世界」よりも「核兵器のない世界」を選ぶと宣言したのである。これは、核兵器を「悪」と見なさない第3の立場とは明確に異なる。第3の立場であれば、いかなる状況であっても、「核兵器のある世界」を選ぶであろうからだ。
では、世界は核兵器のリスクの少ない世界に向かっているのか。問題はその点にある。G7のこうした動きにもかかわらず、実際には核兵器を巡る安全保障環境は悪化の一途にある。
2.核兵器を巡る安全保障環境の悪化:「核超大国」としての中国の出現
核兵器を巡る安全保障環境の悪化の顕著な例としてまず挙げられるのは、ロシア・ウクライナ戦争においてロシアが再三核恫喝を行い、またウクライナを支援している米国がロシアによる核エスカレーションを恐れてウクライナへの支援をあるラインで自制していることである。
ロシアの核恫喝は、核兵器が国際政治における軍事的な圧力手段として大きな役割を果たしうることを明らかにしたし、また米国の自制は、米国に核リスクを理解させることで、その行動を抑制させられることを証明した。つまり、先に述べた第3の「立ち位置」から、現状打破の手段として核兵器を組み込むことが有効であることが示されてしまったのである。このことは今後、核拡散のトレンドを強めることになりかねない。
また、ロシアは核恫喝だけではなく、新START(新戦略兵器削減)条約の履行停止宣言によって、冷戦後の世界の安定の基礎となってきた米露の核軍備管理を空洞化させた。同時に、重ICBM(大陸間弾道ミサイル)であるサルマトをはじめとする戦略核戦力の近代化を着実に進めている。ロシアの戦略核戦力は、新START条約の期限が切れる2026年に出そろうタイムラインに基づいて研究開発が進められていると推測されている。つまりロシアは、単に新START条約の履行停止宣言をしているだけではなく……
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。