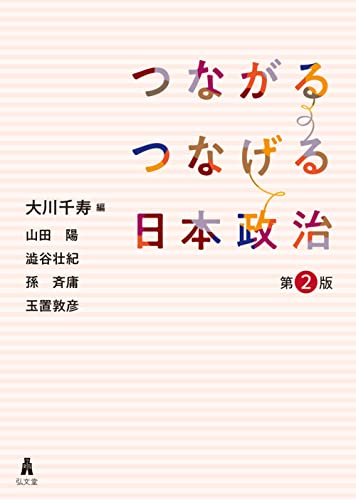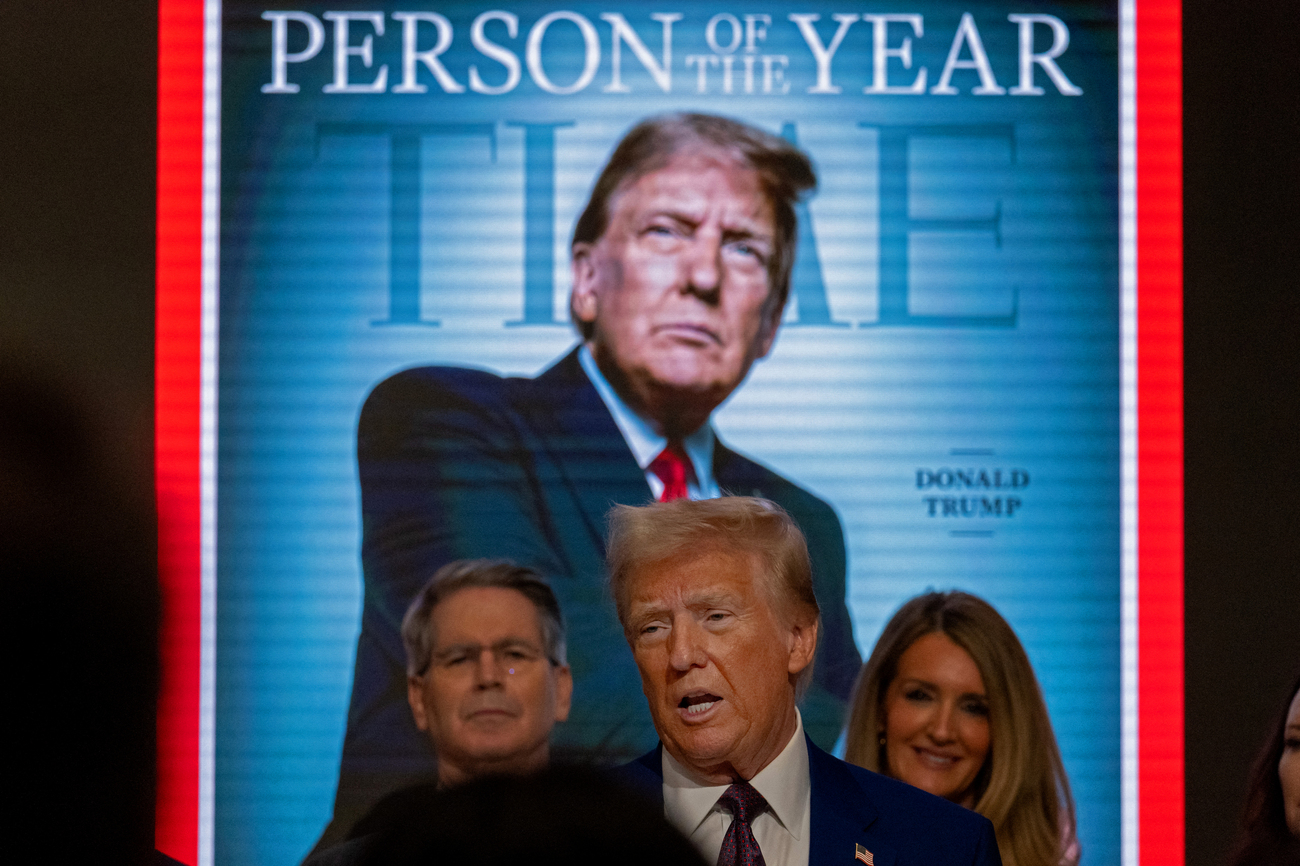
共有される「リベラルな帝国」への懐疑
ドナルド・トランプ前大統領の再登板が衝撃を広げている。2024年11月に米大統領選挙が実施され、2017年から2021年までの第一次政権に続いて、2025年1月にはトランプが再度大統領の座を手にすることが確実となった。トランプは、2021年に成立したジョセフ・バイデン大統領率いる民主党政権を激しく攻撃し、その政策の転換を訴えてきた。経済政策や環境対策等の国内政策についてはもちろん、外交についても、同盟関係、通商政策、ロシア・ウクライナ戦争、中東政策、北朝鮮問題と多くの政策に無視できない変化が生じるものとみられる。短期的には、アメリカの外交政策は内政の変動によって大きく揺れ動くことが確実である。
だが巨視的には、第二次トランプ政権の成立は、2017年以来、過去8年間のアメリカ外交の変化を促進する効果を持つものと捉えるべきだろう。後述するように、すでにバイデン政権の段階で第一次トランプ政権にはじまる外交路線は固定化し、かつ制度化されており、民主党候補のカマラ・ハリス副大統領が勝利したとしても、状況に根本的な変化が生じる可能性は乏しかったからである1。トランプの再登場は、アメリカ外交の変化を顕在化、もしくは加速するものであり、短期的な影響は無視できないが、その長期的インパクトを過大評価すべきではない。
アメリカ外交の構造的な変化の根底にあるのは、やはり国内政治の分断である。2024年11月選挙において、トランプ率いる共和党は大統領選挙及び上下両院で勝利し、同党のシンボルカラーが赤であることから「トリプル・レッド」とよばれる政治的優位を確保した。トランプが完勝したことは間違いないが、しかしこれは圧勝ではない。全米の得票率でみればトランプとハリスの差は僅かであり、「史上稀にみる接戦」という選挙前の評価は誤っていなかった。
他方で、2024年11月選挙以前には、民主党はマイノリティの支持が厚く、これに対してトランプ及び共和党の支持層は白人に偏っており、非白人人口が拡大するというトレンドを考えれば、長期的に共和党の勢力は低減するとの見通しもあった2。ところが今般の選挙ではヒスパニックや黒人の一部が共和党を支持する傾向が顕著となり、こうした見解も説得力を失った。民主党も共和党も、いずれか一方が優位を確保するという状況は予見し得る将来において想定できない。アメリカ国内政治の分断は長期化し、固定化すると考えるべきだろう。
アメリカ外交を考えるうえで重要なのは、内政の分断自体ではなく、その固定化と深刻化によって、国際秩序をリードするリベラルな「帝国」たることへの懐疑が、すでにアメリカの政策論争に埋め込まれているという事実である。そしてその結果、現在のアメリカの政策決定者及び専門家の論調には、党派を超えて、同盟・友好諸国との共存共栄を図るのではなく、同盟をアメリカの安全保障の確保と経済的繁栄の促進のために一方的に活用しようとする思考が顕著となっている。
筆者は、かつて古代ギリシアにおいて、ペルシア帝国への対抗同盟として結成されたデロス同盟の故事を想起せずにはいられない。デロス同盟の盟主アテナイは、同盟諸国の拠出した資金を自らの利益のために流用して繁栄を謳歌し、ギリシアの守護者から利己的な支配者へと変貌した。その末路は同盟国の離反とアテナイによる介入の連鎖であり、これがトゥキュディデスの活写したペロポネソス戦争、ついにはアテナイの没落へと帰結したのであった。なぜいまアメリカで「デロス同盟の誘惑」とでもいうべき事態が生じているのだろうか。
帝国の存在理由
この問題を考えるためには、そもそもなぜアメリカは同盟を結んでいるのか、振り返ってみる必要がある。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。