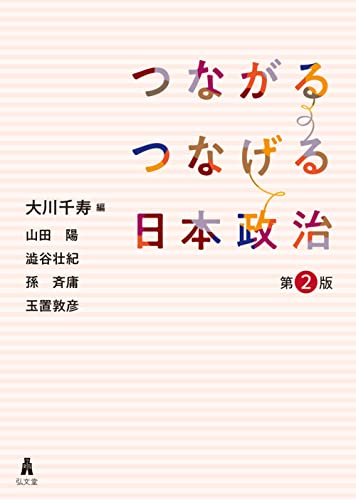転機としてのバイデン政権
2017年1月、冷戦期以来の国家戦略が動揺するなかで誕生したのが第一次ドナルド・トランプ政権だった。この政権は、こうした戦略論争とは無縁に、しかしそれゆえにより直截に、長きにわたるアメリカの戦略構想から大きく逸脱した外交を展開することとなる。そしてその特異な行動様式は、2010年代前半期以来のアメリカ外交の変化を急速に促進する役割を担うこととなった。
とりわけ決定的な意味を持ったのが、トランプ政権の対中政策である。すでにバラク・オバマ政権末期の2014年から2015年を転機として、アメリカの対中政策は大きく変化しはじめていた。とはいえオバマ政権の対中政策は、同盟諸国との軍事関係の強化、自由貿易の推進、国際制度の拡充によって中国の行動を牽制するという、伝統的な国家戦略の延長線上に展開されたというべきだろう。環太平洋パートナーシップ(TPP)の推進はその象徴といえる施策であった。
これに対してトランプは、自由貿易と国際制度・同盟そのものを敵視したため、同盟国やグローバルなアジェンダへの影響を意に介することなく、中国への圧力を行使するという行動をとった。関税や制裁といった経済的圧力の多用、TPP交渉からの離脱、同盟国も含めた二国間交渉での経済的利益の確保といった行動が、「ディール」の名の下に展開されたことは記憶に新しい。そして一連の対中強硬策は、アメリカの労働者・中間層の復興というアジェンダと一体のものとして論じられたことで、同盟国との協調ではなく、むしろその負担の下に中国を抑え込み、またアメリカ経済を復興するとの方針に結実する。このトランプの対中政策は、中国への警戒を強めていた専門家集団、またトランプに対抗して「中間層の復興」を掲げた民主党の政策決定者とも共鳴し、バイデン政権期にこの路線は制度化・体系化されることとなった1。
このようにトランプは、その第一期においても、外交政策の転換の主体というよりも既存の変化を顕在化させる役割を担ったというべきであり、その影響は短期間に消滅する性質のものではなかった。とはいえ第一次トランプ政権が2021年1月6日の連邦議会議事堂襲撃事件の衝撃のなかに終幕を迎え、さらに2022年11月の中間選挙で民主党が善戦した時点では、なおトランプとこれを支持するMAGA(Make America Great Again)派の復権は確実視されていなかった。トランプ以外の候補が共和党予備選を勝ち抜く可能性もあるとみられており、これによって共和党がかつての国際主義的な外交政策に回帰するとの期待もあった。さらにトランプの後を襲ったバイデン大統領が国際秩序への復帰を掲げたことを考えれば、第一次トランプ政権の外交路線は一時的な逸脱と判断する余地がなかったわけではない2。
だがバイデン政権の実態をみてみれば、その戦略構想も国際秩序構想も、かつてのものからすでに決定的な変質を遂げていたことは明らかである。そしてその外交政策には、対中政策に代表されるように、トランプ以前への回帰ではなく、トランプ政権期にはじまる変化をむしろ制度化・体系化する役割を担った例が少なくない。これはすなわち、民主党系の政策決定者及び専門家も、中国の脅威という触媒を背景に、かつてのリベラルな帝国の推進を断念したということを意味する。この点でバイデン政権はアメリカ外交の転機だったといえよう3。
その根幹にあるのは、共存共栄のシステムを築き、またアメリカの力を制度的に自制することで同盟国を惹き付けることがアメリカの優位の核にある、という意識の消滅である。2010年代初頭にはじまったこの変化は第一次トランプ政権で顕在化し、バイデン政権において固定化・制度化され、そして第二次トランプ政権の登場で加速しようとしている。
「唯一の地域覇権国」への固執
以上のように、日本が中長期的に直面している根本的な課題は、アメリカが同盟国・友好国を惹き付ける力と意欲を失った、という事実にある。現在、アメリカの政策コミュニティでは、中国の軍事・経済・技術の伸長を抑え込むことが、アメリカの優位の確保、さらにはその中間層の復興と不可分のものとして議論されている。この論調を、米中の利害はゼロサムであるとの前提に基づくと解釈しても不当ではないだろう。この論理を延長すれば、
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。