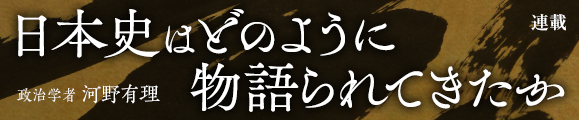小松左京は「人類の進歩と調和」をテーマに掲げた1970年大阪万博のプロデューサーを務めた一方で、『日本沈没』ではカタストロフを書いた (C)時事
(前回はこちらから)
未来学における楽観論と悲観論
小松左京『日本沈没』は1973年の3月に光文社から発売された。日本列島が巨大地震を伴い日本海溝に沈み消滅するという筋書きの言わずと知れたSF大作で、累計は400万部を超える大ベストセラーになった。作品自体の面白さはもちろんあろうが、世相にマッチしたことも間違いなかった。
まずは、公害。四日市ぜんそく裁判に原告が勝利したのは1972年のこと、カネミ油症の原因物質としてPCB(ポリ塩化ビフィニル)の製造中止および回収が決定されたのもこの年である。翌1973年はまた光化学スモッグの注意報が年間328日(史上最多)に達した年でもある。次に、人口爆発。1973年は今のところ(そして当面これからも)日本列島の年間出生数のピークにあたる。同年すぐさま映画化された『日本沈没』の冒頭でも、列島各地が人に溢れる光景がこれでもかと挿入されているのが印象的である。最後に、経済の低成長。1973年10月に勃発した中東戦争によりいわゆるオイルショックが勃発、狂乱物価と称されるインフレが発生し、その後の日本経済は低成長にあえぐことになった。『ゴジラ対へドラ』(1971年映画)、『ノストラダムスの大予言』(1973年書籍)と併記すると、『日本沈没』が広く共感を呼んだこの時期の世相をよりリアルに感じ取ることができるかもしれない。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン