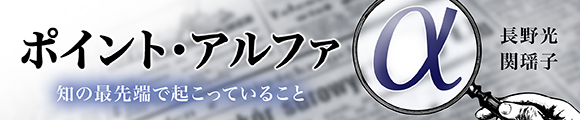「レカネマブ」に残された課題と「予防」への可能性|伊東大介・慶應義塾大学医学部神経内科特任教授(2)
長野光と関瑶子のビデオクリエイター・ユニットが、現代のキーワードを掘り下げるYouTubeチャンネル「Point Alpha」。慶應義塾大学医学部神経内科特任教授の伊東大介氏に、“夢の新薬”とも称される「レカネマブ」の特徴の正しい理解を聞いた。 ※主な発言を抜粋・編集してあります。
代表的既存薬「ドネペジル」との違い
──2023年9月に、日本ではアルツハイマー病の治療薬・レカネマブが薬事承認されました。レカネマブは、どのような作用機序の薬なのでしょうか。
「既存薬との違いとして、ドネペジルと比較してみましょう。ドネペジルは、これまで約25年間、抗認知症薬として使用されてきた代表的な薬です」
「ドネペジルは、脳の神経細胞に働きかけ、活性化させる作用があります。しかし、アルツハイマー病の根本的な原因であるアミロイドβやタウを除去することはできません」
「アルツハイマー病では、時間の経過とともに認知機能が低下していきます。ドネペジルを投与すると、患者さんの認知機能には、数カ月間、症状の改善が見られます。Mini-Mental State Examination(ミニメンタルステート検査)という認知症の国際的な検査手法である30点満点のテストで、1.5点ほど点数が上がります」
「その状態から、数カ月で元の点数に戻ってしまいます。その後症状が悪化していく速度は、治療をしていない状態と変わりません。一次関数で考えると、y切片は上がるが、傾きに変化はない、というものです。下駄を履いた状態で、また症状が進行していきます。これが従来の抗認知症薬の作用です」
「一方、レカネマブは、アミロイドに対する抗体を投与することによって、免疫の力でアミロイドを除去します。アルツハイマー病の症状を抑えるのではなく、病気のそもそもの原因を取り除く、というメカニズムで、アルツハイマー病の進行を抑制することができます」
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。