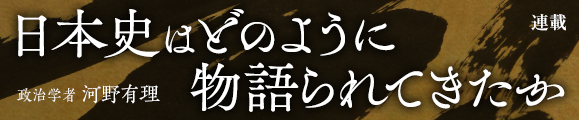(前回はこちらから)
山口昌男と吉本隆明の「近親憎悪」
山口昌男は1969年1月から3月にかけて「幻想・構造・始原」と題した長大な書評論文を『日本読書新聞』に連載している。吉本隆明『共同幻想論』を対象とし、当初は一回で終わるはずだったこの書評論文は実に連載八回に及び、「全員吉本ファン」だった編集部から「「もういい加減にしてほしい」ということで、途中で降板」の憂き目にあったのだという(「歴史と記憶」、1995年、『山口昌男ラビリンス』、国書刊行会、2003年)。「ひとあたり読んでみて、よく分からない部分の多いのに先ず驚いた」で始まる論文はたしかに全体としても極めて辛辣である。これに対し吉本側の反応も激烈で、この「山口昌男という…チンピラ文化人類学者」(「異族の論理」『文藝』1969年12月号)への不快感をまったく隠そうとはしなかった。両者は以後、公式の場で顔を合わせることは無く、その関係は緊張をはらんだものとなった。この書評は山口の最初の単行本『人類学的思考』(せりか書房、1971年)に収録されるが、その後、同書を再編集した『新編人類学的思考』(筑摩書房、1979年)に採録されていないのは、こうした緊張感を反映してのことかもしれない(ただし、1990年刊行の筑摩叢書版では再び収録された)。
もっとも、この点につき山口側の後年の回想は柔らかく、吉本との出会い方についての後悔がむしろにじみ出ている。「吉本というオリジナルでユニークな思想家をいじめてしまったが、あの頃は悪いことをしてしまったという申しわけなさでいっぱい」(同)というのである。「いじめてしまった」という表現になんとも言えない自意識が垣間見えるが、両者を知る人にとっても、吉本に終生「拘泥」していたのは山口の側であり(四方田犬彦「挑発と悲観」『ユリイカ 特集・山口昌男』、2013年6月号)、それが両者の問題意識の共通性に由来するいわば近親憎悪だということは、半ば自明であったように思われる。書評での「罵倒」も言うなれば「芸」であり、さらに言えば吉本自身もまた花田清輝や丸山眞男といった年長世代への「罵倒芸」で論壇に地歩を占めるに至ったという経緯は誰の眼にも明らかだった以上、そこには自ら「トリックスター」たらんとする諧謔とともにある種のリスペクトが込められていた側面もあったのかもしれない。両者を仲介しようとする動きは、その後何度かあったようであるが、「吉本は頑として断った」との由である(前掲四方田)。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。