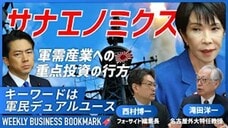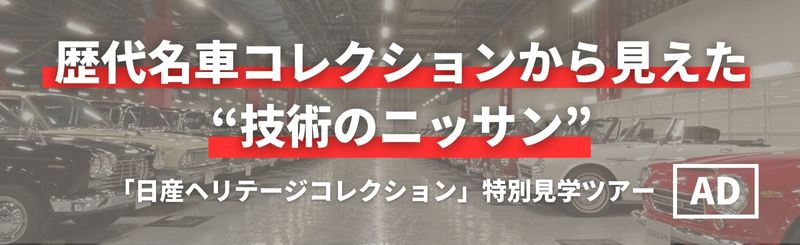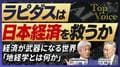小泉悠×小谷賢:サブカルで語る国際政治――なぜ日本人は戦争を正面から描けないのか
【関西大学東京センター×論壇チャンネルことのは】
※小泉・小谷両氏の対談をもとに編集・再構成を加えてあります。
小泉悠(以下、小泉) 私はロシア軍、小谷さんはイギリスのインテリジェンス史が専門ですが、今回は「サブカル」をテーマに国際政治を語ってほしいという依頼です。
小谷賢(以下、小谷) たしか、前回お会いした時にエヴァンゲリオンの話で盛り上がったんですよね。それでこういう対談が企画されたわけです。さて、何から話しましょうか。
原点は「軍都」千葉とガンダム
小泉 僕は軍事オタク、中でもロシア軍のオタクですが、多くのロシア軍オタクって戦車オタクなんですよ。ただ、僕の場合は戦車から入ったわけではなく、アポカリプス(=いわゆる人類絶滅もの)映画が入り口でした。スタンリー・キューブリック監督の『博士の異常な愛情』(1964年)とか、ネビル・シュート原作の『渚にて』(1959年)とか。
ああいう世界観に惹かれたのと、あとショーン・コネリーが出ていた『レッド・オクトーバーを追え!』(1990年)の大ファンだったので、ICBM(大陸間弾道ミサイル)に代表されるロシアの戦略核兵器に関心を持ち、核戦略の研究をしていました。だから、庵野秀明監督の『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年)の終わり方は非常にハマった。
世界全体を滅亡させる核戦力という力を人類はいまだに持っている。アメリカとロシアはそれぞれ1500発の戦略核弾頭を所有、予備弾頭を含めると両者あわせて1万数千発の核弾頭があります。冷戦期のように「人類を7回絶滅させられる」ほどではないにしても、1回は確実に絶滅させられる量です。
冷戦が終わって以降の30年間は、「さすがに核戦力は使わないだろう」という時代が続き、人類絶滅の可能性は後景に退いた。でも僕には、「いつか核戦力が解き放たれる日が来るんじゃないか」という意識がずっとあった。だから、ウクライナ戦争が始まって以降、ついにこういう時代がやってきてしまった、という思いを抱いています。
小谷 意外な原点ですね。私は以前、習志野のあたりに住んでいたことがありますが、小泉さんは千葉県の松戸市出身なんですね。
小泉 はい、松戸のはずれのほうです。千葉県は意外と「軍都」なので、千葉生まれでミリタリーに関心を持ってしまう人ってけっこういるんですよね。『この世界の片隅に』(2016年)の舞台となった広島県の呉市なんかはわかりやすい軍都ですけど、千葉にも昔、それこそ習志野や津田沼に陸軍鉄道連隊がありました。通っていた中学校は海上自衛隊下総基地に近かったので、教室の窓からP-3C(対潜哨戒機)や習志野の第一空挺団のC-1(輸送機)が見えました。
強烈なヤンキー文化の土地でもあるんですが、「陰キャ」は軍オタになってしまいがちな環境がありました(笑)。小谷先生はどちらのご出身ですか?
小谷 私は京都市内の出身ですから、身近にミリタリー的な空気はなかったですね。
その代わり、『ガンダム』のアニメシリーズ(1979年~)を見て育ちました。子供の頃に触れた唯一のミリタリーものがガンダムですね。
小泉 ガンダムは完全に戦争の話ですからね。
小谷 ただ、今から見ると荒唐無稽というか、独特の緩さがあるというか。戦争を描いているといっても、結局はアニメなんですよね。
国際政治って、本当にシビアな世界じゃないですか。軍事・インテリジェンス・外交というものは、シビアでなければ生き残れない世界。今のウクライナの状況がまさにそうです。一方、日本のサブカルに描かれる戦争と、現実の国際政治や戦争とはかなり違う気がします。
「制約」が生んだ日本のサブカル独特の緩さ
小谷 国際政治とサブカルを絡める時、よく「ソフトパワー」という言葉が使われますよね。日本のコンテンツ産業を外交に活かしたいとか、国力に繋げたいとか語られるのですが、そんなことできるわけないんですよ。サブカルというのは基本的に政府の介入やコントロールが及ばない領域で、完全にクリエイティビティの世界なんです。
だから、中国はいま盛んにアニメを作っていますが、日本のレベルには届かないと思います。なぜかというと、中国には検閲があるからです。
小泉 中国にはお金があるし、日本のアニメ業界で働いていた人材もいて、アニメ制作のスキルは持っている。でも、中国からサブカルは出てきませんね。芸術的なアニメ作品はあっても、世界中のオタクが夢中になるような中国製アニメはまず出てこない。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。