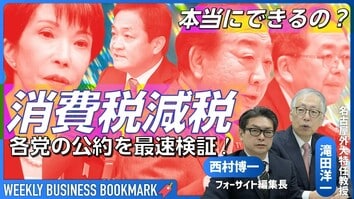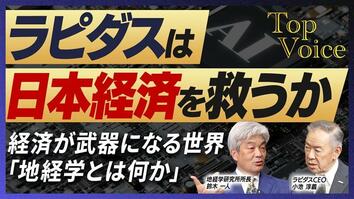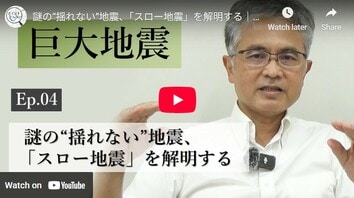池内恵の中東通信
池内恵(いけうちさとし 東京大学教授)が、中東情勢とイスラーム教やその思想について日々少しずつ解説します。
アフガニスタンからの米軍の撤退と、ターリバーン勢力の全土・首都カーブル制圧をめぐって、米国の国内政治の文脈でも、日本など米同盟国の国内政治・外交安全保障論の文脈でも、話題が沸騰しており、それらは重要だが、やや極論を言えば、「負け戦での撤退のやり方と責任の所…
中東の20年前と現在との違いといえば、メディアの双方向性の度合いが著しく上がったことがある。これは中東の一般市民が、国による上からのテレビ放送や統制された新聞による世論誘導を回避して、スマートフォンで撮影した映像をSNSで発信できるといった、「アラブの春」で顕…
中東で、10年、そして20年単位の歴史の節目というべき事象が相次いでいる。「10年」というのは「アラブの春」からの10年である。「アラブの春」の長期的・大規模な変動の口火を切り、唯一の民主化の成功例とされてきたチュニジアで、7月25日、カイス・サイード大統領が、緊急…
一般財団法人中東協力センター(JCCME)の『中東協力センターニュース』には、かなり長い間、定期的に寄稿の機会をいただいている。以前は「連載」していた時期もあり、最近は忙しくて、年に数回程度だが、毎回苦しみながら一定の規模のレポートをまとめている。今回はエジプ…
イランで8月3日ごろ(5日という報道もあるが)にロウハーニー大統領が任期満了で退き、保守派で、最高指導者ハメネイ師の後継者にも擬せられるライースィー師が大統領に就任する。それに先立って、ロウハーニー政権の成果を、ハメネイ師を交えて検証・評価する、いわば「通信…
イスラエルの内政・外交を騒がせるBen & Jerry's騒動について、これが直接的に大きな影響をもたらすものではないにしても、様々な重要なものを表出しており、また何らかの大きな変化のきっかけや兆候となるかもしれないので、いくつかメモをしておこう。最新の動きとしては、7…
イスラエルの外交に逆風が吹き始めている。米トランプ前政権とネタニヤフ前政権の強固な関係を通じて「我が世の春」を謳歌し、中東国際政治に主導権を握っていた感のあるイスラエルだったが、トランプ大統領の再選失敗による強力な庇護者の喪失、2年間で4回の選挙を要したイス…
イラン核合意(JCPOA)の再建交渉は、結局のところ、ロウハーニー政権の元では妥結されず、ライースィー政権に持ち越されることになった。Iran will not return to nuclear talks before new government is formed in Tehran, The Washingon Post, July 14, 2021.Exclusive: I…
6月18日に投開票が行われたイランの第13期大統領選挙については、事前に分析を二本載せており、現地の特派員がリアルタイムで二本の記事を書いてくれてもいる。日本の一般の新聞でもかなり詳細に報道されていた印象がある。ここで多くを付け加える気がしないが、一点、改めて…
6月には中東政治の今後の起点となる重要な事象が複数生じた。そのうち二つを挙げれば、一つはイスラエルでのネタニヤフ首相退陣・ベネット=ラピド政権発足であり、もう一つはイラン大統領選挙でのライースィー候補の勝利である。いずれも大きな事象で、月が改まる前に「中東…
新型コロナウイルスへのワクチンが各国の内政や、外交・覇権競争の主要課題となっている現在である。ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社、ジョンソン&ジョンソン社などの欧米系の巨大製薬企業がそれぞれの製品を競い、mRNAをはじめとする最先端技術の迅速な応用が進…
6月18日に投票が予定されるイラン大統領選挙で、5月25日、監督者評議会(護憲評議会とも呼ばれる)による立候補届出者の審査と選別結果が、内務省により発表された。報道によれば、次の7名の立候補が認められた。Saeed JaliliSeyed Ebrahim RaisiAlireza ZakaniSeyed Amir Hos…
6月18日に投票のイランの大統領選挙の立候補が締め切られた。主要な立候補者は、エブラーヒーム・ライースィー(ライシ)司法長官と、アリー・ラーリジャーニー前国会議長の二人と目されている。いずれも保守派と目される。イラン大統領選挙の仕組みと機能イランの大統領任期…
5月10日のハマースによるロケット砲攻撃に始まった、イスラエルとガザのハマースとの戦闘で、5月20日、双方がエジプトの仲介による停戦の受け入れを発表した。イスラエルの現地時間5月21日午前2時(日本時間同日午前8時)に発効した停戦がもし持続すれば、今回のガザでの戦闘…
昨年12月1日に調印されて専門家の注目を集めた、スーダンの紅海岸の主要都市ポート・スーダン付近にロシア海軍の基地を建設する計画が停止されたとの報道がある。4月28日に中東メディアで報じられている。米国やエジプトやサウジのみならず、トルコやUAEなどが紅海・アフリカ…
ザリーフ外相が革命防衛隊、特にクドゥス部隊のガーセム・ソレイマーニー司令官の外交への介入を批判したインタビューがリークされた問題について、補足とアップデートをしておこう。続報によれば、ザリーフ外相のインタビューは、大統領府の戦略研究センター(Center for Str…
4月25日には「薄れゆく『イラン対サウジの覇権競争』」と題して、「中東 危機の震源を読む」欄への久々の寄稿として、遅ればせながらのサウジの対イラン接近の表面化について記しておいた。ここでは対イラン圧力政策、イエメン内戦介入政策、イスラエルへの接近政策のいずれ…
イランのザリーフ外相が、イスラーム革命防衛隊による支配を批判するインタビューの録音がリークされ、話題になっている。"Iran’s Foreign Minister, in Leaked Tape, Says Revolutionary Guards Set Policies," The New York Times, April 25, 2021.ザリーフのインタビュー…
「中東通信」欄は元来は、ごく短い文章でその時々の中東情勢の断面・断片を切り取るアフォリズム(警句)のような、最近でいえばTwitterの呟きのようなものと考えて設立してもらった欄なのだが、書くとなるとつい力を入れて本格的になってしまう。暫くはなるべく簡略に。メモ…
例年4月24日は、世界各地のアルメニア人が、第一次世界大戦中の1915年以降に生じた「アルメニア人虐殺」を思い起こし世界に呼びかける記念日である。バイデン大統領は、今年のアルメニア人虐殺の記念日に寄せた声明で、米大統領として初めて公式にこれを「虐殺(genocide)」…
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン
- 24時間
- 1週間
- f
-
1
台湾領海で海底ケーブルを切断した「宏泰58号」の謎

-
2
「避けられたはずのグリーンランド危機」は米欧関係に何を残すか

-
3
Q.17 酒鬼薔薇聖斗は社会復帰しているか

-
4
40歳まで成長期? ティラノサウルスは大器晩成型だった

-
5
対中関係“温め直し”に走る欧州

-
6
石油をめぐる米国とベネズエラの地政学から浮かび上がる6つの論点

-
7
はたして少年A=酒鬼薔薇聖斗は、更生しているのか

-
8
習近平総書記が失脚する? なぜ日本人は怪しげな中国政治ゴシップを信じるのか

- 9 「権力になびく大学人」と「業者にたかる大学人」の性根は同じ 東大医学部スキャンダルが終わらぬ理由
-
10
新首相官邸に常勤医を送り込む防衛庁

-
 廃墟のヨーロッパ
¥2,860(税込)
廃墟のヨーロッパ
¥2,860(税込) -
 北方領土を知るための63章
¥2,640(税込)
北方領土を知るための63章
¥2,640(税込) -
 ウクライナ企業の死闘 (産経セレクト S 039)
¥1,210(税込)
ウクライナ企業の死闘 (産経セレクト S 039)
¥1,210(税込) -
 地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦
¥1,870(税込)
地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦
¥1,870(税込) -
 誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断 (PHP新書)
¥1,100(税込)
誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断 (PHP新書)
¥1,100(税込) -
 農業ビジネス
¥1,848(税込)
農業ビジネス
¥1,848(税込) -
 古典に学ぶ現代世界 (日経プレミアシリーズ)
¥1,210(税込)
古典に学ぶ現代世界 (日経プレミアシリーズ)
¥1,210(税込) -
 ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔
¥2,750(税込)
ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔
¥2,750(税込) -
 ウンコノミクス (インターナショナル新書)
¥1,045(税込)
ウンコノミクス (インターナショナル新書)
¥1,045(税込)