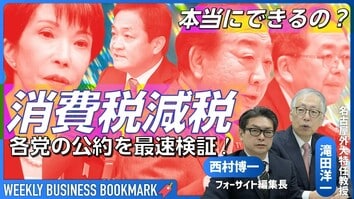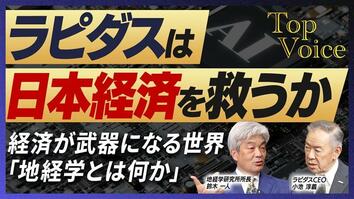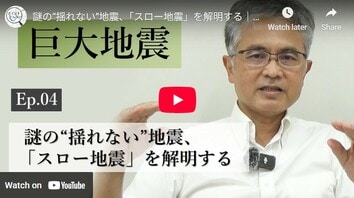池内恵の中東通信
池内恵(いけうちさとし 東京大学教授)が、中東情勢とイスラーム教やその思想について日々少しずつ解説します。
米・イラン間の緊張が高まるペルシア湾岸情勢で、エスカレーションを進めかねないのが、米トランプ政権と一致して対イラン圧力を強めるサウジへの、イランの代理勢力とサウジが認識する勢力からの攻撃である。5月14日にサウジ国営通信社が伝えた、ハーリド・アル・ファーレハ…
ジョン・ボルトン米大統領安全保障問題担当補佐官と、マイク・ポンペオ国務長官が牽引するとされるトランプ政権内の対イラン強硬派が、イランとの緊張を意図的に高め、いわば「意図的に偶発的な衝突を生じさせる」ことを狙っているのではないかという疑念が、フジャイラ沖の「…
5月15日に急遽訪日したイランのザリーフ外相の最近の動き。5月15日から遡る「過去数日以内」に、カタールのムハンマド・ビン・アブドッラフマーン外相がイランを訪問しテヘランでザリーフ外相と会談した模様である。ウデイド空軍基地に米軍を受け入れつつ、米同盟国のサウジや…
イランのザリーフ外相が、5月15日、急遽来日した。外務省によれば、滞在は17日までの予定という。NHKの報道では、16日に河野外相との会談、安倍首相への表敬訪問が行われる模様である。NHKのウェブサイトは短期間で削除されてしまうことが多いため(これによってNHKは国際的に…
ペルシア湾の出口ホルムズ海峡の外に位置するUAEフジャイラでの事件と関連があるかどうか分からないが、気になるのは、5月11日にパキスタン南西部バルーチスターン州の港市グワダルで起こった、高級ホテル(Zaver Pearl-Continental Hotel)の襲撃事件である。初期の報道では…
フジャイラ沖船舶への「破壊工作」の実態が一向に明らかにならないまま緊張が高まるペルシア湾岸情勢は「霧の中」にある。水面下での工作が絡む場合、大国の諜報機関ですらそう即座に明らかにできないものであるから、目先の情報に踊らされることは時間と労力の無駄である。公…
米国トランプ政権が、イランへの圧力を強めていく中で、5月12日にUAE(アラブ首長国連邦)のフジャイラ港沖で発生したとされる、サウジ2隻、UAEシャルジャ1隻及びノルウェーの4隻の船舶を対象とした「破壊工作」を境に、偶発的な衝突の危険性への警戒が高まっている。5月14…
今年の10連休は、休みなく2回の中東出張で費やした。トルコとイスラエルにそれぞれの用事で出向いて忙しく過ごしたのだが、特に現地での(現地との)やりとりに欠かせないのが無料で通話やテキストメッセージのやりとりをする対話アプリのワッツアップ(WhatsApp)である。現…
今週の中東からのニュースで、地域国際政治の長期的・構造的な変化に大きな意味を持つのはこのニュースだろう。"Exclusive: Egypt withdraws from U.S.-led anti-Iran security initiative - sources," Reuters, April 11, 2019.エジプトが「アラブ版NATO」とも呼ばれる、サウ…
最近の中東の関心事といえば、4月9日のイスラエル総選挙だろう。注目・関心は一点「ついにネタニヤフ首相が退陣するか」どうかにある。イスラエル検察は2月28日、ネタニヤフ首相を汚職疑惑で起訴する方針を発表した。選挙では、ネタニヤフのかつての側近たちを含む対抗勢力が…
日々に新しい動きが身の回りに起こるのだが、最近の特筆すべき出来事は、ドバイのアラビア語日刊紙『アッ=ルウヤ(意見)』のコラム二ストになって、毎日曜日にコラムを寄稿するようになったことだ。2月に始め、すでに6回のコラムを寄稿している。最近も昨日3月31日に掲載さ…
グローバルセキュリティ・宗教分野では、私の主要なフィールドである中東を中心に、ロシア・東欧・バルカン、あるいはアフリカや南アジアなども対象に含んでいる。そういうこともあって、特任助教に、『フォーサイト』への寄稿でもおなじみの小泉悠氏を採用した。日本の国立大…
しばらくお休みしていた「中東通信」欄だが、新学期の季節ということもあり、肩に力を入れず再開してみよう。ここのところの忙しさは何よりも、昨年10月1日に、所属先の東大・先端研に「グローバルセキュリティ・宗教分野」を設立したことによる。それまでは「イスラム政治思…
最近最も気になったニュースはこれである。"Twitter warns of 'unusual activity' from China and Saudi Arabia," BBC, 17 December 2018.Twitter社自身の発表によると、プログラムのバグにより、ヘルプ欄からTwitterのユーザーの国番号やアカウントのロックの有無が漏れる状…
米国のマティス国防長官が12月20日に、2月末での辞任を表明した。マティス更迭が近いという観測は中間選挙前から流れていたが、職を辞するに至った決定的な契機は、前日トランプ大統領自身が発表した、政権内部や軍幹部の意向、同盟国の反対を押し切って急激なシリア撤退を決…
米トランプ大統領は12月19日昼に「シリアでイスラーム国に勝利した。米軍がシリアに駐留する唯一の理由(がなくなった)」とツイートし、シリアからの米軍の早期撤退を表明した。米国は2000人規模の軍をシリアに、特に北東部を中心に展開し、クルド系部隊をはじめとした現地の…
10月2日にイスタンブルのサウジアラビア総領事館で発生したサウジ人記者ハーショクジー(カショギ)氏殺害事件をきっかけにした「サウジ問題」あるいはより正確には「ムハンマド皇太子問題」についての国際的な関心は持続している。「ゴシップ・ネタ」として面白いためか、普…
先月はひと月のうち23日も海外に出ていた。トルコ・イスタンブル、エジプト・カイロ、米ミシガン州、米テキサス州など。その前はイスタンブル経由でイスラエルのテルアビブやエルサレムに行っていた。会議に呼んでいただくこともあるが、私の場合は現地調査やなんらかの会議・…
つい先日も「フォーサイト読んでいました」と声をかけられた。「いました」と過去形なのは、月刊誌の「紙の」時代のフォーサイトを購読していただいていたからである。親子で読んでいてくださって、私の本も探して読んでいただいていたという。嬉しい限りである。ビジネスマン…
しばらくこの欄の更新をしていなかった。「フォーサイト(先見)」というこの媒体の性質を、かつての月刊誌の時代から深く受け止めている。フォーサイトへの寄稿の際には、多くが注目していない時に将来の変化の兆しを感じ取って、先立って記しておく、ということに全神経を集…
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン
- 24時間
- 1週間
- f
-
1
台湾領海で海底ケーブルを切断した「宏泰58号」の謎

-
2
「避けられたはずのグリーンランド危機」は米欧関係に何を残すか

-
3
Q.17 酒鬼薔薇聖斗は社会復帰しているか

-
4
40歳まで成長期? ティラノサウルスは大器晩成型だった

-
5
対中関係“温め直し”に走る欧州

-
6
はたして少年A=酒鬼薔薇聖斗は、更生しているのか

-
7
石油をめぐる米国とベネズエラの地政学から浮かび上がる6つの論点

-
8
習近平総書記が失脚する? なぜ日本人は怪しげな中国政治ゴシップを信じるのか

-
9
新首相官邸に常勤医を送り込む防衛庁

- 10 「権力になびく大学人」と「業者にたかる大学人」の性根は同じ 東大医学部スキャンダルが終わらぬ理由
-
 廃墟のヨーロッパ
¥2,860(税込)
廃墟のヨーロッパ
¥2,860(税込) -
 北方領土を知るための63章
¥2,640(税込)
北方領土を知るための63章
¥2,640(税込) -
 ウクライナ企業の死闘 (産経セレクト S 039)
¥1,210(税込)
ウクライナ企業の死闘 (産経セレクト S 039)
¥1,210(税込) -
 地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦
¥1,870(税込)
地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦
¥1,870(税込) -
 誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断 (PHP新書)
¥1,100(税込)
誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断 (PHP新書)
¥1,100(税込) -
 農業ビジネス
¥1,848(税込)
農業ビジネス
¥1,848(税込) -
 古典に学ぶ現代世界 (日経プレミアシリーズ)
¥1,210(税込)
古典に学ぶ現代世界 (日経プレミアシリーズ)
¥1,210(税込) -
 ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔
¥2,750(税込)
ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔
¥2,750(税込) -
 ウンコノミクス (インターナショナル新書)
¥1,045(税込)
ウンコノミクス (インターナショナル新書)
¥1,045(税込)