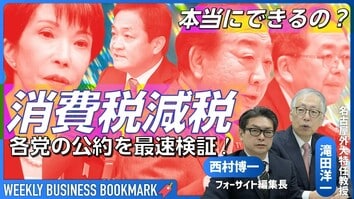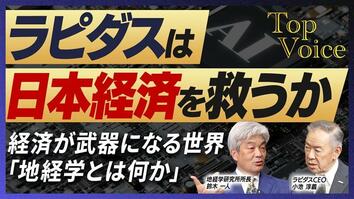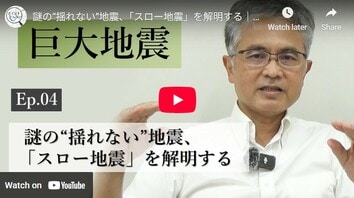池内恵の中東通信
池内恵(いけうちさとし 東京大学教授)が、中東情勢とイスラーム教やその思想について日々少しずつ解説します。
「エネルギーの部屋」の岩瀬昇さんが、参議院の「資源エネルギーに関する調査会」で参考人として意見陳述を行うとのお知らせが『フォーサイト』のトップページにあったので、事後になったが、ウェブサイトを見てみると、参議院のウェブサイトからビデオで視聴ができる。何しろ…
トランプ大統領が1月28日に発表した中東和平案、通称「世紀のディール」は、簡単に言えば、イスラエルがヨルダン川西岸の占領地に建設した入植地の大部分をイスラエルの正統な領土であると認めたものである。ネタニヤフ首相は早速、米国が認めると言ったのだから、即座に入植…
トランプ大統領が1月28日正午、ホワイトハウスで、イスラエルのネタニヤフ首相と共に、中東和平(イスラエル・パレスチナ和平)に関するいわゆる「世紀のディール」を発表した。和平案"Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli Pe…
連載「中東 危機の震源を読む」に久しぶりに論考(中東―危機の震源を読む (96)年末年始・中東のもう1つの騒動:東地中海ガス田をめぐるトルコとイスラエルの虚実皮膜」)を寄稿した。今後は大きなテーマについてのまとまりのある論考は連載「中東 危機の震源を読む」に、日…
サウジアラビアのアーディル・ジュベイル外交担当国務相(元外相)が、1月23日にダボス会議でイランに「普通の国」になれ、と告げたことが少々話題になっている。サウジ系のメディアでは、当然のことだが「言ってやった」と囃し立てる。"Jubeir Says Restoring Ties with Iran…
年末年始の、カルロス・ゴーン逃亡事件と、ソレイマーニー司令官暗殺によって急加速した米・イラン対立の緊迫化の合間に、このような論考を走り書きしていた。池内恵「トルコのリビア内戦介入と東地中海地域のエネルギー国際政治」『中東協力センターニュース』2020年1月号、1…
昨年から注目してきた、サウジアラビアやイスラエルが絡んだ国際政治における、スマホ・ハッキング問題であるが、「Amazon.com」の創設者であり、『ワシントン・ポスト』のオーナーでもあるジェフ・ベゾス氏のスマートフォンを、サウジのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子と…
この欄では、元来は「有料・会員限定ツイッター」のようなものにしたかったのだが、毎度、本格的な論考に近いものを載せることになってしまい、いきおい更新頻度が下がる。今度こそつぶやきに戻していきたい。先月・昨年末からつぶやきたかったのは「サウジ・アラムコ株は『日…
カーブース前国王の死去が1月10日に発表されたが、11日に召集された王室会議で、前国王の従弟で、遺産文化相を務めていたハイサム・ビン・ターリク・ビン・タイムール(Asa'ad bin Tariq bin Taimur Al Sa'id)が、新国王に選出されたとの発表があった模様だ。アラブ部族の権…
大晦日と正月に、ゴーン逃亡事件という日本が直接に関係した茶番劇と、ソレイマーニー司令官暗殺で急激に高まった米・イラン直接戦争の危機が持ち上がり、この欄で書くべきことがすでに山積みになっているが、さらに長期的に重要な出来事が矢継ぎ早に起きているので、まとめら…
今回のロウハーニー大統領の来日は、イランの大統領としては2000年のハータミー大統領以来19年ぶりの来日であり、ロウハーニー大統領にとっては初の来日である、ということが、日本での報道・論評では決まって取り上げられていた。ただし、大統領になる以前にはロウハーニーは…
ロウハーニー大統領が12月20−21日に来日し、安倍晋三首相との首脳会談、拡大会合、夕食会等の盛りだくさんな日程による接遇を受けた。これについて、筆者は英語でコメントを出しているが、基本的な印象は、あくまでも日・イランの「二国間関係」に(少なくとも表向きは)限定…
今回の現地調査では、カタール・ドーハでの用事を終えた後、トルコのイスタンブールとアンカラを巡った。カタールで目立つのはトルコの影響力の増大である。ドーハ・フォーラムでも、総合司会がトルコの国営放送TRTワールドのキャスターであるのに始まり、エルドアン大統領の…
カタール訪問の件は、ここフォーサイトが日本語で、しかも会員制だからこそ書けるという面もある。カタールに頻繁に出かけているということを、アラブ世界向けに英語やアラビア語で公にする文章では、書きにくい。サウジ側やUAE側の人たちから「カタール側の人間ではないか」…
先月に続き、カタールのドーハを訪問した。毎月のようにカタールに行くというのは多い気もするが、カタールが国際政治・安全保障上の戦略として力を入れる、「国際会議」「国際スポーツ大会」は、ドーハだけでなくロンドンやイスタンブールなどにも投資して支援し拠点形成とネ…
先ほど書いた、サッカーのアラブ・湾岸地域の国際大会への参加を通じて、サウジ・UAEがカタールへの歩み寄りを図っている噂が事実であったことが、公式報道で確認された。カタール系メディアが一足先に報じ、サウジ、およびUAEのメディアが続いて一斉に報じたところでは、サウ…
サウジ・UAE主導のカタール制裁は2年以上続くが結局カタールを屈服させることはできず、カタールの背後にいるとサウジが危惧したイランやトルコとの関係でも、むしろサウジ側が不利になる中で、なし崩しに制裁解除を行うタイミングを双方が図っているようである。"Qatar Takin…
カタールに行く時に留意せざるを得ないのは、サウジアラビアやUAEなどの隣国との関係である。2017年6月に、サウジ・UAEが、サウジの属国的立場にあるバーレーンや、サウジ・UAEの資金注入に国家経営を依存するエジプトを従わせて、カタールとの外交・通商貿易関係を切断した。…
国際会議のためにカタールのドーハに来ている。先週はモスクワ出張で、帰国した直後に今度はドーハに向かった。カタール政府(首長府)は「ドーハ・フォーラム」をはじめとした国際会議をスポンサーして、各国から関係者を集めて毎年いくつもの国際会議を開く。そういった招待…
ロシア出張の途中で、各地を転々としながら書いているのだが、昨夜の「国際政治ch」の感想をもう1つ。「国際政治」をテーマにしたチャンネルを立ち上げるというのは、制作会社の方にとって容易なことではなかったはずである。みたところまったくのテレビ業界人で、芸能やバラ…
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン
- 24時間
- 1週間
- f
-
1
台湾領海で海底ケーブルを切断した「宏泰58号」の謎

-
2
「避けられたはずのグリーンランド危機」は米欧関係に何を残すか

-
3
Q.17 酒鬼薔薇聖斗は社会復帰しているか

-
4
40歳まで成長期? ティラノサウルスは大器晩成型だった

-
5
対中関係“温め直し”に走る欧州

-
6
はたして少年A=酒鬼薔薇聖斗は、更生しているのか

-
7
石油をめぐる米国とベネズエラの地政学から浮かび上がる6つの論点

-
8
習近平総書記が失脚する? なぜ日本人は怪しげな中国政治ゴシップを信じるのか

-
9
新首相官邸に常勤医を送り込む防衛庁

- 10 「権力になびく大学人」と「業者にたかる大学人」の性根は同じ 東大医学部スキャンダルが終わらぬ理由
-
 廃墟のヨーロッパ
¥2,860(税込)
廃墟のヨーロッパ
¥2,860(税込) -
 北方領土を知るための63章
¥2,640(税込)
北方領土を知るための63章
¥2,640(税込) -
 ウクライナ企業の死闘 (産経セレクト S 039)
¥1,210(税込)
ウクライナ企業の死闘 (産経セレクト S 039)
¥1,210(税込) -
 地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦
¥1,870(税込)
地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦
¥1,870(税込) -
 誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断 (PHP新書)
¥1,100(税込)
誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断 (PHP新書)
¥1,100(税込) -
 農業ビジネス
¥1,848(税込)
農業ビジネス
¥1,848(税込) -
 古典に学ぶ現代世界 (日経プレミアシリーズ)
¥1,210(税込)
古典に学ぶ現代世界 (日経プレミアシリーズ)
¥1,210(税込) -
 ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔
¥2,750(税込)
ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔
¥2,750(税込) -
 ウンコノミクス (インターナショナル新書)
¥1,045(税込)
ウンコノミクス (インターナショナル新書)
¥1,045(税込)