
2022年の世界の動きを振り返ると、常に宗教と政治の深い関わり合いを感じざるを得なかった。ロシアによるウクライナ侵攻は、ウラジーミル・プーチンが「聖戦」として正当化しようとしている。また、米国で行われた中間選挙で国論を二分した中絶問題も、プロテスタントが主流だった米国社会で、カトリック人口が増大した影響が大きい。米人口の60%が中絶の非合法化に反対、これを受けた民主党が若い女性票や無党派層にアピールして、有利と言われた共和党に善戦した。しかし裏を返せば40%近くが中絶に反対しているという現実がこの国にはある。
宗教に関心の薄いといわれる日本人は、これらの事態をどう理解するべきか、2022年に刊行された3冊の本で考えてみたい。
牧原出『田中耕太郎―闘う司法の確立者、世界法の探究者』(中公新書、2022)
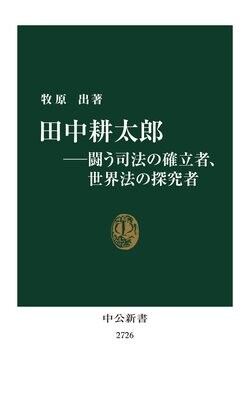
田中耕太郎は日本の法学者として、まさに頂点を極めた人であった。東大法学部長を経て、第一次吉田内閣では文部大臣として入閣。参院議員から最高裁長官に転じ、晩年は国際司法裁判所の判事も務めた。だが、彼に対する世間の評価は総じて「アメリカの犬」であり、「保守」「反共産」の権化であり、とくに左派リベラルと言われる人たちからは、つねに厳しい批判を受けていた。田中はこうした声に「世間の雑音に耳を貸さず」と、応じた。そんな田中耕太郎を現在の視点で改めて見つめ直し、従来の評価に一石を投じたのが本書である。
田中の名を世に知らしめた判決の一つは、彼が最高裁長官時代に扱った砂川事件(第2次)であろう。
1957年に東京立川の米軍基地に立ち入ったデモ隊を、日米地位協定の前身である「日米安保第3条に基づく行政協定」で逮捕起訴した事件は、最終的に田中の差し戻し判決によって地裁で有罪となったが、裁判では米軍の駐留が憲法第9条に触れるかどうかが大きな論点となった。田中は、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定していない。同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力で、外国の軍隊はこの戦力にあたらず、米軍の駐留は憲法及びその前文の趣旨に反しない」としたうえで、「日米安保のように高度な政治性をもつ条約は、明白に違憲無効と認められない限り、その内容が違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」と、いわゆる「統治行為論」にも言及した。
60年安保闘争へと向かう「逆コース」といわれた時代にあって、当然のことながら、これら田中の言説は世の指弾を受けた。しかも後に公開された米公文書で米国大使に裁判の仔細を報告していたことが明らかになると、すでに鬼籍に入っていた田中はさらなる批判に晒された。
また、田中を知る上で、もう一つ重要な判決がある。それは長官就任直後の1950年に下した尊属殺人加罰規定の合法判決である。従来厳罰とされてきた尊属殺は、1973年の「栃木実父殺害事件」(性的虐待を続けた父を娘が殺害した事件)で、「法の下の平等」を理由に、ついに違憲とされたが、それ以前の段階、田中は、頑なに厳罰維持を主張していたのである。
こうして見ると田中耕太郎は、旧来の因習にとらわれる頑迷な法学者ということになるだろう。しかしここにキリスト教カトリックの視点を通すと、別の田中耕太郎像が浮かび上がってくる。
本書では冒頭から田中の生い立ちとともに、彼の宗教遍歴が紹介される。かつて内村鑑三に傾倒するプロテスタントだった田中は、内村が作り出す家父長的な空間に違和感を覚えはじめると、敬虔なカトリック信者の妻の影響もあって、その宗教観を一変させる。キリスト教信仰をめぐり個人の内面を追究するプロテスタントより、教会の権威のもとで信仰の統一性を保つカトリックに意義を見出し、個人主義でも集団主義でもないコミュニティ論を見据えた、自然法に基づく新トマス神学に傾倒するようになるのだ。そして「主観主義に基づく無教会派に代表されるプロテスタント」を強く批判するようになった。
こうした田中は、ローマ法やカトリック神学起源の大陸欧州法を熟知、また英米法判例にも明るく、フランスや米国で戦後判例のある統治行為論を砂川事件に適用した可能性が指摘出来る。
さらに尊属殺についても、それはローマ法で定められた「パリキディウム(近親殺)」に通ずる考え方であり、田中自身も、家族を「本源的で完全な共同体」と呼び、国家の教育権の起源を、両親の子供に対する自然法上の教育権に見出していた。
こうした一連の田中の司法判断は、宗教に強い影響を受ける国際社会を理解する上で重要な視点となる。
前嶋和弘『キャンセルカルチャー―アメリカ、貶めあう社会』(小学館、2022)

砂川事件の判決の際に論じられた「統治行為論」とは、高度の政治性ある事柄について司法の審査対象から外し、三権分立を維持するために司法の独立性を担保するというものだが、これは米国の中絶論争に通じる。
2022年6月、女性の中絶権を合法とした1973年のロー対ウエイド判決が覆され、各州で中絶が制限、もしくは禁止された。これについて、おそらくはトランプ政権下で指名された3人の保守派の最高裁判事がリベラル派の判事を圧倒して中絶が非合法化されたというのが一般的な理解だろう。ただ、判決内容を正確に読めば、ロー対ウエイド判決は、プライバシー権を根拠としたものであり、覆された理由も、その法的根拠が弱かったことによるものである。つまり裁判官は中絶問題という、高度な政治性をもつ事案に対して、司法の独立性を維持したのである。
しかし米国社会はそうは受け取らなかった。2022年の米中間選挙で最大の争点となったように、法的な説明よりもむしろ、「中絶は殺人」と感情に訴えかけ、ドナルド・トランプ前大統領を支持するキリスト教福音派の「勝利」が喧伝された。また一方でリベラル派は女性の権利を声高に唱えた。そこに双方が歩み寄る余地はなかった。
こうした動きについて本書は、「アメリカの人工妊娠中絶の賛否は、日本でいえば憲法9条のように『国民を大きく割るくさび形争点』であり、文化戦争の最大の『戦場』の一つである」と記している。
SNSの普及に伴うエコーチェンバー現象の加速化、失われる対立意見との間の議論。結果として生まれたのが、一方的に相手を貶める「キャンセルカルチャー」である。
この問題は移民や人種問題、環境問題、ワクチンなどあらゆる分野で起きていると本書は指摘する。2020年に起きた白人警官による黒人殺害事件をきっかけに起こったBLM(Black Lives Matter)は、瞬く間に米国から世界に広がった。白人警官には禁錮22年の厳罰が科されたが、BLMの動きは英米の歴史的な白人の銅像の破壊に及び、ジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファーソンら「建国の父祖」たちの像が撤去され、その追及の手は英国のウィンストン・チャーチル元首相の像の破壊にも及んだ。
「中絶は殺人」を強く主張したのは、米国の保守派、主にキリスト教福音派の人たちだったが、原理主義的な価値判断の文脈で見ると、BLMを支えた急進的なリベラル主義者もまた同様である。彼らは歴史上の偉人を評価することを拒否し、21世紀の価値基準であるジェンダーや人種平等論を過去の歴史にまで押し付ける。
感情に訴える政治であり、トランプが扇動した米国議会襲撃事件もこうしたキャンセルカルチャーの表象の一つであろう。そこでは法を破ることがいとも簡単に行われる。
角茂樹『ウクライナ侵攻とロシア正教会―この攻防は宗教対立でもある』(KAWADE夢新書、2022)
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、感情に訴えて法を破ることが国際法の領域で行われた事例である。この軍事侵攻は明らかな国際法違反であるにもかかわらず、本書で明かされるように、プーチンは宗教を利用してロシア国民の感情に訴え、侵攻を「聖戦(正戦)」と言い換えて正当化した。
本書ではキリスト教は戦争をどう考えるのかが議論されている。
アリストテレスの「自己防衛」論と、ローマ法に由来するアウグスティヌスの「穏健で必要最小限度の暴力行使」の原則は、カトリック神学においてはトマス・アキナスの自然法に受け継がれ、後期スコラ哲学サラマンカ学派へと発展した。国際法に基づいた「自衛の戦争は許される」という言説は、ここを母胎として誕生している。またプロテスタントでも、フーゴ―・グロティウスが「戦争における法」を確立し、「戦闘員と非戦闘員の区別」などの項目が設けられて、マイケル・ウォルツァーの「正しい戦争」へと繋がっていった。
そのためカトリックにもプロテスタントにも従軍司祭、牧師がおり、彼らは兵士たちを祝福する。
本書によると、カトリック教会は自衛のための戦争を認めているので兵士を祝福するのは当然だが、ロシア正教会の総主教キリルのように、核兵器を含むあらゆる武器も祝福することはしない。核兵器や生物化学兵器など大量破壊兵器の使用は、自衛を超えたものであるからだ。
ところで、冒頭に触れた田中耕太郎だが、彼が最後に就いた公職は上述の通り国際司法裁判所の判事だった。これに選出されるプロセスでは、欧米やアジア各国の裁判官との選挙戦があった。裁判官は出身国の利益代表ではないものの、敗戦国で国連非常任理事国の日本にとって田中の選出は悲願であった。常任理事国の米国の後押しもあり、最終的に田中が選出される。
米大統領のフランクリン・ローズベルトやハリー・トルーマンに仕え、国連の設立に大きく寄与した法学者フィリップ・C・ジェサップと田中には共通した視角があることも、選出の理由であった。元々ドイツの商法学にそのキャリアの起点がある田中は、ローマ法など大陸欧州法に精通していたが、判例法に基礎を置く英米法にも親しんでいたからである。
日本国内では「保守」の立場が明確だった田中だが、国際司法では異なる側面を発揮した。南アフリカ等で行われたアパルトヘイトに無批判な欧米の判事たちと闘い、欧米中心だった国連で次第に高まるアジア・アフリカの中小国の発言力に呼応した。国際世論に人種差別への批判を導き入れた貢献は、いま高く評価されている。その外交交渉力には、今日の日本が見習うべきものがある。田中は戦後を代表するインターナショナリストの一人という再評価も成り立つであろう。
ロシアによる「戦闘員と非戦闘員の区別」を無視したウクライナ民間人の虐殺は国際法違反であり、ウクライナによる戦闘行為は、自衛の「正戦」としてキリスト教的な観点からも正当化され得ることなるだろう。改めて「聖戦」と「正戦」の違いを考察するにも、これら3冊は有用だ。











































