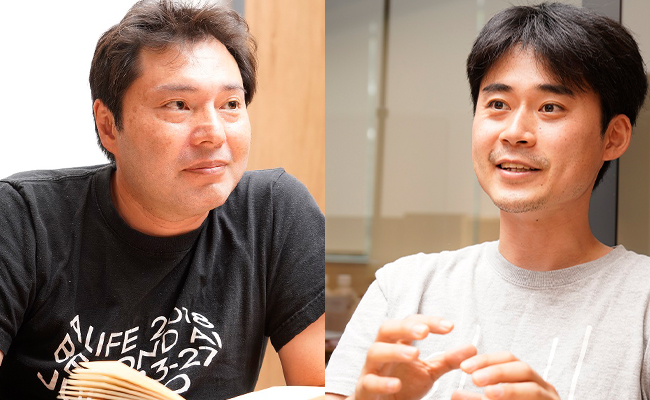
(前篇「300年後に「なめらかな社会」をつくるには」からつづく)
2013年に「スマートニュース」創設者・鈴木健氏の『なめらかな社会とその敵』が刊行された際、大きな話題を呼んだ。それから約10年の時を経て昨年文庫化。そのあいだにも世界の分断は大きく進んでしまった。我々はその現実の前に膝を付くしかないのだろうか。〈ひとりひとりが生きやすい、居場所が見つけられる社会〉という、現実に負けない理想を独立研究者・森田真生氏と語り合った。
***
森田 今回の文庫化まで10年の歳月が流れたわけですが、単行本の刊行当時と比べたとき、現在はどのような心境でいらっしゃいますか。
鈴木 10年前に比べると、危機感が高まっていますね。
たとえば、国際政治の観点から言えば、たった10年のあいだに、こんなにも世界が大きな戦争に向かっていくとは想像していませんでした。いまも、核兵器が使われるのではないかとまでヨーロッパでは議論が始まっていますね。当然、日本もその対象になり得る。状況を見ていると、10年前に比べて圧倒的に冷戦の時代に近づいているように感じます。というよりもむしろ、100年前に逆戻りしているような感さえあります。
100年前というとちょうどスペイン風邪が蔓延して、大きなパンデミックが世界を襲っていました。もう一回歴史が繰り返すのではないかと思わされるくらい、世界はいま急速に分断に向かっている。10年前は、こういう流れがあり得るとしても、もっと時間がかかると思っていた。こんなに早く世界の分断が顕在化するとは思ってもいませんでした。
僕は2014年から、スマートニュースの事業でアメリカに行くようになって、アメリカ50州のうち25州くらいはすでにまわっているのですが、特にアメリカのなかでも、いわゆる保守的な人たちが住むような、アメリカ中心部の、観光ではあまり行かないようなところをロードトリップでまわったんです。ちょうどトランプ旋風が起きつつあるタイミングで、その様子を実際に目の当たりにして、アメリカのなかで分断がすごい勢いで起きているということを体感しました。その後、アメリカ国内だけでなく、世界中で分断が加速していった。想像を絶するスピードで分断が起きているのです。そうした現実を自分の目で見て、300年後のための本とは言いつつも、いまやっていくべきことについてはいますぐにでもやっていかないと、という思いは強くしています。
森田 「なめらかな社会」という理想に対して、現実はまるで反対の方向に、しかも急速な勢いで向かっている。なめらかではなく「ステップ」な世界というのが、10年前よりもますます進んでいる。それでもなお理想を語るということはどういうことなのでしょうか。
鈴木 今回の対談のタイトルは「『分断』の時代にこそ、『理想』を語ろう」ですね。
森田 タイトルを考える際に念頭にあったのは、哲学者の鶴見俊輔さんの言葉でした。今年(2022年)ちょうど鶴見さんの生誕100周年ということもあって、絶版だった本が次々と復刊され、盛り上がっていますが、谷川嘉浩さんという若い哲学者の方が『鶴見俊輔の言葉と倫理』という本のなかで、鶴見さんの哲学を丁寧にひもときながら、重要な指摘をしています。鶴見さんは「本当に現実主義的であるためには、現実主義だけではいけない」と語っていたそうなのです。
鶴見さんは若いときに、「現実的平和主義」を唱えた戦前の知識人の多くが、現実のあまりの複雑さにのみ込まれていった過程を目の当たりにしました。予測不可能で不確実な時代には、夢や理想を語る言葉がやせ細っていく。そして、「現実を見ろ」という声ばかりが大きくなっていく。ところが、現実だけを見るという姿勢が、現実の複雑さのなかで、結果的には現実の受動的な追認へと変質していく過程を目撃したのです。
理想は現実に汚される宿命にあるのだから、冷徹に現実を直視する方が「間違い」の可能性は低い。しかし「現実に徹することは追認をもたらす。むしろ、夢想や想像という『無駄なもの』から、現実の複雑さに押し負けないスタイルが生まれうる」と谷川さんは書かれています。
『なめ敵』でも「現実に汚された理想が、何もない現実に比べてはるかに多くを成し遂げたことを、私たちは歴史の中で知っている」と書かれています。しかし、理想は現実とかけ離れているからこそ、理想の方から現実を違った目で見られる。こうもできるのではないかという突き放した視点で現実を見られることが、あまりに複雑な現実の追認に陥らないために、とても重要なことなのではないかと思うのです。
鈴木 なるほどね。ただ、「現実」という言葉はとても難しくて、おそらく「理想」よりもずっと、難しい言葉だと思うんです。現実というのは、ものの見方と切り離すことができない。現実というのは、かなり多様で、いま森田さんが見ている「現実」と、僕が見ている「現実」は、この同じ部屋のなかにいても違うかもしれない。そうなると、理想を持ちながら社会を見る場合と、そうでない場合とでは、違う「現実」が見えてくる、という方が正確かもしれません。
「制度」という不思議なもの
森田 そういう意味では「現実」という言葉を不用意に使ってしまったかもしれません。僕たちにとって確たる「現実」であるかのように見える物事も、よく考えてみると、ものの見方や、それこそ「習慣」の網によって作られている。このことをきちんと考える場合、この対話のなかでも何度か出てきた「制度」という概念が鍵になってくると思います。
「制度」という言葉は、日常では耳慣れない言葉かもしれませんが、重要な概念なので、僕なりに補足させてください。制度というのは、どこに着目するかでいろいろな定義の仕方があり、たとえばアブナー・グライフは『比較歴史制度分析』のなかで、「行動に一定の規則性を与えるルール・予想・規範・組織のシステム」として制度を概念化しています。制度というのは、人間の行動の規則性に関わる概念である、という点をここでは強調しておきたいと思います。
卑近な例を挙げれば、たとえば、車が左側を走る、なんていうのも、人間の社会的行動に見られる顕著な規則性の一つです。自動車を走らせるときに右側を走ることも物理的には可能なはずで、物理法則は車が右側車線を走ることを禁じていない。にもかかわらず、少なくとも日本の道路を走るときには、誰もが基本的に左側を走ります。ここにも一つの制度があるわけです。
あるいは、講演中に席を変えたり、立ち上がって別の席に移動するようなことをする人はほぼいなくて、人の話を聞いているときは、基本的に同じ席でじっとしている。ここにもまた、自然法則には還元できない行動の規則性があります。こうして考えてみると、僕たちは実に様々な制度の網のなかで生きていることに気づきます。人間は自由な意志で物事を選択して行動できる存在であるはずにもかかわらず、実際には、かなりいろいろな場面で、非常に規則的に行動している。
こうした制度の生成や変容のメカニズムを理解することは、現代の経済学においても一つの中心的な課題になっているそうです。制度は、ひとたび成立すると、人間の行動に高い規則性をもたらすのですが、自然法則とは違うので、実際には常に変化の余地がある。生成するものであり、変化していくことができる。ここが制度の面白いところでもあり、また『なめ敵』の背景にある一つの基本的な認識ですよね。
鈴木 おっしゃる通りです。
森田 ただ、ひとたび成立した制度を変えることは非常に難しい。この本のなかでも、「大草原で空を見上げたり、宇宙から国境のない地球を見下ろしたときに、あるいはロックスターのライブに熱狂しながら、人々のマインドさえ変えれば簡単に実現できそうだと思えることが、現実には一度も達成されたことはない」と書かれています。その気になれば、「人々のマインドさえ変えれば」明日にでもすぐに実現できそうなことが、実際には何十年、何百年も変わらない。それはどうしてなのか。不合理な制度を、よりよい制度に変化させることが、どうしてこんなにも難しいのか。
この問いに簡単な答えがないことはわかっているのですが、あえてここで、なぜ制度はかくも変わりにくいのか、そして、不合理な制度を変えるために、最も必要なことはどういうことなのか、ぜひ現時点でのお考えをお聞かせください。
鈴木 今回は森田さんがどんな難しい問いを投げてくるだろうかと身構えてましたが、そうきましたか。
森田 僕はいつも健さんには、一番聞きたいことを遠慮なく投げかけています(笑)。
鈴木 いま制度について森田さんが説明してくれたなかで、右側通行・左側通行の話が出てきましたので、そこから話を始めてみましょうか。
僕はいま右側通行の国(アメリカ)に住んでいて、日本では左側通行なわけですが、右側通行の国と、左側通行の国と、どっちの方がいい国だと思いますか? おそらく、こう聞かれたら、多くの人は、どっちでもいいだろう、と答えると思います。ゲーム理論では、これを「複数ナッシュ均衡」といいます。
ところが、いったん左側通行になってしまったら、右側を走るのは難しい。自分だけ右側を走ろうとしても、ただ大きな混乱を引き起こすだけです。どっちでもいいはずなのに、いったん決めてしまうと、そうでない行動は取りづらくなる。みんなと別の行動を取ろうとすると、とても生きづらくなる。そういうことが、制度というものには内在している。
制度が生み出す生きづらさの裏には、もちろん、制度が実現する生きやすさもあります。みんなが左側を走っているなら、自分も左を走る方がずっと走りやすい。道路に出るたびに、どっちを走るか考えないといけないよりも、左側をみんなが走ることが制度として成立している方が、ずっと生きやすい。その意味で、制度によって僕たちは生きやすくなる。
そもそも、左側通行と右側通行どっちがいいのかということに決着がつけられれば、みんなにとって生きやすく、生きづらさはこの制度によって最大限取り除かれているのだ、と言えるかもしれないのですが、先ほども言ったように、問題は、どっちの制度の方がいいのか、という優劣をつけるのは難しい場合のほうが多いということです。道路の例は単純ですが、そもそも制度の優劣をつけることが一般的には難しいと言える理由の一つは、複数の制度が絡まり合っているからなんですね。これを、経済学者の青木昌彦さんは「制度的補完性(institutional complementarity)」という概念で非常に明快に論じているのですが、たとえば労働市場において終身雇用的な制度がいいか、それよりもアメリカ的なもっと流動的な市場の方が望ましいのか、という問い自体にはあまり意味がない。それは、労働市場における制度と、金融市場における制度の間の「補完性」を考える必要があるからです。かつての日本の終身雇用制は、金融市場におけるメインバンク制度のようなものと支え合う関係にあった。だから、単体で取り出してきた制度について優劣を比較する、ということにはほとんど意味がないのです。
制度の優劣を決めるのが難しいもう一つの理由は、制度の良し悪しをはかる物差しが一つに決められないということです。制度を評価するにも、多様な評価軸があり得る。そもそも人間の幸せを一次元の指標で測ることは難しい。だから、何か一つの軸に沿って最適な制度を一つ選ぶということはできないのです。
森田 僕たちは無秩序や混沌のなかを生きることはできないので、ある種の「生きやすさ」を支える足場として制度を必要としているが、常に複数の制度の可能性があるなかで、どの制度が最も優れているかということを決めることはできない。だからこそ、もっと他の制度があり得るのでは、現状の制度では生きづらいのでは、という問いが常に残されるわけですね。
制度を変えることができるという自覚
鈴木 社会はなんでこんなに息苦しいのだろうと思うときがありますが、多少は生きづらくても、人間はそこから抜け出して、それなりに自由な場所をだいたい見つけられるものです。ところが、戦争状態になると、この自由がまったくなくなってしまう。息苦しさから抜け出せなくなる。
森田 『万物の黎明(The Dawn of Everything)』という本のなかで著者のデヴィッド・グレーバーとデヴィッド・ウェングロウが、「自由(freedom)」という言葉の起源は、シュメール語で「母への回帰」を意味する言葉「ama(r)-gi」にまで遡れると指摘しています。息苦しいとき、あるいは、自分の身に危険が迫っているときに、そこから抜け出せて、安全な場所、母なる場所へと回帰できる、というのが最も基本的な意味での「自由」なのかもしれません。
鈴木 なるほど、それは面白いですね。
戦争状態になると、すべての価値観の軸が、敵か味方か、そのどちらかだけになってしまう。いまウクライナがまさにそういう状況です。そうなってしまわない限りは、ある程度の自由があります。それでも、戦争状態でなくても、大なり小なり、どんな社会にも、息苦しさというのは残ります。
では、どうしたら息苦しくない社会が作れるのか。世界は複雑なので、この生き方だけがすべて正しいということはもちろん言えない。ある生き方が、ある場所では正しくて、別の場所では正しくなかったりする。そういう世界で僕たちは生きているので、一人一人が、それなりに自由に、自分にとっての生きやすい場所を見つけられる社会をどうしたら作れるのか、ということがポイントになります。
そこで、森田さんの質問に戻ると、制度を無理やり変えていくというのは難しい。いまお話しした通り、制度は互いが互いを縛りあっているので、一つの制度だけをいじっても、もとに戻ってしまう。だから、一つの制度だけに注目して、そこを変えていこうとするのとは別のアプローチが必要です。
そもそも、制度というのはきちんと考えてみると、実はとてつもなく広い概念なんですよね。明文化された法律のようなものだけが制度なのではない。究極的には、「人間が生きているときに互いに期待し合っているもの」は何でも制度だと考えることができる。
森田 互いの期待が一致しているということは、そこから生成する行動に規則性があるということですからね。
鈴木 そうすると、明文化されたルールや規制のようなものだけでなく、言語化されていない習慣やタブーや慣習的な行動など、いろいろなものが制度だということになる。
そういう意味での制度を、どう変えていったらいいのかといえば、究極的には、一人一人が、「ああ、制度というのは、そういうものなんだな」ということを認識する、自覚することからだと思うんです。与えられたものを与えられたまま受け取るのではなくて、なるほど、そういう条件があって制度というものは動いているのだな、だから、いつでも自分たちの力で、それを変えたり、よりよいものにしていくことができるのだな、という感覚で生きるということ。実はこれこそがデモクラシー、つまり、民主主義というものの本質だと僕は思っているのです。
偉い人が言っているからという理由だけで与えられた制度を受け取るのではなくて(もちろん、偉い人が、本当に偉いことを考えている場合は少なくないのだけど)、それが本当に自分たちにとって幸せになっているのか、よいことなのか、ということをあらためて自分で考えて、本当にこれで居心地がいいだろうか、と自分に問うてみること。そして、自分の感覚に正直になること。
どこか居心地が悪いなと思ったら、「居心地が悪いです」と言える、ということが大事ですよね。これが言えなくなる社会はすごく厳しい。かなり居心地が悪いですよね。なので、まずは言えることが大切です。
その上で、居心地の悪さをみんなに相談できる必要があります。もっと居心地よくしていくことができるのではないかと提案し、相談し、みんなで考えていく。それがデモクラシーです。
森田 なるほど。
鈴木 このことを発見したのが、トクヴィル(1805-1859)というフランスの思想家でした。彼はフランスの思想家ですが、フランスではなくて、アメリカでデモクラシーを発見したのです。
現代のデモクラシーは、アメリカで発展したデモクラシーが起源です。しかし、それにアメリカ人は気づかなかった。アメリカにとっては外国人であるトクヴィルが、たまたま調査でアメリカをまわっていたときに気づいたんですね。アメリカ人は、制度を自分たちで変えている。自分たちの町は自分たちでよくしていこう、そのためにみんなで考えて、みんなで相談する、そういう文化がある。これこそがデモクラシーなのだと、彼は発見したのです。これを「タウンシップ・デモクラシー」といいます。
だから、国の大きな政治ではなくて、小さな町だとか、小さなお寺だとか、そういう小さなところから、どうしたらもっとよくなるのかということを考え、相談し、実行していく。その流れを重ねていくことによって、いつしか大きな制度を変えられる。そういうことだと思うのです。
森田 制度を変えていくというのは簡単なことではなくて、トップダウンで政策を変えたり法律を書き換えたりするだけでは変わらない。たとえばもしいま道路交通法を誰かが書き換えて、いまから右側通行ですよというふうに、法律が変わったとしても、外に出て、左側を走っている車ばかりだったら、普通に自分も左を走りますよね。法律が書き換わった瞬間に行動が変わるかというとそうではない。つまり「制度=明文化された法」というほど単純ではない。
では制度の核心にあるのは何かといえば、先ほどおっしゃった通り、一人一人が心に抱いている期待、あるいは予想(belief)が制度の核にある。みんなが左を走るだろうという予想があるからこそ、みんなが左を走るという行動が生成してくる。逆にいえば、制度が変わるときとは、みんなが何を信じ、何を予想しているのかが変わるときです。しかしそれがどうやって変わるのかは難しい。
そもそも制度がそういうもので、みんなの期待によって形成されているものなのだから、自分が何を期待するか、自分が何を予想し想像するかで制度は書き換え可能だし、自分たちがコミットしている制度は、いままさに自分たちが何を信じるかによって生成しているのだという感覚をより多くの人が内面化することによって、より制度は変わりやすくなるのだ、ということですね。
鈴木 社会の仕組みはさまざまなので、良し悪しではなくて、複数の仕組みが共存できるようにするためにはどうすればいいかを考えていく必要があります。そうでないと、一つの社会制度に収束していくことが正しいよね、ということになりかねない。それがあまりにも強いと、唯一正しい社会制度以外の制度は敵である、というふうになってしまう。それは、すごく危険な状態です。
そういう意味では、理想には、二つの種類があると言えるかもしれません。一つは、誰にとっても理想的な社会がある、だからそれを実現しましょう、というタイプの理想。もう一つは、誰にとっても理想的な社会なんてないのだから、様々な社会が共存できるようにするにはどうすればいいか、と考えていくような理想です。
森田 分断の時代にこそ、後者の意味での理想を追究していく必要がありますね。
加速する分断と、未来への種子
鈴木 そもそも本書の原点にあるのは、少年時代に目撃した、ベルリンの壁の崩壊でした。僕はこのとき、たまたまドイツに住んでいたのですが、ベルリンの壁が崩壊する5ヶ月前に、実際に自分の目でこの壁を見ました。ベルリンという街の真ん中に、まさに分断を象徴する物理的な壁が立っていて、その東側と西側とでは、家族も親族も往来できない状況でした。
僕が訪れる4ヶ月前に、東ベルリンの若者が、西ベルリンに脱出しようとして、胸を撃たれて、亡くなった。その9ヶ月後に壁が崩壊したのです。そうしたら、東ベルリンの人たちが、簡単に西ベルリンに入れるようになった。家族と会えるようになったのです。
そこから30年、基本的には自由で民主的な国家というものが世界中に広がっていくというふうに、西洋の人たちは信じていました。ロシアも民主化され、中国も、より民主主義と親和的な制度になっていくだろうと期待されていた。ところがこの10年くらいで、すべての国が自由で民主的な国になっていくという幻想は、脆くも崩れ去ろうとしています。
ヨーロッパではいま非常に大きな戦争が行われていて、ロシアはウクライナを直接的に軍事攻撃している。他方で、ウクライナには、ヨーロッパ及びアメリカ側が武器を供給していて、代理戦争のような状況になっている。さらにいま、プーチンが追い込まれているなかで、核兵器をウクライナで使うという可能性をちらつかせながら、アメリカ及びヨーロッパを撤退させようとしている。
アジアをみると、中国、北朝鮮、ロシアに挟まれているなかで、将来的に戦争になるリスクは高いと考えられています。10年前にはそう思われていなかったのに、いま急速に、極めて大きな分断が世界規模で起きている。
アメリカに関していえば、国内でも大きな分断が生じています。デモクラシーの母国であるにもかかわらず、分断を言葉だけによって解決するのはもはや不可能である、したがって、相手を力で封じ込めなければならない、というふうに、対立する陣営が相互に思い込んでしまっている状況があります。一部ではすでに暴力が勃発していて、アメリカ議会が2021年の1月に襲撃され、占拠される事件がありましたし、つい先日も、ペロシ下院議長の自宅に暴漢が現れ、夫が頭を殴られる事件がありました。もう言葉で解決する時代は終わった、これからは暴力の時代である、とアメリカの一部の人たちは本気で信じ始めている。これも非常に大きな分断です。このような時代に、いかに理想を持つか、というのは極めて難しい問題です。
『なめ敵』のタイトルのもとになった本として、哲学者カール・ポパーが書いた『開かれた社会とその敵』という本があります。そこでポパーは、自由で開かれた社会を作るためには、そうでない社会を否定しなければならない、ということを語っています。しかし、僕らの時代は、同じことを繰り返すのではなく、自分とは違う考えだとしても、そうした社会と共存していくためにどうすればいいかを考えていかないといけないと思います。自分たちと異なる制度を、全否定するのではなく、極めて多様な民主主義の考え方や捉え方があるのだということを受け止めた上で、互いが互いに影響を与え合っていくということが成立しないと、また悲劇的な事態が起きてしまう。
森田 いまこの季節は、ドングリがどんどん落ちてくるので、子どもたちは大喜びです。もちろん木は子どもたちを喜ばせるためにドングリを落としているのではなくて、あくまで生命を次世代へと繋いでいくために、ドングリを落としているわけですが、それをリスが拾ったり、カラスが拾ったり、あるいは子どもたちが拾ったりして、未来のために落とされたドングリが、そこに集うたくさんの生き物たちに、思わぬ仕方で恵みとなっていく。本来の目的や機能とは関係のないところで、何かが誰かの役に立ってしまったり、恵みとなっていたりするというのが、生命が繋がりあった生態系の面白いところです。
健さんの思考は文庫にもなり、あちこちに種子としてまかれていくことと思います。こういう世界にしたいと目指す理想を人に押し付けたり、一つの考えで周りを制御したりするためではなくて、ドングリのように、誰かが拾ったり、面白いなと思ったりして、考えたり、疑問に思ったり、批判したり、あるいは書き換えたりしながら、新たな思索と探究、そして実験が始まる種子になっていくのだと思うのです。
冒頭におっしゃっていたように、僕たちはいろいろな生き物や人間とのご縁に支えられて生きています。やはり生きていく以上は、自分が少しでも誰かの役に立つことができたり、自分の生きていることが誰かにとっての恵みをもたらすことができたらと思います。僭越ながら、健さんの魅力は、全力で思考しているその思考が、自他共に役に立ちますように、誰かにとって恵みとなりますように、という願いに貫かれていることです。ただ頭がいいということではなくて、いつも、誰かの生きることを少しでも楽にできないか、誰かの生きづらさを少しでもやわらげることができないかと、そういう慈悲の心に裏打ちされた思考が、そこにあると思うのです。(了)
(「新潮」2023年4月号より転載)
(構成・森田真生)
鈴木健(すずき・けん)
SmartNews創業者、代表取締役会長兼社長 CEO。1975年、長野県生まれ。98年慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。2009年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。東京大学総合文化研究科特任研究員。著書に『なめらかな社会とその敵』など。専門は複雑系科学、自然哲学。
森田真生(もりた・まさお)
1985(昭和60)年東京都生れ。独立研究者。京都に拠点を構えて研究・執筆のかたわら、国内外で「数学の演奏会」「数学ブックトーク」などのライブ活動を行っている。2015(平成27)年、初の著書『数学する身体』で、小林秀雄賞を最年少で受賞。他の著書に『数学の贈り物』『計算する生命』、絵本『アリになった数学者』、編著に岡潔著『数学する人生』がある。









































