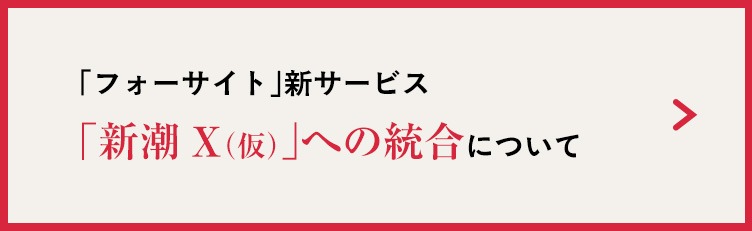都市部の医療が崩壊しつつある。2024年度、東京都内の病院の約7割が赤字に陥り、吉祥寺南病院など地域の中核病院が診療を休止した。兵庫県伊丹市の近畿中央病院は、運営する公立学校共済組合が赤字を理由に、2027年度に予定されていた市立病院との統合を待たず、2026年3月以降の診療休止を決定した。
公立病院も状況は変わらない。週刊ポストが2026年1月2・9日合併号に掲載した「足下に迫る医療崩壊 地域別経営不安の赤字病院リスト120」という記事が興味深い。編集部は全国の2023年度の公立病院の経営状態を調べたが、最も赤字が多かったのは東京都立多摩総合医療センターで約89億円だった。次いで、都立墨東病院(約86億円)、都立小児総合医療センター(約79億円)、都立駒込病院(約76億円)と続き、トップ10は全て首都圏の病院だった。内訳は東京7、埼玉2、千葉1である。
苦境は病院だけではない。2024年、医療機関の倒産は64件と過去最多を記録した。休廃業・解散も722件に達し、こちらも過去最高を更新した。とりわけ深刻なのがクリニック(診療所)で、休廃業・解散の約8割を占め、大半が東京・大阪・名古屋など都市部に位置していた。
診療報酬で無視されている都市部と地方のコスト格差
都市部の医療機関の閉鎖は、医師不足が原因ではない。患者がいない訳でもない。住民は地域医療の充実を望み、医師も十分にいるのに病院の経営が立ち行かないのだ。
なぜ、こんなことになるのか。それは、厚生労働省が診療報酬を全国一律に定めているからだ。都市部と地方では、家賃や人件費には大きな差があるのに、診療行為に対して支払われる診療報酬は同じだ。
都心部の病院が経営できるレベルの診療報酬を設定すれば、地方の医療機関は大儲けする。国が払うので、取りっぱぐれもない。この仕組みが地方の医者を金持ちにさせた。高度成長期の開業医や病院経営者のイメージだろう。
こんなやり方は長続きしない。診療報酬を抑制すれば、都心部の医療機関から経営破綻するのは当然だ。まさに、現在、起こっていることだ。
日本の医療を持続可能にするには、病院の赤字を補助金で補填する弥縫策ではなく、公的医療の仕組みを抜本的に見直さなければならない。高齢化社会で医療が重要なことはいうまでもない。我々に残された時間は多くない。
日本の医療の最大の問題は、医療システムを循環する資金の絶対量が不足していることだ。政府もメディアも、この点を取り上げることはまずないが、議論の前提として非常に重要だ。
実は、我が国の医療費は少ない。医療費の対GDP(国内総生産)比は10.6%(OECD『図表でみる医療2025』)であり、G7の中ではイタリア(8.4%)に次いで2番目に低い。
一方、高齢化率は29%とG7で突出している。通常、高齢化に伴い必要な医療費は増えるから、これは異様だ。高齢化率が23%のドイツ並みの財源(対GDP比12.3%)を確保しようとするならば、10兆円規模の追加財源が必要となる。
今回の診療報酬改定で、診療報酬本体は3.09%引き上げられた。「30年ぶりの大幅な引き上げとなる。厚生労働省の求めた数字を高市早苗首相がそのまま採用した」(日本経済新聞2025年12月24日)など批判的な論調が目立つが、これは的を射た見解ではない。
この程度の引き上げで増加が期待される医療財源は1.5兆円程度にすぎない。全く足りず、問題の解決にはならない。もっと財源を積まなければならないのだ。
日本維新の会も「しがらみ」を断ち切れないのか?
すぐに思いつくのは、保険料率を上げることだ。ただ、それは難しい。我が国の国民皆保険制度は、現役世代が支払う保険料や税で、高齢者の医療費を賄う賦課方式で運営されているからだ。
2025年12月24日、朝日新聞は一面トップで、「出生66万人10年連続最少」という独自推計の結果を報じた。今後も減少する現役世代だけに負担を負わすことは現実的ではない。
政府も、このことは認識している。高所得の高齢者には3割負担や保険料増額を課し、若年世代の負担を減らそうとしている。ただ、これも弥縫策だ。高額療養費の負担増で増える財源は数百億円程度に過ぎない。また、政府にとっては負担減でも、医療機関にとっては支払い者が変わるだけで、経営改善にはつながらない。
東京や大阪の医療機関の経営が立ち行かないなら、全国一律の診療報酬単価を改め、地域差を導入すればいい。
これは誰でも思いつくことだ。国民皆保険制度導入時、政府もそのつもりだった。診療報酬が「1点10円」で計算されるのは、その名残りだ。東京を11円に上げることは制度上は可能なのだ。
ただ、これには政治的な困難が伴う。地方から都市部へ医療費を再配分することを意味するためだ。2009年の民主党政権誕生時に医療政策に大きな影響力を持ったのは、仙谷由人氏だった。筆者は、仙谷氏に都市部の診療報酬を上げることを提案したが、「それは無理」と却下された。その理由として、仙谷氏は「国民皆保険制度のもと、地方の開業医は金持ちになり、自民党に限らず、全ての政治家の後援会の幹部には、高校の同級生のような医者が名を連ねているから」と説明した。
残念なことに、今回、与党となった日本維新の会からも、そのような提案は出てこない。維新は大阪という大都市に強固な支持基盤を持ち、日本医師会との関係は薄く、配慮する必要はないはずだ。さらに梅村聡議員や阿部圭史議員をはじめ、医療政策に精通した議員もいる。
梅村氏は、大阪大学医学部を卒業した内科医で、民主党政権では厚労大臣政務官を務めた。私とは、2007年の初当選以来の付き合いだ。私どもの研究室で、彼の国会質問を一緒に作ったこともある。優秀な人物で、本稿で述べる内容は送っている。
阿部氏は、北海道大学を卒業した医師で、厚労省医系技官も経験した。大学時代、我々の研究所で学んだこともある。最近の付き合いは少ないが、診療報酬制度の問題は熟知しているはずだ。
それでも、彼らからこのような訴えが出ることはない。何かに配慮しているのだろう。このような状況を知ると、与野党を問わず、政治の力で診療報酬制度を見直すことは期待できないと感じられる。
「大企業の関連病院」という都市部医療の担い手
都市部の医療を守りたければ、保険料だけでは足りない財源を、東京や大阪が独自に調達するしかない。前出の週刊ポストの記事は、このような現状を示している。都立病院の大赤字を東京都は一般会計からの支出で埋めている。
東京都のみならず、港区や中央区など特別区の中にも、強い財政力を有する自治体がある。戦時中の戦費調達のために、内務省が東京市を解体したという経緯もあり、特別区の権限は弱く港区や中央区は区立病院を運営していない。だが、この地域には大学病院や大病院は多くあるが、住民が気軽に受診、入院できる中小病院はない。この「医療過疎」に歯止めをかけるなら、特別区も医療に参入することを検討すべきだ。東京都よりも小回りがきき、きめ細かいサービスを提供できるはずだ。
また、大企業が拠点を置く東京や大阪は、“民間”も元気だ。彼らが医療システムを支えればいい。富裕層も存在する。
現に、一部の企業は地域医療を支えている。その一例が三井記念病院だ。三井グループの支援で設立された総合病院で、一般財団法人三井記念医学財団が運営する。東京大学の関連病院でもあり、高度医療の貴重な担い手として神田周辺の地域医療を担っている。いわば、三井グループがこの地域の住民の健康を支えていることになる。
同院は、2017年の決算で債務超過に陥った。この時、「三井グループが協力して病院を救済した」(三井記念病院に出向していたグループ企業社員)ことは、医療関係者の間では有名だ。当時、三井記念病院の累積損失は約142億円、2億5400万円の債務超過だった。負債は一つの病院としては大きいが、三井グループとしては微々たるものだろう。大企業にとっては、病院の赤字は軽微といえるレベルだ。
都内には、このような企業の関連病院として、JR東京総合病院やNTT東日本関東病院などがある。大阪にも松下記念病院や住友病院がある。トヨタグループも、トヨタ記念病院を運営している。JR東京総合病院やNTT東日本関東病院など病院が別法人でなく企業の一部門である場合には、病院の赤字は福利厚生費や損金として処理できるため、企業側の実質負担は限定的だ。税務上の合理性も高いのだろう。
このような病院は、母体企業の資本力と経営規律を背景に、安定した運営を維持してきた。最近も、このような病院の経営が傾き、病院閉鎖を検討しているという話は聞かない。
なぜ、民間企業の医療進出が増えないのか。医療の非営利性を錦の御旗に、厚労省が株式会社による新たな病院経営を認めていないからだ。確かに、米国では営利企業の病院経営が大きな問題となっている。ただ、それは運用次第だ。
ソフトバンクや楽天などのIT企業が病院経営に参画すれば面白いだろう。政府は、医療DXを推進しているが、IT企業が自前の病院でその「開発」を推進すれば、一気に可能性が開けるはずだ。
医療現場なしではあり得ない製薬企業のビジネス
医療への株式会社の進出を議論するにあたり、忘れてならないのは、製薬企業だ。医療機関の経営難を脇目に、国内製薬企業は巨額の利益を上げている。2024年度、国内主要製薬企業10社の営業利益は約1.9兆円に達する。ちなみに、同時期の大学病院の赤字総額は約500億円だ。
これは国内製薬企業の開発力が高かったからではない。利益の多くが円安による薬価差益だ。例えば、武田薬品工業が公開している財務諸表によると、同社は為替影響により売上で1961億円、営業利益で559億円の押し上げ効果を得ている。中外製薬の為替差益は、営業利益で764億円だ。
利益は投資家に還元される。配当性向は、武田薬品工業が287%、アステラス製薬が261%という異常とも言えそうな値を記録している。物価高で多くの国民や病院が赤字に苦しむ中、製薬企業は巨額の利益を上げ、投資家の懐をあたためている。
製薬企業のビジネスは、医療現場なしではあり得ない。小野薬品工業を急成長させたオプジーボのような革新的な創薬は、大学病院による基礎研究に支えられている。しかし、彼らが上げた利益は医療現場に還元されていない。彼らの利益の一部を大学病院に還元されるだけで、その診療力や研究力は高まるはずだ。
医療システムにおいて、製薬企業のような存在は枚挙にいとまがない。検査会社、医療機器メーカー、電子カルテメーカーなど、巨額の利益を上げている。
このような状況になるのは、厚労省の基本的思考を反映している。厚労省は医療費は社会的コストで、できるだけ安い方がいいと考えているし、医師の診断や説明より、薬や検査を尊重する。
このことは厚労省が定める診療報酬を調べれば一目瞭然だ。医師に診察に対して支払われる初診料と再診療は、それぞれ2910円と750円だ。心肺停止患者に対して実施される心臓マッサージに至っては約3000円だ。
一方、血液検査は約3500円、MRIは約2万円、オプジーボの点滴は1回当たり約50万円だ。人命救助に直接的に関わる心臓マッサージの価格は、オプジーボの167分の1で、街中のマッサージ店より安い。
医療機関が収益を上げようとすれば、患者の話をじっくり聞くより、3分診療で済ませ、検査や投薬を増やすしかない。
ただ、検査や薬代の収益の大部分は、検査機器の初期投資、メンテナンス料、薬の購入費として検査会社や医療機器メーカー、製薬企業に支払われる。医療機関が得るのはごく僅かだ。これが医療関連産業が栄えて、医療機関が滅ぶ理由だ。
厚労省は懲りていない。2026年6月の診療報酬改定で、眼科や整形外科の診療報酬を抑制する方針だ。この診療科の医療費が伸びているためだ。
高齢者の「医療消費」開拓は悪ではない
こんなことをしているから、日本の医療は衰退する。医療費が増えているということは、需要があるということだ。高齢化に伴い、白内障や膝関節症の患者は急増し、手術によりQOLは劇的に改善する。90代でも手術を希望する患者がいる。このあたり、一定の年齢を超えると、手術を希望しない患者が増えるがんや心臓病の治療とは対照的だ。
眼科や整形外科は「成長領域」だ。政府は、この分野の発展を後押しすることはあっても、環流する資金を抑制してはならない。いかにすれば、国民負担を上げずに、成長するか考えるべきだ。
幸い、白内障や膝関節症は、がんや心臓疾患のように命には影響しない。一定レベルの治療を国が保証して、それ以上の治療行為は自由診療として認めることに国民は反対しないだろう。
このような付加的医療行為に、どの程度の金を払うかは患者次第だ。病院は自由に価格を決めればいい。これまで診療報酬は、厚労省が算定するコストプラス最低利潤という枠組みで計算されてきた。価格決定の議論が幼稚だった。相手の満足度を高め、価格に添加することを検討したことはなかった。これでは収益は期待できない。
混合診療規制を緩和することで、眼科や整形外科などの領域で、「医療消費」という経済活動が発展するだろう。患者が満足しながら、医療機関は収益を上げるはずだ。この辺り美容整形と似ている。
幸い、東京や大阪には富裕な高齢者が多数住んでいる。彼らの資産は大きく、最大の関心は健康だ。彼らが満足するサービスを開発し、収益を上げることで病院経営は改善するはずだ。これは眼科や整形外科に限った話ではない。孤独死対策などの周辺サービスも、医療機関は提供できるはずだ。このようなサービスを開発すべく、医療機関が試行錯誤を繰り返すことが、日本の医療の競争力を高める。
もちろん、厚労省や日本医師会をはじめとした業界団体、さらに医療業界誌は、保険診療と自由診療を原則として併用不可とする「混合診療規制」の緩和に大反対するだろう。診療報酬の統制は、彼らに大きな権限と利権を与えてきたからだ。混合診療の普及を、彼らは自らの権限、利権を脅かすものと感じている。
ただ、もう、そんなことを言っている余裕はないはずだ。都市部の医療は急速に崩壊している。持続可能な医療システムの構築に向けて、そろそろ本気で議論すべき時期が来ている。