
ラース・チットカ『ハチは心をもっている』(みすず書房、今西康子訳、2025年)には、まさかハチにこんなことができるとは! と何度も驚かされた。
たとえばマルハナバチは、机とアクリル板の間に挟まれた直接触れることのできない造花(砂糖水が仕込まれている)を、その造花に付いた紐を引っ張り、手前に寄せられるか(そして砂糖水を吸えるか)という実験。紐を引っ張る訓練を重ねると、多くのハチがこの課題を習得できたことにも目を見張るものがあるが、未習得のハチが熟練のハチが紐を引く様子を観察しただけでその技術をコピーできたという事実にはさらに強い衝撃を受ける。自然界のハチが、紐を引っ張ってエサにありつくようなシチュエーションに遭遇することは考えにくい。だが、彼らには未知の課題に対して柔軟に解決策を構築する認知能力が潜在的に備わっているらしい。
本書が示すのは、こうした行動は決して例外的な「芸」ではなく、ハチが世界を認識し、記憶し、推論する存在であるという事実である。色、形、匂いだけでなく、電気的な痕跡を使って訪問済みの花かどうかを見分けるなど、採餌の戦略を立てたり、状況に応じて行動を変えたりする。その姿は、知能は大きな脳を持つ動物の専売特許だと見なしてきた我々の思い込みを覆す。
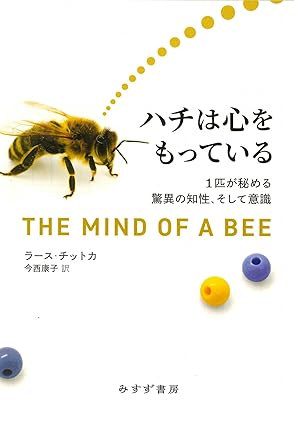
IoT(Internet of Things:モノのインターネット)といえば、工場設備や家電、都市インフラにセンサーを設置し、ネットに繋ぐ技術である。それでは「動く物」、すなわち動物にセンサーを取り付け、追跡すると何が見えるだろうか。
人工衛星や超小型GPSセンサーを活用し、渡り鳥、大型哺乳動物、海洋生物、昆虫などを地球規模のネットワークで繋ぐプロジェクト、名づけてICARUS(イカロス)を率いているのがドイツの生態学者マーティン・ヴィケルスキ氏であり、その計画に至る歩みを記したのが『動物たちのインターネット』(山と溪谷社、プレシ南日子訳、佐藤克文解説、2025年)だ。
常時のモニターにより、たとえば渡り鳥は遺伝的な本能だけで移動するのではなく、時には別種の鳥とも鳴き交わして高度や行き先を「相談」し、ベテランから知識を学ぶという。群れから外れ、常識外れのルートを選び、あえて人間の生活圏にとどまる個体もいるらしい。知的ネットワークもまた人間の専売特許ではない。
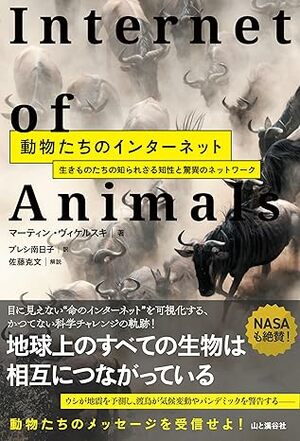
人間自体にも、未知の領域はまだまだあることを教えてくれるのが、石井優『硬くて柔らかい「複雑系」 骨のふしぎ』(講談社ブルーバックス、2025年)だ。骨は硬く、変化しない構造物のように見える。しかし実際には、日々壊され、作り替えられ、力のかかり方に応じて形や内部構造を変えていくという。
骨を壊す破骨細胞は無作為ではなく「老朽化」を認識し、移動し、狙いを定めて破壊活動を行い、骨折の修復時などには、骨を作る骨芽細胞と連携する。その巧みさは知性すら感じさせるほどだ。その様子を、最先端の技術で可視化しているところが本書の白眉。
骨はカルシウムやリンの貯蔵庫の役割も果たすが、著者はその理由を、生命が海から陸へ進出する過程で獲得した進化の政略と読み解く。つまり、重力に抗う支柱であると同時に、海水から安定して得られなくなったミネラルを体内に蓄える骨は、生物にとって一石二鳥の仕組みだという。我々の身体がいかに巧妙でダイナミックなシステムでできているかがわかる。

無数のセンサー、顕微鏡や望遠鏡など可視化技術により、我々はより細かく現実を見ることができるようになった。我々人間も日夜せっせと(この書評も含めて)文章や数字を生み出している。こうして生み出され、コンピュータに供給されたデータを使い、複雑な現象を分析したり、将来何が起こるか予測したりするために世界を計算可能な形に置きかえたものが数理モデルだ。近年急速に普及してきた生成AI(人工知能)も数理モデルの一種である。数理モデルが社会の、あるいは個人の意思決定に果たす役割は大きい。
だが、エリカ・トンプソン『数理モデルはなぜ現実世界を語れないのか』(白揚社、塩原通緒訳、2025年)は、気候変動、感染症対策、金融予測などで多用される数理モデルが、しばしば客観的な事実と混同され、過度な信頼を寄せられていると警鐘を鳴らす。数理モデルには必ず作成者の主観的な価値判断や偏見が埋めこまれる。だからこそ我々は数理モデルが描き出す単純化された世界「モデルランド」から脱出しなければならないと説く。
著者はモデルを否定するわけではない。大事なのは、モデルに潜む作成者の世界観を欠陥ではなく特徴と認識した上で、データの不足やモデルの構造から生じる不確実性を透明化すること。そしてモデルを単なる予測エンジンではなく思考の補助やメタファーとして捉え直し、専門家の知見や多様な視点を積極的に取り入れることだという。

データの氾濫、数理モデルの乱立で複雑化した世界と向き合うのに役立つのが科学的思考だ。吉田伸夫『この世界を科学で眺めたら』(技術評論社、2025年)を読むと、科学が完成された体系ではなく、試行錯誤の営みであることがわかる。
著者は量子論や相対論を平易な言葉で語る書き手として知られる。筆者もその種の分野の研究者を取材する際、吉田氏の著作の数々から基本的な知識を得てきた。といっても本書が力点を置くのは難解な物理理論そのものよりは科学的なものの見方、すなわち仮説を立て、疑い、別の可能性を考え、安易な答えに飛びつかない態度を日常の出来事や社会問題にどう応用するかである。
指を少し湿らせると紙をめくりやすいのに、大雨が降ると自動車がスリップしやすい。言い換えると、同じ水でも少量だと摩擦を増やすのに、大量だと摩擦を減らすのはなぜか。「無秩序さが増大する」というエントロピーの法則があるのに、生命のような秩序が生まれるのはなぜか。地平線の月が大きく見えるのはなぜか。身の回りのあちこちに科学の種はある。数々の種に注意を向け、小さな疑問も見過ごさず、丁寧に育てていく。その先に、難解な理論を攻略する道も拓けるわけだ。











































