
10年ほど前、当時80代後半でなお矍鑠たるご老人に「一番オススメの健康法は?」と訊ねたことがある。「毎朝の散歩」という普通の答えに筆者は驚いた。その人が健康グッズ、健康食品を紹介する雑誌を多数出している出版社の社長だったからだ。「散歩」ではたぶん商売にならない。それでも勧めるのならよほど効果があるのだろうと、以来、筆者も散歩する機会を増やした。
ジェレミー・デシルヴァ(赤根洋子訳)『直立二足歩行の人類史 人間を生き残らせた出来の悪い足』(文藝春秋、2022年)によれば、歩行には健康促進のみならず、創造性の増進、記憶力の改善、うつ病・不安神経症の緩和などの効用があるという。
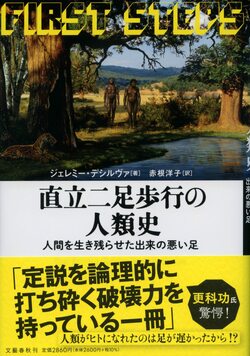
といっても本書の主たるテーマは健康法ではない。題名の通り直立二足歩行である。初期人類はアフリカの草原に進出し、軽く握った拳を地に付けて歩く「ナックルウォーク」をしていたところから徐々に上体を起こして直立するように進化したというのが従来の学説。筆者も人類はチンパンジーやゴリラのようなナックルウォークから二足歩行に移行したと当たり前のように考えていた。ところが、実際は逆だったらしい。
近年の化石研究に基づけば、類人猿と初期人類の共通祖先は、草原に進出する以前から森の木々の上を直立二足歩行していたという。その後、ナックルウォークするように進化したグループと、直立二足歩行にさらに適した骨格に進化し、草原の環境に適応した初期人類とに分岐。直立二足歩行は四足歩行よりも遅く、初期人類は単独では肉食動物に負ける。だが集団体制や道具使用でそのデメリットをカバーし、捕食されにくくなる。そうして生まれた余剰エネルギーで脳が成長し、世界中に進出した。今年もコロナ禍で外出が少なめだった筆者に、歩行の健康的な意義を改めて教えてくれただけでなく、人類史的な意義まで気づかせ、もっと歩かねばという気持ちを奮い立たせてくれた一冊である。
直立二足歩行の偉大さにいい気になっていた筆者に冷や水を浴びせたのがブライアン・バターワース(長澤あかね訳)『魚は数をかぞえられるか? 生きものたちが教えてくれる「数学脳」の仕組みと進化』(講談社、2022年)。数を数える、計算するといった行為は高度で、人間にしかできないように思える。ところが、ライオンやクジラなど他の哺乳類だけでなく、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、果ては微生物までほとんどあらゆる生き物が数え、計算までしているらしい。
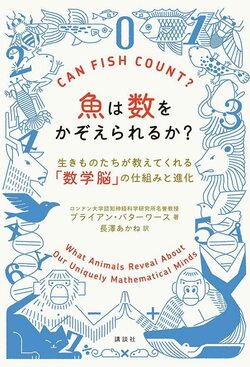
群れに含まれる個体数、エサの量、あるいは特定の鳴き声をくり返す回数など、たしかに生物はしばしば数を数える必要に迫られる。数を操作する能力は生存や生殖にとっての有利不利に直結するのだ。地磁気を感知し、脳内に広範囲で詳細な地図を作って地球規模の渡りをする鳥、カメなどの計算能力には驚かされる。
生物が数を利用できるのも、宇宙が数学的構造を備えているからなのだろう。須藤靖『宇宙は数式でできている』(朝日新書、2022年)は、一般には毛嫌いされる数式をあえて載せる。その狙いは読者をビビらせることではなく、芸術作品のように鑑賞し、数式が表現する物理法則が現実世界を支配していることを示すところにある。アインシュタインが作った一般相対性理論の基礎方程式による計算は水星軌道のごくわずかなズレを説明し、光の湾曲を予言して観測値と恐るべき精度で一致する。いくら数学脳を生物全般が共有しているといっても人類(の一部)が到達したレベルには及ばないだろう。

科学はキレ味よく未来を予測し、謎を解き明かす。だが、その本来の威力を発揮しにくい分野もある。大野智『民間療法は本当に「効く」のか 補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー』(化学同人、2022年)で論じられる民間療法もその一つ。多くの人が使っているならと同じものを選ぶ人が増える「バンドワゴン効果」、治療費を無駄にしたくない故に効いているはずと思いこむ「サンクコストの呪縛」、都合のよいことを覚え、記憶をすり替える「思い出しバイアス」、あるいは「権威への服従心理」などがあるため、人は元々欺されやすい。

どう対処するか。本書は、正確な情報を「入手」し、医学的な視点で「理解」し、情報が信頼できるか批判的に「評価」した上で、「活用」すべし(意思決定を行う)と説く。なかなか実践するのは難しそうだが、具体例として、「膝の痛みにグルコサミン」「風邪の予防にビタミンC」「がん患者にヨガ」にそれぞれどの程度の効果があるのか4ステップを適用し、検証しているのが参考になる。
医師でもある著者は民間療法を頭ごなしに否定すべきではないという。患者には医療への不信感がある。だからまずは患者の話を聞けというのだ。科学至上主義に傾きがちな筆者には耳の痛い指摘だが、同意せざるを得ない。宗教や政治など分断が進む他の領域でも活用すべき教訓が本書には含まれている。
宗教や哲学のテーマとして扱われることの多い「なぜ死ぬのか」という問いについても上記の最初のステップ、正確な情報の「入手」からはじめるのがよいだろう。その手引きとして、更科功『ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか 生物の死 4つの仮説』(新潮選書、2022年)を勧めたい。本書は生物学の視点から、〈単なる事実としての「死」を考察〉している。

死を説明する仮説の一つは、種の利益のため、老いた個体が死ぬとする「種の保存説」だ。老醜をさらすより潔く若い世代に道を譲りたい気持ちをくすぐる説で、筆者もこれが正しいのだろうと素朴に考えていたが、現代の生物学ではほぼ否定されているという。それではなぜ死ぬのか。身も蓋もないが、その答えは、自然淘汰が働くからというもの。進化の結果、生物は死を獲得したらしい。個体には迷惑な獲得に思える。しかし死がなければ我々は今のように地球環境に適応できなかった。
時間的、空間的スケール次第で、生きている状態と死んでいる状態が変わって見えるという。一般にウイルスは無生物とされるが、感染して乗っ取った細菌まで含めれば生物に見えるし、歴とした生物である大腸菌も、冷凍保存されて細胞分裂をしない状態は死んでいるように見える。どの視点で見るかによって生と死は変わるのだ。












































