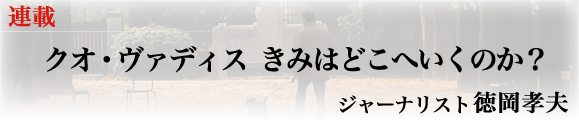軍事政権によって長期軟禁されていた間は「聖女」だったが、自由を得てからのスー・チーは「普通のオバサン」になってしまった、という新聞の評を見た。
驚くに足りない。押す力があってこそ反発する力が生まれる。突っかい棒を外された戸は自由に開閉する普通の戸になり、劇的なものがなくなる。
日本人は竹山道雄の『ビルマの竪琴』があるから、概してミャンマーに好意的である。そこへいま日中関係が悪化した。軍事独裁を緩めたミャンマーを見て「労賃の安い新工場が天から降ってきた」と安易に喜んだ経営者が多いのではないか。
万事に疑い深い私は、そんな簡単なもんやおまへんで、と呟く。
工場を中国からタイへ、カンボジアへ、ミャンマーへと移して製品の国際競争力を保とうとする社長には「東南アジアも結構ヤバイよ」と言いたい。
私はミャンマー政府に向かって、まず「お宅はなぜ北朝鮮と国交回復したの? これからも平壌と仲良くやっていくの?」と問いたい。同時にスー・チーには「あんたのお父さんの廟を爆破した北朝鮮を許すんですか」と聞いてみたい。
今後ミャンマーを「安い下請け工場として使いたい点では、韓国産業も日本と同じだろう。だが1983年10月に全斗煥大統領はじめ韓国高官が、ラングーン(いまのヤンゴン)郊外の国父アウンサン廟へ献花に行ったとき、一行が着く直前に廟は遠隔操作の地雷により爆破され、韓国人を含む21人が死んだ。
北朝鮮人2人が生きて捕まり黙秘を続けたが、うち1人は死刑執行直前に北朝鮮の工作員であると自白して死んだ。
ミャンマーは、そういう国家主権を無視する犯罪国家・北朝鮮と、なぜ国交を修復したのか。復交は、北朝鮮とミャンマー双方に、以後どんな利益をもたらしたのか。現在も利害関係があるのか。その疑問が解けない限り、ミャンマーと心を許して仲良くなり、資本を投下したりインフラの整備に協力したりするのは考えものだ、と私は思う。
東南アジアも結構流動する。日本に一定の敬意を払う点は中国人と少し違うが、指導者の損得勘定も素早い。彼らがいかに恣意的に動く人物か、その一例として最近長逝したカンボジアのシアヌーク前国王(享年89)の話をしたい。
私が日本人記者6人か7人の一員としてプノンペンの王宮でシアヌークに2時間40分ものインタビューをしたのは1967年11月だった。
泊っていたオテル・ロワイヤルからシクロ(足踏み3輪車)で王宮に乗りつけた。
出迎えた侍従に「何分間くらい頂けますか」と訊くと「皆さんの質問がつまらなければ3分間。面白ければ無制限」との返事だった。みなで相談し、私が英語で代表質問することにした。シアヌークの表芸は旧宗主国のフランス語だが、こっちは誰もフランス語会話ができない。ポチェントン空港に国民を集めて演説しても、興が乗ってくるとフランス語で喋っていたという殿下である。記者団のうちNHKの2人は、デンスケ(携帯録音機)を担いでいた。
ちょっと時間を巻き戻して、前日の話をする。
われわれがプノンペンに入った最大の目的は、ジャクリーン・ケネディの取材だった。JFKがダラスの凶弾に斃れてからまだ4年、ジャクリーンは世界の同情を集める若き未亡人だった。それがシアヌークの招きに応えてカンボジアに来る。
東南アジアはベトナム戦争の真っ最中だった。シアヌークはカンボジアの不戦中立を宣言し、米軍機の領空侵犯を厳禁した。
ところがジャッキーは米軍の小型輸送機に乗って空港に着いた。赤い絨毯が敷かれ、ドアが開いてピンク色のスーツに例のピルボックス・ハットを被ったジャッキーが降りてきた。シアヌークは進み出て彼女の手を取り、片膝を少し曲げてジャッキーの手に接吻した。あんたアホちゃうかと、私は言いたかった。
その夜、プノンペンの映画館でシアヌーク自作自演の映画の上映があった。一階は一般国民、二階は外交団や我ら外人記者だけの特権階級の席だった。日本大使によると、欠席したら後で必ず嫌がらせをされるとのことだった。
映画はシアヌークがカンボジア軍の司令官になって国境から侵入してきたタイ軍を打ち破り、最後はモニク夫人演じる従軍看護婦長と熱いキスを交わすという、世にも他愛ない筋書だった。映画の後で特権観客全員にシャンパンが出た。
殿下とのインタビューに戻る。入ってきたシアヌークは、いきなり「昨晩の映画どうだった」と尋ねた。記者全員が「ベリー・グッド」と答えた。私の番が来た。
「あまり感心しませんでした」思い切って私は答えた。
「どこが悪かったのか」
「最後のキス・シーンが短すぎました」私は答えた。
シアヌークは大いに照れた。照れながら「お前は巧いこと言う」と言い、彼も私も笑った。おかげでインタビューは延々と続き、NHKの人が「もうテープがない」と手で合図したので、私は打ち切った。
王宮を辞した後、私は各社から「お前は媚びへつらうのが巧いよ」と総攻撃を食った。
ほぼ50年前のことだから、東南アジアもその後は変わっただろう。だがかつては、おめでたい方々が好きなように国を動かしていた。ミャンマーも、何が起るか知れない。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。