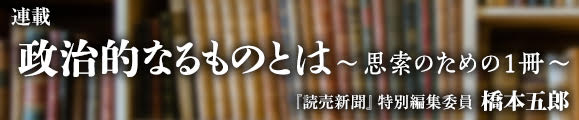1971年3月、大平正芳は『日本経済新聞』に「新権力論」(『大平正芳全著作集3』講談社)というエッセーを発表した。この時大平は何の役職にも就いていなかったが、前尾繁三郎から宏池会代表を引き継ぐことが決まっていた。大平はこの中で、マキャヴェッリの政治哲学について、「運命の奔流を制御して徳の実現に至る手段と術策を工夫し組織しなければならない。そこにいうところの権謀とか術数とかいうものが考えられることになるというのが(中略)骨組みのように私は理解しておる」として次のように書いている。
権力というものを考える場合でも、権力自体の構造や機能を掘り下げるだけではなくて、それを必要とするより高次のものを予定しておるものだという消息を心得てかかる必要があるように思われる。権力というものが、それ自体孤立してあるものではなく、権力が奉仕する何かの目的がなければならないはずだ。権力はそれが奉仕する目的に必要な限りその存在が許されるものであり、その目的に必要な限度において許されるものだということだ。
大平は権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけない、大義がなければいけない、目的が明確でなければならないという信念を持っていた。こんなエピソードがある。「四十日抗争」という自民党内を真二つにした大平と福田赳夫の確執の最中、宮澤喜一(のち首相)が初めて東京・瀬田の大平の自宅を訪ねた。必ずしもそりのあわない二人だったが、宮澤はこう激励した。
「あなたがどんなに権力闘争がお嫌いか、分かっているつもりです。私はこういう戦いには何の役にも立ちませんが、あなたが権力闘争をしてらっしゃるんじゃないことだけはよく分かりますから、どうかそれだけは誰が何と言おうと気にとめないで頑張って下さい」
このエピソードを私は、大平の生涯を描いた辻井喬の『茜色の空』(文藝春秋)で知った。下世話な表現で言えば、大平とは決して仲がよくなかった宮澤が、一番大平の大平たる所以を知っていたのかもしれない。
二者択一の限界を越える
大平の政治哲学の根底には、こうした「謙抑的」姿勢に加えて、「楕円の思想」があった。大平は昭和13年(1938年)正月、新年拝賀式で横浜税務署長としての訓示を行った(『大平正芳全著作集1』)。大平が最初に「楕円」という言葉を使った演説と言われているが、「楕円の思想」の意味が集約的に表現されている。
行政には、楕円形のように二つの中心があって、その二つの中心が均衡を保ちつつ緊張した関係にある場合に、その行政は立派な行政と言える。例えばその当時支那事変の勃発と共にすべりだした統制経済も統制が一つの中心、他の中心は自由というもので、統制と自由とが緊張した均衡関係に在る場合に、はじめて統制経済はうまく行くのであって、その何れに傾いてもいけない。税務の仕事もそうであって、一方の中心は課税高権であり、他の中心は納税者である。権力万能の課税も、納税者に妥協しがちな課税も共にいけないので、何れにも傾かない中正の立場を貫く事が情理にかなった課税のやり方である。
この時大平は28歳である。元学習院大学教授香山健一は「大平正芳の政治哲学」(『大平正芳とその政治 再論』PHPエディターズ・グループ)で、大平の楕円の哲学について次のように解説している。
それは、近代合理主義の「Aか非Aか」――肉体と精神、理性と感情、神と悪魔、体制と反体制、支配階級と被支配階級、右翼と左翼、資本家と労働者、権利と義務、自由と統制、集団と個人、利己と利他等々と際限なく物事を二つに分割していく「二分法」(dychotomy)――の二者択一的思惟の限界を越えようとするものである。
昨今、「多様性」という言葉が流行っている。多様性という名の下に、これまで積み重ねられてきた伝統的な考えを問答無用に否定するというおかしな現象もみられる。「楕円の思想」はそれと比べればはるかに深いように思う。大平が20代でこのような精神領域に到達していることにあらためて驚きを禁じ得ないのである。
「任怨 分謗」の精神
「政治とは鎮魂である」。第2次大平内閣で労働大臣を務めた藤波孝生は、閣議が終わると「お茶を飲んでいけよ」と呼び込まれ、官房副長官の加藤紘一とともに大平と話し込むことがしばしばだった。その時大平はよく、この言葉を口にした。政治の究極の目的とは、人々の魂を鎮めることなのだ。しかし、現実を見れば、人々の魂を騒々しくさせている政治家ばかりではないか。藤波はそう思って、心に深く刻んだのだった。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。