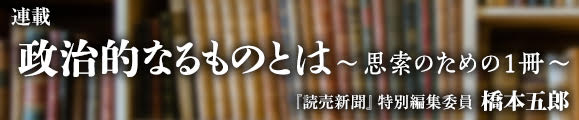2025年2月25日、東京・千代田区の帝国ホテルで、前年12月19日に98歳で亡くなった読売新聞主筆、渡邉恒雄の「お別れの会」が行われた。午前10時半から4回に分けて献花を受け付け、参列者は高円宮妃久子さまはじめ政財界や野球界などから3900人に上った。会場には渡邉の足跡をたどる追悼展も企画され、「終生一記者」「販売第一主義」「活字文化への思い」「日本テレビとともに」「プロ野球界における足跡とスポーツ界への貢献」「執務室とその素顔」の全6章で構成されていた。駆け出しの記者時代のスクープ記事や主筆として執筆した社説、1994年11月3日に発表された「読売憲法改正試案」の紙面などがパネルで展示され、それはそのまま「傑出した戦後メディア人」の全貌を物語るものとなった。
中でも目を引いたのが、東京・大手町の読売新聞グループ本社から運ばれた机やソファなどで再現された「執務室」である。机の上には、最後に椅子に座って読んだ読売新聞の11月26日の朝刊が広げられていた。脇の本棚には、学生時代から親しんだ哲学書が並べられている。『安倍晋三 回顧録』(中央公論新社)は2カ所にわたって置かれている。そばには幼くして父を失った渡邉恒雄が父と慕った元自民党副総裁、大野伴睦の書や盟友中曽根康弘執筆の書「渡邉恒雄の碑」が掲げられている。自宅マンションのベランダに飛来する鳥などを撮った一眼レフカメラや愛用したパイプなども公開された。
これらは児玉明子秘書部長を中心とした読売新聞秘書部のアイディアだという。おそらく最期の一瞬まで仕事をした渡邉恒雄の姿を「永遠の今」として刻んでおこうと、さまざまな角度から写真に収め再現したのだろう。再現にあたってもっとも腐心したのは、いかに元のままの汚い状態にするかということだったという。渡邉恒雄は生前から、自らの葬儀のために流すクラシック音楽9曲をテープにとって残していた。それは葬儀でもお別れ会でも流されたが、主筆室の再現は本人にとって何よりの供養だったに違いない。
マスコミの「タブー」を破った憲法改正試案
渡邉の死にあたっては、「戦後メディア界のドン」の終焉として、功罪相半ばする論評が行われている。私にとっては仰ぎ見るだけの存在ではあったが、50年以上の長きにわたって比較的近くで見てきた者として、最大の功績は、ジャーナリズムの重要な役割として「提言報道」を位置づけたことだと思う。ジャーナリズムには事実を正確に伝える「報道」と、その事実がどんな意味を持つのかという「解説」の二つの機能があると言われてきた。国論を二分するような重要な課題について報道機関として賛否を明確にするなどということは、マスコミの「中立性」を犯すものと思われてきた。
渡邉はその「タブー」を破った。そのさきがけとなったのが1994年11月の読売憲法改正試案の発表だった。自衛隊について国民の多くが認めている。しかし、憲法学者の7割は違憲だと断じている。このような事態を放置していいはずがない。プライバシーの権利をどう守るかなど日本国憲法制定時には想定されなかった問題もある。この際、日本人自身の手で新しい時代にふさわしい憲法を作ろうと、社内に「憲法問題調査会」を組織し、2年間かけて、一字一句新たな憲法案を作ったのである。
国家と国民を守るもっとも枢要な組織であるはずの自衛隊に「違憲」の烙印が押されているのはどう考えても不健全である。正す方向は二つしかない。自衛隊を解体するか、それとも憲法9条を改正するかである。そう思ってきただけに、調査会のメンバーに選ばれたのは嬉しかった。その一方で、閣僚が憲法改正を口にするだけで首が飛ぶという時代状況を考えれば、一報道機関が憲法改正案を作ることには相当の反発が予想された。新聞の部数が減ることも覚悟しなければならず、時期尚早ではないかという思いもあった。しかし、渡邉恒雄に迷いはなかった。決して揺るぐことはなかった。
憲法改正試案が発表されると案の定、激しい批判が寄せられた。それは大きく分けて三つあった。第一は、憲法9条を改正して自衛隊を「自衛の組織」として認めることに対する左の勢力からだった。9条改正は戦争への道を開くものだというのである。第二は、右からの批判である。現憲法は第一章が「天皇」だが、天皇主権から国民主権に代わったのだからという理由で「国民主権」を第一章にしたことが攻撃の的になった。第三の批判は、朝日新聞はじめマスコミ各社の批判である。新聞社が改憲の片棒を担ぐとは何事か。マスコミはあくまでも中立的であるべきだというのである。
当時はインターネットで炎上などという時代ではなかったが、抗議のファクスや葉書が殺到した。その多くが同一文章であり、明らかに組織的なものだった。読売新聞は不測の事態に備え、警察に相談した。私の家も最寄りの高尾警察署が一日4回も見回りするほどだった。結果的に、部数が減ることはなかった。自衛隊を正当に位置づける必要性を多くの人が感じていたからだろうし、部数が減る恐れがあるにもかかわらず、タブーに挑んだことへの共感もあったのかもしれない。
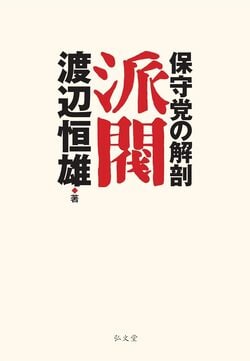
「政権寄り」批判への反論
提言報道はこれで終わらなかった。総合安全保障政策大綱や内閣・行政機構改革大綱、さらには地方自治、経済政策、教育、税制改革、医療改革などあらゆる分野について具体的にどうあるべきかを提言してきた。さらに、狭い意味での提言報道を超えて世に問い、大きなインパクトを与えたのが「検証 戦争責任」である。満州事変から日中戦争、太平洋戦争に至るまでの政治・軍事指導者の責任について徹底検証した。マスコミの責任も含めて日本人自らの手で検証することは、過去の反省にとどまらず、これからの日本を考えるうえでも必須の作業だったと言っていい。
渡邉恒雄と政治との関係については次回で触れることにするが、提言報道も含めて読売新聞に対しては、常に「政権寄り」という批判が付きまとっている。その根底には、「マスコミの唯一無二の役割は権力批判にある」という牢固としたマスコミ観がある。朝日新聞はじめ多くのマスコミが発している言葉であり、大学のマスコミ論などでもあたりまえのこととして教えられている。
しかし、私はそうは思わない。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。