
岡本隆司氏の最新刊『物語 江南の歴史』(中公新書)は、中国史を「乾燥地域(北方)」と「湿潤地域(南方)」という生態史観的な視角から捉え直す。南方の商人や知識人層と北方の政治的権威の相克と相互依存は、現代の民間IT企業と共産党政権の関係にも引き継がれている。梶谷懐・神戸大学教授が詳解する。
* * *
いかに歴史を語りなおすか
本書の著者、岡本隆司氏は日本を代表する中国史の研究者で、非常に多作なことでも知られている。だが、歴史家としての岡本氏が傑出しているのは、単に出版点数が多いという点にとどまらず、それぞれの著作において関連した内容が相互に補完し合い、それこそ壮大なサーガ(物語)のように密接につながっている、というところにある。そこに共通する姿勢は、あえていうなら専門とする中国史を橋頭堡として、西洋からの借り物ではない、独自の視点を獲得したうえで、改めて「歴史」そのものを語り直す、という著者の強固な意志である。その意味で本書は、「離れの奥座敷」たる四川から始まって、黄河と長江の中間に位置する淮河以南のエリアに焦点を当てた、中国史の語り直しの試みだといえるであろう。
ではなぜ、そのような広大な「南方」エリアに注目して中国史を語り直す必要があるのか。そこには近年の著者の作品群を貫く、生態史観的な問題意識が関係している。それは、ベストセラーとなった『世界史とつなげて学ぶ中国全史』の見出しタイトルを借りるなら、「乾燥地域と湿潤地域が人々の暮らしを二分した」という認識にたって中国史のダイナミズムをとらえようとするものである。本書において、「中国史とは、北方中原に発祥した文明が南進した歴史」であり、「かつまたその『南』が独自に発展してきた歴史でもあった」と説かれているのは(237頁)、そういう意味にほかならない。重要なことは、このような乾燥地域と湿潤地域の二分法は、世界史のダイナミズムを捉える上でも有効な概念だ、という点である。ここに、中国国内における「乾燥地域」=「北方」と「湿潤地域」=「南方」との関連性について考察を深めることは、世界史における乾燥地域と湿潤地域が織りなすダイナミズムを捉えることにつながる、という著者の姿勢も垣間見えてくるであろう。
長江下流域を中心とした経済のつながり
そんな本書の中でも、中心的な役割を果たしているのはやはり経済的な先進地域であった長江下流域、『東方見聞録』にいうところの「カタイ(中国北方を支配していたキタイ〔契丹〕民族にちなむ呼称)」に対する「マンジ」である。中国史に詳しくない人でも「蘇湖(蘇州ならびに湖州)熟せば天下足る」ということわざについて、社会の教科書などで一度は目にしたことがあるだろう。実はこの言葉に、著者が注目する、広域の「江南」における生態史観的なダイナミズムを理解するカギが隠されている。
蘇湖、すなわち長江下流域は早くから灌漑設備や平坦な土地の造成など、穀物生産のための土木技術が発達し、宋代には一大穀倉地帯となっていた。このため、江南デルタで収穫が豊かな場合、中国全土の穀物消費が満たされると言われたのが、上記のことわざの意味するところである。15世紀になると、そこに綿花栽培と養蚕が加わり、農業の副業として紡績、製糸、機織りが普及し、軽工業が大いに発展する。つまり、江南は中国で真っ先に工業化したのだ。
もともと人口の多かった江南デルタには、商工業の発展に伴って一層多くの人びとが流入したため、食料を自給することができなくなる。そこで前景に出てくるのが長江中流域の「湖広」と呼ばれる地域である。今は湖北と湖南と呼ばれる地域で、「湖」とは洞庭湖のことを指す。古代においては交通の要衝であり、明朝になるとこの地域は本格的な開発が進み、面目を一新した。江南が工業化したため、食料が不足し、未開発だった上流の地域に水田を作り、食料の供給地ならびに、江南の工業製品の消費地としての役割を担うようになる。そこに「蘇湖熟せば、天下足る」が「湖広熟せば、天下足る」と変化した背景がある。
一方、黄河流域の北京及びその周辺一帯は、多数の官僚・軍隊を抱える一方で、生産力が低く、物資は黄河と長江とを結ぶ「大運河」を通じて調達するシステムがすでに出来上がっていた。こうして、15世紀から16世紀の中国では政治・軍事を扱うのが北京、製品を作るのが江南、食料を生産するのが湖広というように地域がそれぞれの機能に特化し、お互いに補完し合う分業システムが成立した。つまり、中国の発展を考える上で「北方」と「南方(江南)」との関係を考えるのはもとより重要だが、「江南」のコアたる長江下流域の発展も、より内陸の「江南」との関係の中で新たにとらえ直す必要がある。これが、著者がより広域の「江南」に着目し、中国史を語り直そうとする最大の理由であろう。
いっぽう、長江下流域が上記のような中華世界の「内側のつながり」の中心にあるとしたら、「外側とのつながり」の中心的な役割を果たしたのが「瘴癘(しょうれい=感染症)」 の地とされながら、海外貿易のフロンティアとしての役割を果たし、それゆえに近代における「革命」の原動力ともなった福建および広東という華南地域であった。本書ではそれに加え、「離れの奥座敷」としてチベットなど西方の地への漢民族の移住・入植のゲートウェイとしての役割を果たしてきた四川までもが「北方」に対置される「南方」の多様性を象徴する存在として登場する。
「国つくりの論理」と「人つなぎの論理」
しかし、このような各地域の多様性に基づく分業体制は、必ずしもお互いの「ウィン=ウィン」関係の成立を意味しなかった。政治の中心である北京は、不均一で多様な国土において、常に均一な直接の支配を及ぼすことにこだわったからである。それは時に、経済的に進んだ江南、なかんずく長江下流域に対し、北方の遅れた地域に歩調を合わせるための圧力として働いた。このような状況は、江南地域において、とくに商人や知識人層が「北方」に対する批判精神を通奏低音とする独自の文化や思想が発展する素地を生んだ。その象徴が官職につかずに屈折した地域エリートとしての生き方を選ぶ、「郷紳」と呼ばれる独特の社会階層の存在であり、またときに「過激思想」と評された陽明学を講じる李卓吾や 考証学の祖・顧炎武などの知識人であった。しかし、そのような批判精神は、「北方」の政治的権威に真っ向から背くことはせず、一面では依存していることを自ら内面化するものであった。著者の言葉を借りれば「自己に確固たる理念信念、主義主張などがありながら、長いものに巻かれる、世情に迎合しがちな行動様式が勝ってきた」(149頁)のである。
このような「南」と「北」との一筋縄ではいかない関係を、丸橋充拓氏はその著書『江南の発展』のなかで「国つくりの論理」と「人つなぎの論理」の相克として表現している。専制的な君主の側からトップダウンで下りてくる「国つくりの論理」に対して、商工業に従事する人々はそれをある程度受け入れつつ、同時に、いざというとき頼りにできる仲間との横方向の連携を広げるという「人つなぎの論理」でこれに対応した、というわけだ。「北」の統治体制に対して「南」の商人や知識人が常に抱いていた鬱屈した感情と「長いものに巻かれる」処世術によって育まれてきたのが、まさにこの「人つなぎの論理」だといえるだろう。
「江南」からみたこれからの中国社会のゆくえ
さて、このような生態環境の違いに起因する「北方」と「南方」の相克と相互依存、という観点から中国史を理解し直すことは、現代中国社会を理解する際にどのような示唆を与えてくれるのか。ここで注目しておきたいのが、中国の伝統的な統治システムと、西洋社会におけるそれとの本質的な差異だろう。
この点に関し岡本氏は、別の著作『世界史序説』の中で、西洋における統治のあり方の特徴を「君主と臣民が一体化する」ことに求めた上で、中国をはじめとしたアジアではそういった君民が一体となるような体制がなかなか形成されなかった、ということを強調している。すなわち、「貿易・金融と生産を一体化し、さらにそれを政治軍事と一体化した構造体であって、その核心に君臣・官民を一体とする『法の支配』が存在した」(同書238頁)西洋とは異なり、アジアにおいては生態系が多様であり、政治・経済をそれぞれ多元的な主体が担っているため「全体が一体に還元できないし、全体を律する法制も存在しえない。厳密な意味で官民一体の『法の支配』が機能しない」(同書240頁)、という結論が導かれることになる。これは、もっぱら東アジアにおける生態系の多様さを念頭に行われた記述だが、その議論はそのまま「北方」と「南方」の多様性を内包する中国一国についてもあてはまる、というのが、本書を貫く視点であることは今さら言うまでもないであろう。
さて、このような「全体が一体に還元でき」ず、それゆえに「官民一体の『法の支配』が機能しない」という中国における統治システムの特徴は、現代の共産党体制の下でもほぼそのまま存続していることに気づかされるだろう。特に、批判精神と面従腹背をベースとする「南方」の商人と「北方」における統治のロジックとの相克という本書で描かれた構図は、近年躍進が著しい民間のIT企業と、共産党政権との「持ちつ持たれつ」ともいうべき特殊な相互依存関係として、まさに現代に受け継がれていると考えられる。
そのことを象徴するのが、2020年11月におけるアリババ傘下のアントグループのIPO(新規株式公開)差し止めに端を発し、「共同富裕」を重視するという名目のもとで行われた一連のIT企業への締め付けである。一連の締め付けは、浙江省杭州市を基盤とするアリババ、および広東省深圳市を基盤とするテンセント(騰訊)という「南方」を代表する二大企業をターゲットとした独占禁止法の適用を経て、最終的にこの二社が「共同富裕」政策を実施するための「自発的寄付」として、2025年までに1000億元(約155億ドル)の拠出を約束する、という形で幕を閉じた。この一連の措置に対して、これまで成長を牽引してきた民間IT企業のイノベーションの命脈は絶たれた、という声も内外でささやかれるようになった。
しかし、中国の社会保障問題に詳しい片山ゆき氏によれば、この「自発的寄付」の実態は以下のようなものであった。たとえば、2022年に中国の広州市慈善会は、騰訊基金会、WeChat Pay、微保(テンセント傘下の保険代理販売会社)、太平洋保険会社などと合同で、広州市が認定した生活保護受給者、低所得者向けに、医療保険を提供する慈善活動キャンペーンを開始した。各社の寄付はWeChat Payを通じて行われ、合計すると2022年12月末時点で総額は600万元(約1億2000万円)に達したという。ここに見られるのは、大手IT企業が政府の指導に応じて拠出した「基金」の運用を通じて、本来政府が提供すべき公共サービスを肩代わりし、そのことによって北京からの抑圧を逃れ自らの命脈を保つ、という構図である。ここに、政府に従順な姿勢を見せつつ、その中で可能な限り経営自由度を確保しようとする、かつての南方の商人・知識人から引き継がれた「長いものに巻かれる」処世術のなごりを見ることはたやすいだろう。
本年は、中国の市場経済改革が始まって45年にあたるが、このような政府と民間企業との間の、明文化されたルール、すなわち「官民が一体になった法の支配」に基づかない「持ちつ持たれつの関係」は、形を変えて存続しているばかりか、特定の領域についてはむしろ強化されつつあるのが実情だ。
西側の視点から見れば、鄧小平から胡錦濤までの中国は紆余曲折を経ながら西洋近代のロジックになんとか近づきつつあったのが、習近平政権になってから道を踏み外したように見える。しかし、本書が描き出した、本来的に多様性を抱えているがゆえに、分裂と隣り合わせの、危うい均衡の中にある、という中国像からは、かつて西側諸国から歓迎された鄧小平路線も、そして現在厳しい目を向けられている習近平路線も、その危うい均衡の一つの解でしかない、ということになるだろう。
果たしてこれからの世界において「普通の国民国家」と同様な性質を持つ政治体として中国を扱うことは適当なのか。適当ではないとすれば、「普通の国民国家」はその存在に対してどのように対峙すればよいのか。そのようなより長期的に見た中国との付き合い方を考える上でも、本書を含む岡本氏の一連の著作は、私たちにとって有効な視座を与えてくれるだろう。
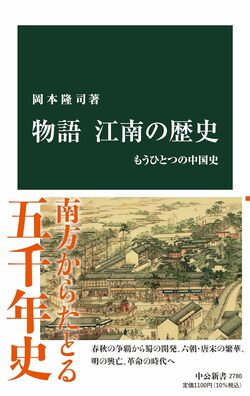
参考文献:
岡本隆司(2018)『世界史序説』ちくま新書
岡本隆司(2019)『世界史とつなげて学ぶ 中国全史』東洋経済新報社
岡本隆司(2022)『明代とは何か』名古屋大学出版会
片山ゆき(2023)「三次分配と保険(中国)」『ニッセイ基礎研究所』
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73630?pno=2&site=nli#anka1
丸橋充拓(2020)『江南の発展 南宋まで』岩波新書












































