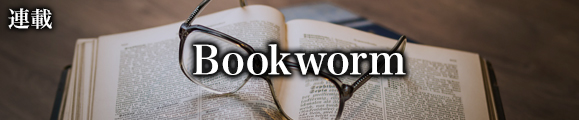恒川光太郎『白昼夢の森の少女』
評者:杉江松恋(書評家)
途方もなく孤独だが心安らぐ
異才、恒川光太郎の傑作短篇集
途方もなく孤独だが心が安らぐ。
恒川光太郎の小説を読むと、森の奥に取り残されたような気分になる。洞窟の中で目を閉じて眠りにつくような、というべきか。最新刊『白昼夢の森の少女』に収められた10篇の中で、幾度もそんな感覚を味わった。
表題作は人ならぬ存在に変化した者たちを描いた物語である。14歳の〈私〉はある朝、絡まり合った蔦の中にいる自分を発見する。植物はただ身体を取り囲むだけではなく、その中に管のように入り込んでいたのである。やがて〈私〉は、同じような境遇の人々が多数いることに気づく。無数の思考が〈私〉の中に流れ込んでくる。蔦を通じて、彼らは一体化していたのだ。
共有夢を通じて群生が出来上がる。植物に近い存在になった〈私〉たちの日々は穏やかなものであり、かつての家族や友人たちのそれとは異なる時間の流れの中に入っていく。そうやって訪れた別れや変化が穏やかな筆致で描かれていくのである。
日常との別れを描いたものでもう1篇のお気に入りは、「銀の船」だ。主人公は幼い頃から、空を飛ぶ巨大な船の存在を信じていた。小さな島ほどもあり、甲板の上には町があって大勢の人々が暮らしている。いつかそれに乗ってみたいという夢は叶わず、短大に入学する年齢になる。ふとした気まぐれで見知らぬ相手と性交をし、妊娠が発覚した2日後、彼女は空に銀の船を見るのである。ここではないどこかへ行きたいという願望が実現した「その後」を描いた作品で、空を行く船から見える風景はひたすら美しいが、そこで主人公が辿ることになる運命は甘いものではない。その苦さが忘れられない余韻となって残る小説だ。
本書は恒川が10年間に発表した短篇を集めたもので、主題の統一がないのが逆に個性を際立たせている。お菓子の話を、との注文になぜか妖怪小説が出来てしまった「古入道きたりて」や、掌篇ながら果てしない奥行きを感じさせる「海辺の別荘で」など、内容は多彩だ。珍しい実話怪談「布団窟」は日常から非日常への落差が本当に意外で、ページをめくった瞬間に奇声を上げてしまった。
怪奇小説としての白眉は「傀儡の路地」だろう。ある行為が原因で理不尽な目にあった主人公が、路地裏で人形を抱いた奇怪な女性に出会う場面から始まる話である。恒川が連れ出す「ここではないどこか」には恐ろしい場所もある、と思い知らされる。危険な香りが漂う。だからこそ誘いに乗ってみたくなるのだ。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。